カルチャー
時間を制する写真、「顔」を制す
文・村上由鶴
2025年10月31日
text: Yuzu Murakami
ちかごろ、割と伝統的なメディアが運営しているネットニュースのサイトでも「これ、写真の選び方がちょっと意地悪すぎないか?」と思うことがあります(そういえば某バラエティ番組でも、悪人顔に見える一瞬の写真をおもしろがるコーナーがありましたね)。
たとえばこちらは、AP通信、ロイターにならぶ世界三大通信社の一つ、AFP通信が、ドナルド・トランプ米大統領が「辞めさせたい」としていた連邦検事が辞任したというニュース。
自分の思い通りにならない人物を要職から排除しようとするトランプ政権の独裁的な傾向を報じる深刻な事件ですが、目を伏せて、口をとがらせる大統領の写真は、かなり強い意図で選ばれた写真だと感じます。
このような意地悪な写真は個人のSNSでの悪ふざけや、著名人への誹謗中傷などではよく見られてきましたが、個人的には、報道においても多く見られるようになっている気がします。こうした写真が「増えている」と感じるのは、アクセス数と収入が直結している現代のインターネット環境において多くの人がクリックしたくなる写真を追求した結果として、頻繁に目にすることになったからかもしれません。一方でこうした写真は数百字程度の短い記事や事件の内容をすっとばして、ある人物の演出された印象を伝えるという効果のほうが強くなっていると思います。「この人物はひどい」「なんという愚かしさだ」と読者に感じさせ、むしろ記事を最後まで読まないように誘導してしまってもいるのではないでしょうか。
もちろん、このような「醜いイメージ」そのものは新しい現象ではありません。20世紀の戦時下のプロパガンダポスターを振り返れば、例えば第二次世界大戦下のアメリカでは、ヒトラーやムッソリーニ、昭和天皇は丸い眼鏡をかけた猿のような小さく愚かな人物のように描かれてきました。日本でも敵国をそのように描写したポスターが多く作られています。
報道写真でも、独裁者の冷酷な横顔や冷戦下のソ連指導者のなにかを企んでいるような表情など、敵対する権力者の政治的イメージを補強するような写真は繰り返し利用されてきました。
このような「意地悪な写真選び」は、実際には、メディアの側だけの仕掛けではなく、受け手である私たち自身の欲望を投影しているともいえます。ある政治家の「悪そうな顔」を見て「ほんと悪いやつ!」と批判的な気持ちに火をくべるようにして、ニュースを感情的な娯楽として消費してしまうのです。このように「愚かさの演出」は、供給するメディアと受け取る読者との共犯関係のうえで成立してきました。
さらに、心理学のある研究ではニュースに「装飾的な写真」があるだけで、それを見た人がそこでの主張を「真実」として受け取りやすくなるということが実験で明らかにされています。となると、こうした悪人顔の写真は単にある人物を愚かに見せる以上に、かなり具体的にわたしたちの行動や心理を左右している可能性があります。
そもそも写真は、瞬間を切り取るという方法によってある人物を無様に見せることができる、という意味で、撮影される人よりも撮影する人が時間的に優位に立つものであると言えます。
友人同士で撮った写真でも「なんでこの顔のときにシャッター押したの?」と文句を言いたくなるような経験は誰にでもあるでしょうし、「なぜこんな顔の写真をSNSにあげた?」というところからトラブルに発展する、なんてこともあるかもしれません。報道写真でも同様に、撮影者はその一瞬を選ぶことで、撮られる側が自らではコントロールできないある瞬間の表情をつかまえて、その人の印象を左右するように発表するのです。このように相手を醜く写す写真(や、それにまつわるトラブル)は、写真のメディアの特性と深く結びついているのです。
ニュース写真に意地悪さを感じるとき、それはメディアの策略であると同時に、私たち自身がそう感じる準備をしているからでもあります。プリクラやカメラアプリのフィルターがかわいさを演出し、強調するのと同じように、報道写真の場合は「愚かさ」や「悪人顔」を盛る。写真は美化だけでなく醜化のためにもずっと使われてきたのです。ではまた!
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
土を集める人を撮る人
文・村上由鶴
2025年9月1日

カルチャー
「みてね」と写真のなかの手
文・村上由鶴
2025年7月7日

カルチャー
想像力を節約する技術
文・村上由鶴
2025年5月31日

カルチャー
写真の(なんかゴタゴタした)夜明け
文・村上由鶴
2025年3月31日

カルチャー
映画「アプレンティス ドナルド・トランプの創り方」と写真戦略
文・村上由鶴
2025年2月28日

カルチャー
インスタグラムのアイデンティティクライシス
文・村上由鶴
2025年1月31日

カルチャー
2024年の写真のロマンティックを振り返る
文・村上由鶴
2024年12月31日

カルチャー
「リンダリンダ」と撮影できない展覧会
文・村上由鶴
2024年11月30日

カルチャー
写真は鏡であったり窓であったりする、けどその前に扉でもある
文・村上由鶴
2024年10月31日

カルチャー
実態のない「秋田美人」
文・村上由鶴
2024年9月30日

カルチャー
正しさよりも優れていること
文・村上由鶴
2024年8月31日

カルチャー
写真とエモーショナルな政治
文・村上由鶴
2024年7月31日

カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
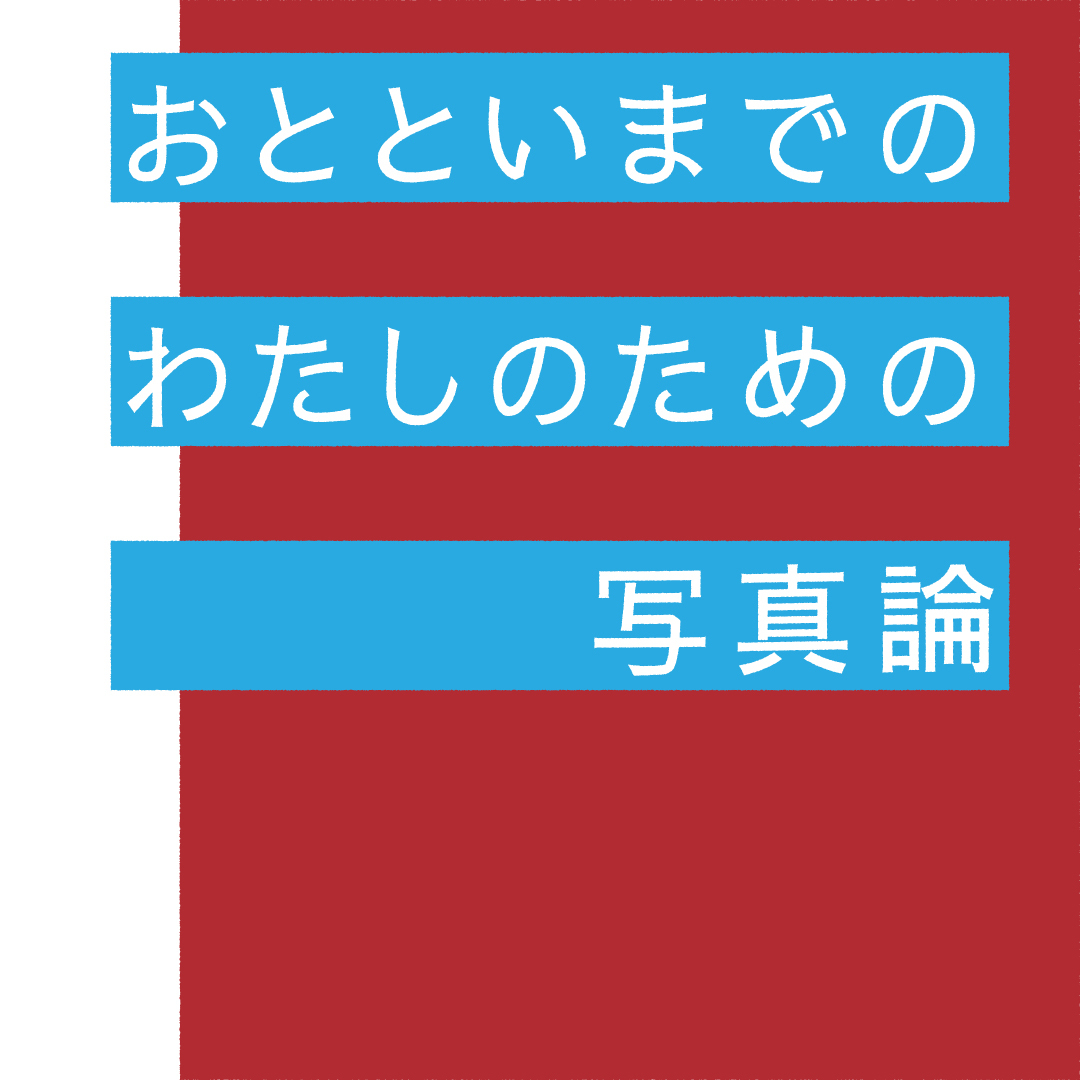
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
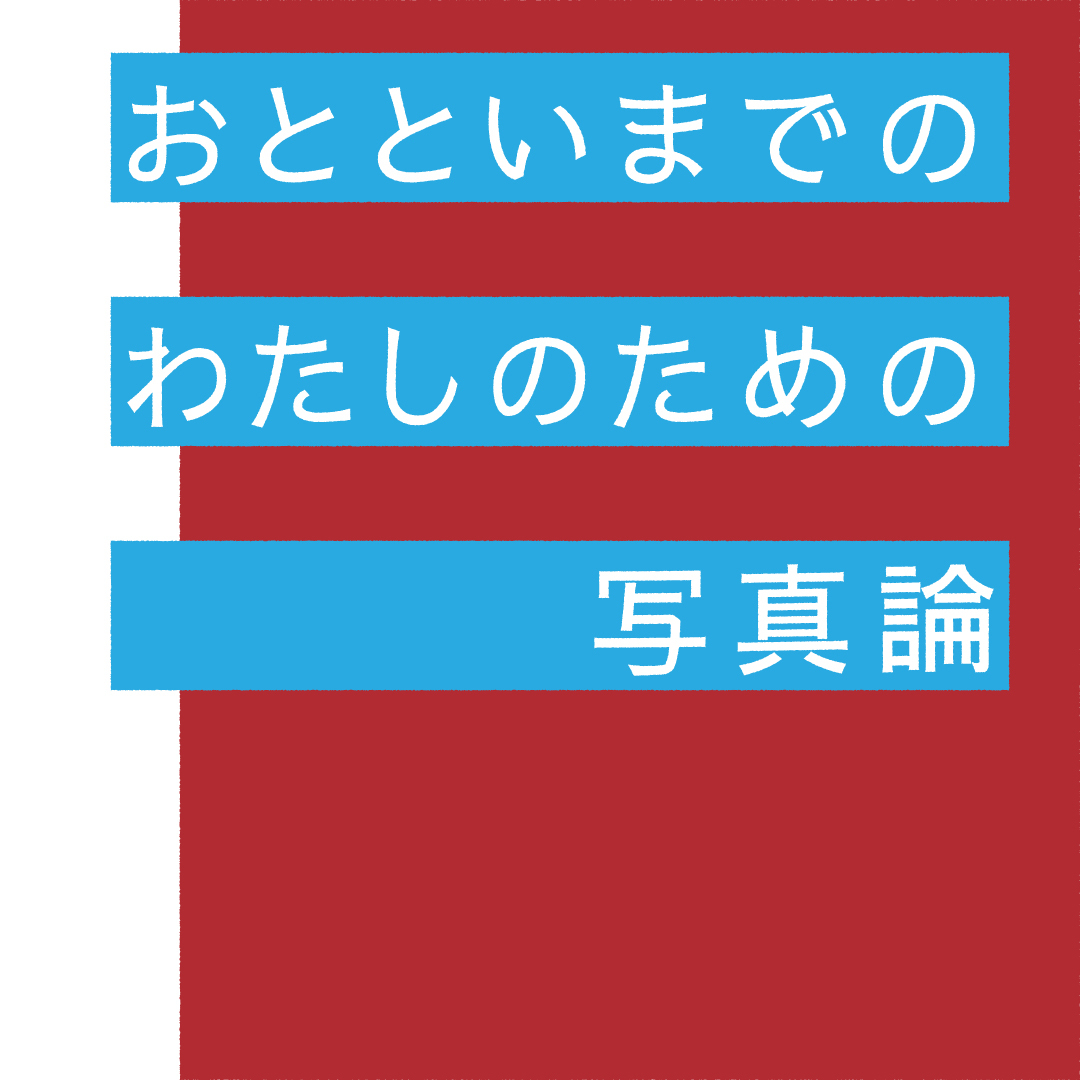
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
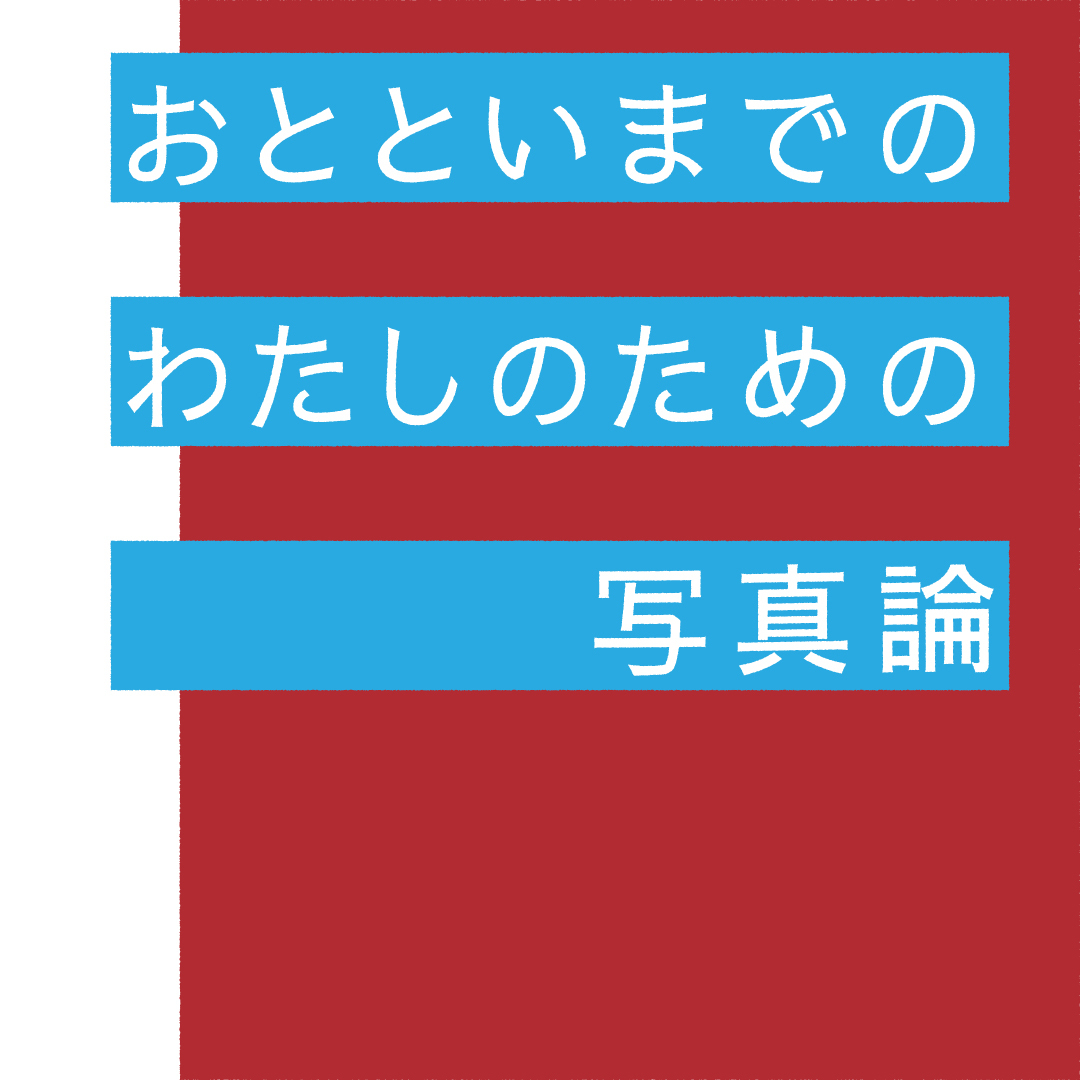
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日




