カルチャー
土を集める人を撮る人
文・村上由鶴
2025年9月1日
text: Yuzu Murakami
毎年甲子園に足を運ぶくらいには高校野球が好きです。
夏の甲子園大会は、熱中症対策や試合日の調整などのために毎年少しずつその運営方法を変えてきました。
わたしはこういう高校野球のアップデートを好ましく思っているのですけれども、そのなかでもわたしが一番気になる変化は、やはり撮影にまつわることです。
夏の高校野球といえば、試合終了後に負けたチームが土を持ち帰るのが慣例であることは、高校野球ファン以外の方にも知られていることだと思います。
改めて思えばこの「土集め」の、地べたに座り込み、がっしりとした体格の青年たちが涙で顔を濡らし、汗をぬぐいながら地面に手を伸ばすという光景はかなり異様です(土下座や埋葬を思わせるところもある気がします)。
しかし、その「異様さ」さえも感動的に見えるのは、やはり選手たちのひたむきなプレーがあるからこそ。加えて、その姿を「感動的」なものにしてきたのは、彼らが土を集める姿を、やはりカメラが「ここぞ!」とばかりにとらえてきたからではないか、と思います。
では、その「土を集める人」の姿がどのように撮影されてきたかといえば、長らく、各社のカメラマンがグラウンドに這いつくばって下からあおって見上げるように撮られてきました。いわば、甲子園では「土を集める人」とそれを「這いつくばって撮る人」がセットで慣例になってきたのです。球場で実際に試合を見ると、試合後、球場の興奮も冷め切らないなか、這いつくばって球児の泣き顔を撮ろうとするカメラマンの姿に、すごいプロ根性だなと感心すると同時に、どこかさもしさを感じてしまう、ということもありました。
ところが、ここ数年、土を集める姿と、それを撮るカメラマンの姿に変化が現れています。
というのも、コロナ禍では、ベンチの消毒などの感染防止対策に時間を要するため甲子園の土を持ち帰るのが禁止とされた時期がありました。2023年から改めて解禁となり、その間に撮影者のルールに変更があったのでしょう(想像するに、阪神園芸が迅速にグラウンド整備を行うため?)。近年は、土を集める選手の顔を撮るためにグラウンドに這いつくばるカメラマンは見られなくなっています。
あの這いつくばっていたカメラマンの姿が見られなくなったことで、改めて思い返すきっかけを得ましたが、やはり、どこかカメラというものの乱暴さが、褒められるべきプロ根性や矜持というよりも警戒するべきものへと社会のなかの意識が変わってきたのではないか、と私は思います。
涙に暮れる球児たちに向けられたカメラマンの奥には、その敗北の瞬間をこそ「感動」として「これぞ高校野球の魅力!」とする観客がいるのは間違いありません。つまり高校野球というコンテンツ自体が、敗北の瞬間に美的な価値を置いてきたのです。
観客席から見れば滑稽にも映る「土を集める人を撮る人」の姿は、単なる職業的なルーティンではなく、あの異様な光景を「感動的」な場面へと仕立て上げてきた力でもありました。そしてその力は、ときに「過剰な感情の演出」として働いてきたと言えるでしょう。球児の涙を拡大し、泥にまみれた頬を敗北の象徴として消費する報道写真は、感動を「記録する」というよりも、「増幅させる」役割を果たしてきたのです。
しかし、近年そうした這いつくばるカメラマンの姿は気付けば過去のものに。「泣き顔を至近距離でとらえた」構図の代わりに、望遠レンズでとらえられる後ろ姿や横顔、あるいはグラウンド全体の中に埋め込まれるような画が紙面を飾るようになっています。
それは「過剰な感情の演出」を抑制し、すこし冷静な立ち位置からの視点で球児の姿を伝えようとする変化にも見えます。甲子園においては土を集める人と、それを撮る人の関係性もまた、少しずつアップデートされているのです。
さて、今年の高校野球は伝統校の暴力事件が明るみに出たことによる試合の辞退もあって、暗い話題が目立ってしまった夏の甲子園でした。確かに、「高校の部活動の範疇にしては色々過剰では?」とか、「丸坊主の伝統ってまだ続けるの?」など、つっこみどころは満載です。
個人的には、高校野球がよりよい方向に変わっていくことができれば、それは日本の社会に大きなよい影響をもたらすのではないか、とわたしは期待しています。そのために高校野球の(盲目的ではない)ファンとして今後もそのアップデート応援していきたいと思っています。沖縄尚学優勝おめでとう!
ではまた!
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
「みてね」と写真のなかの手
文・村上由鶴
2025年7月7日

カルチャー
想像力を節約する技術
文・村上由鶴
2025年5月31日

カルチャー
写真の(なんかゴタゴタした)夜明け
文・村上由鶴
2025年3月31日

カルチャー
映画「アプレンティス ドナルド・トランプの創り方」と写真戦略
文・村上由鶴
2025年2月28日

カルチャー
インスタグラムのアイデンティティクライシス
文・村上由鶴
2025年1月31日

カルチャー
2024年の写真のロマンティックを振り返る
文・村上由鶴
2024年12月31日

カルチャー
「リンダリンダ」と撮影できない展覧会
文・村上由鶴
2024年11月30日

カルチャー
写真は鏡であったり窓であったりする、けどその前に扉でもある
文・村上由鶴
2024年10月31日

カルチャー
実態のない「秋田美人」
文・村上由鶴
2024年9月30日

カルチャー
正しさよりも優れていること
文・村上由鶴
2024年8月31日

カルチャー
写真とエモーショナルな政治
文・村上由鶴
2024年7月31日

カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
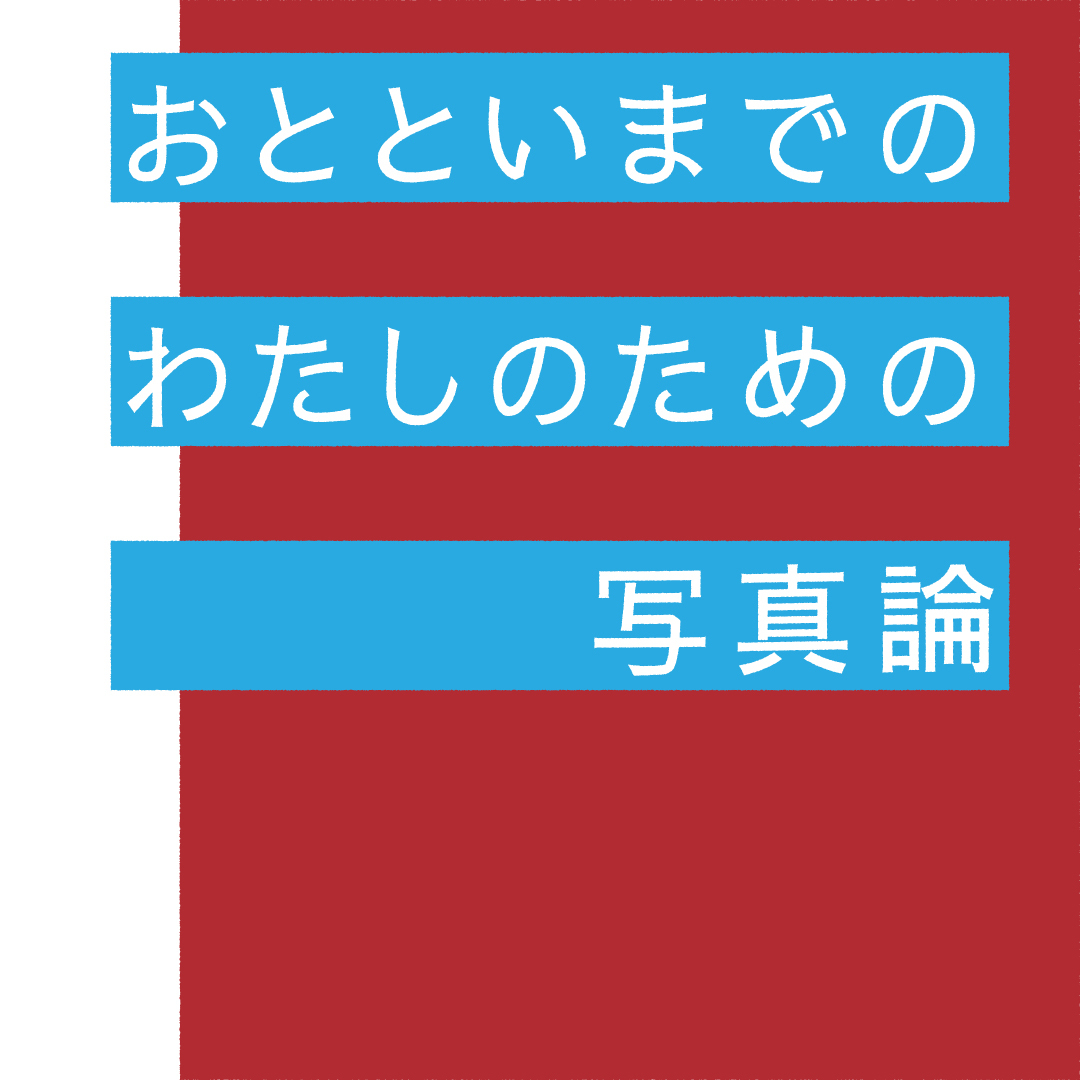
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
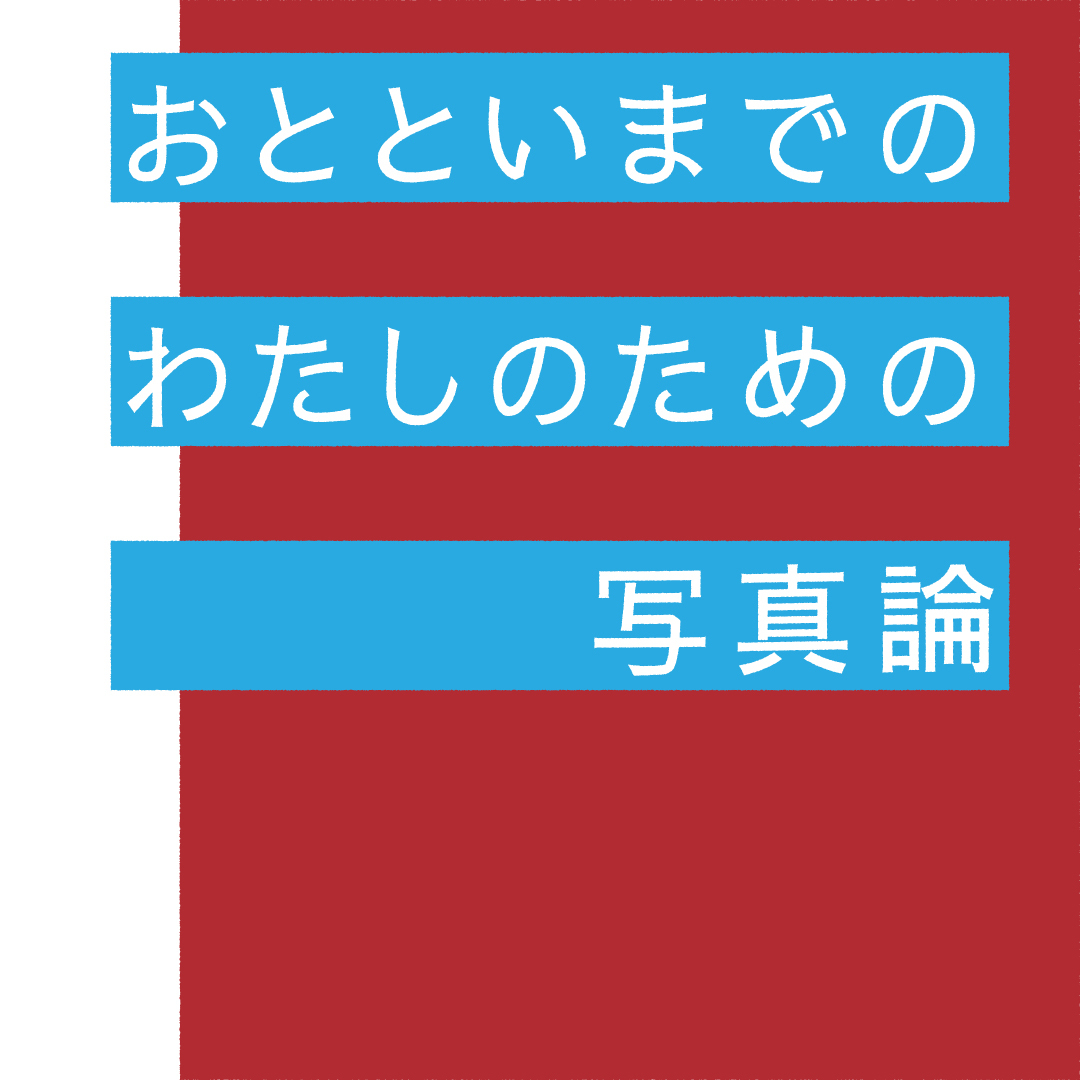
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
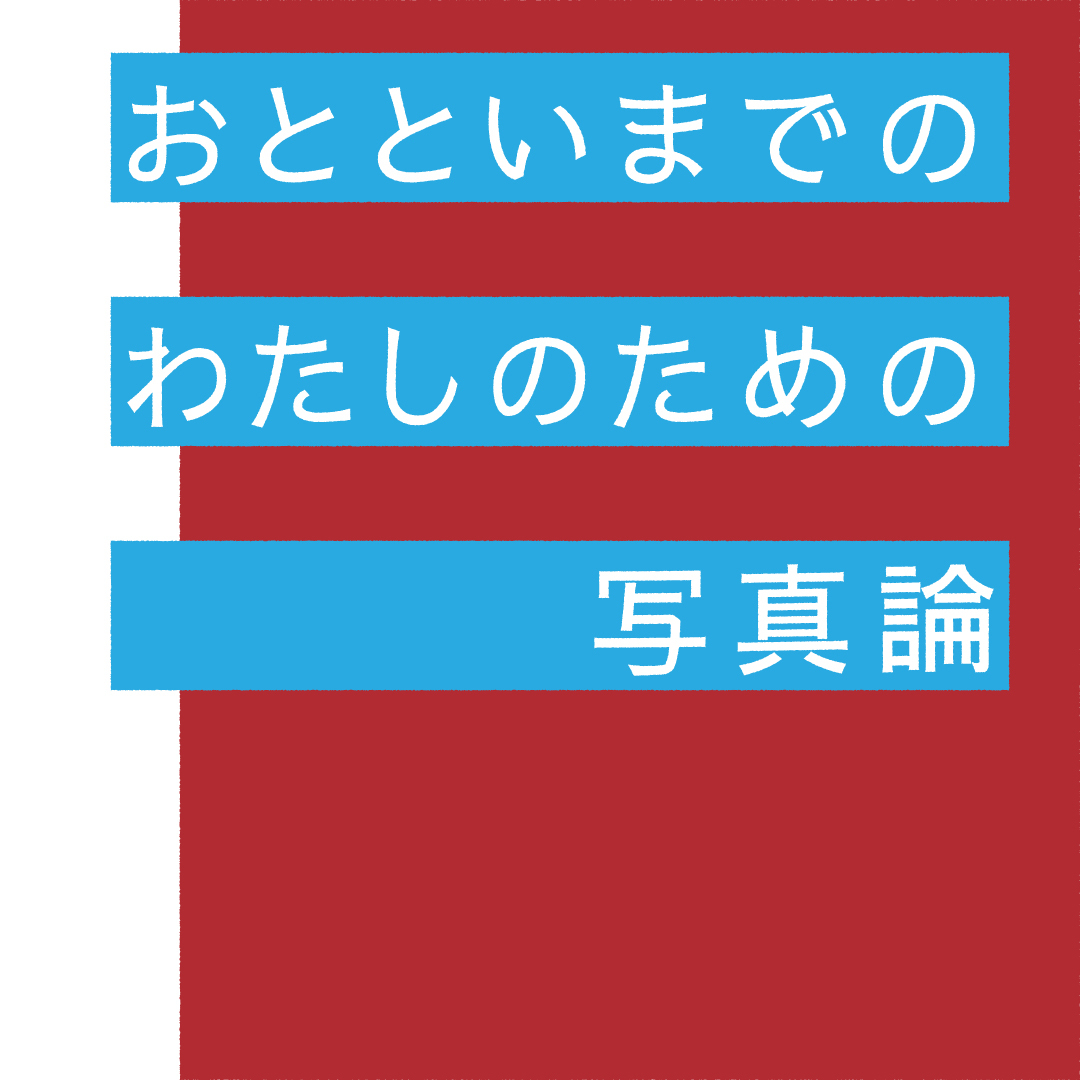
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日




