カルチャー
2025年を振り返る、「音量写真論」
文・村上由鶴
2025年12月30日
text: Yuzu Murakami
実は、わたしはPOPEYE本誌でも「そもそも写真教室」という連載をしていて、このPOPEYE WEBでの連載「おとといまでのわたしのための写真論」とは毎月別の文章を書いています。
本誌1月号の毎年定番のデート特集「ガールフレンド」号は(デートにはあんまりおすすめできない展覧会ですが)アーティゾン美術館で開催中の展覧会「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着」の、志賀理江子さんのインスタレーション作品《なぬもかぬも》について書きました。
ここで白状するとわたしは志賀理江子さんの作品が不得意です。記憶のあるなかではじめて志賀さんの作品を見たのは2013年、金沢21世紀美術館で開催された「内臓感覚 — 遠クテ近イ生ノ声」展で見た「カナリア」シリーズでした。その後発表された写真集「螺旋海岸」でも、写真のなかで、写真のために行われていることを見て、そこまでやる必要が?と思ってしまいました。
志賀さんは、セットアップ写真(協力者に演出をして、その様子を写真に撮る方法)で作品制作をなさっていることが知られていますが、その方法で、わざと観客を嫌な気持ちにしようとしている、というかおどろおどろしい、演出過多の肝試しのように感じられるのです。
もちろん志賀さんが近年扱っているテーマは、東北のこと、原子力のこと、都会的な文明に搾取される地方の労働や資源といった深刻な問題であり、それらに対して向き合う態度として、このような雰囲気の作品だからこそ伝わるニュアンスもあるのでしょう。
たとえば、アーティゾン美術館の展示室を丸ごと使った《なぬもかぬも》は、波打つ写真の中を歩くような作品で、明確にグロテスクなイメージが全面に展開されています。展示室のなかには、この不思議なタイトル「なぬもかぬも」との出会いにまつわるエピソードが書かれていて、志賀さん自身の興奮も伝わってくるし、確かにその言葉に「なにかありそう」というような気持ちにさせてくれます。
わたしももうすぐ秋田で働き始めて2年になりますが、今年は、8月に三菱商事がコスト高騰を理由に、秋田県内の風力発電の事業撤退を表明したこと、そして秋のクマ騒ぎなどを経験して、「経済合理性」の名の下に行われる「地方への諦め」や「切り離し」、中心と周縁の心的な距離など…をひしひしと感じました。特にクマ出没がもっとも頻繁だった時期は、コンビニ行くにも命がけ、街を歩いていて「喰われるかも」という恐怖を感じ、それは新鮮な体験でした。
宮城県(石巻)で暮らす志賀さんが(わたしがいる地域やその事情は違えど)地方の深刻な状況を目のまえになにかを真摯に、一生懸命、切実に伝えようとしていることはわかる。とはいえ、どうも、わたしにはあの《なぬもかぬも》の方法では、そのメッセージが、音量が大きすぎて聞こえにくい。ビリビリと音割れしてしまって、なにも聞き取れず、ただ不快とか、不穏とか、そういう感覚が残る、ということになっているのではないか、と思うのです。
志賀さんが伝えたい社会的な課題やテーマと、そこで展開されるおどろおどろしいイメージは、どんな凄腕DJでもそれとそれを直接つなげるのは至難の技では…?と思ってしまうくらいにわたしにはアクロバティックで、少し無理くりな接続だと感じられます。写真は割とステレオタイプな「恐怖」や「グロさ」のイメージであり、「気持ち悪っ」と思わせるために、実は表層的で「あるある」な視覚的なインパクトにとどまっているのではないでしょうか。
本展の関連イベントとして開催されていた『なぜ原爆が悪ではないのか アメリカの核意識』の著者・宮本ゆきさんとのトークも大変興味深く拝聴しました。また本展には、「反戦反核ライブラリー」も設置されていましたが、これらのイベントや選書を通じて語られることと、実際に展覧会で受け取ることができるメッセージの間には大きな飛躍があるとわたしは感じました。イベントや書籍は、その飛躍の空白を埋める役割を期待されているのでしょう。一方で、写真の、というか会場全体のおどろおどろしい、肝試し的な空気はなにかを鑑賞者に浴びせているとは思いますが、課題や意識づけへの誘導として機能しているのでしょうか。アトラクション的な驚きを与えるだけになってしまってはいないでしょうか。
ところで、そもそも写真は、メッセージや作者の意図などを伝える方法としては、いわば「音量小さめ」であることに矜持を持っているメディアである、とも思います。
たとえば2025年の展覧会で言うと、東京都写真美術館「遠い窓へ 日本の新進作家 vol. 22」展は、もちろんそれぞれの参加作家によって異なる部分はあれど、寺田健人さんのように写真のなかのささやかな兆候に豊かなニュアンスを読み解く作品や、甫木元空さんの作品は写っていない部分へ思考や想像を誘導するような作品だと感じました。
「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」展も、個々の写真が強いメッセージを主張するというより、写真と写真のあいだに生まれる関係性が展覧会全体のリズムをかたちづくっていたと思います。しりとりのように写真の細部がつながっていて、次のイメージへと視線が移っていくように誘導されていき、その過程で鑑賞者は「写真に耳をすます」ようになっていくように仕向けられます。
このように写真は、鑑賞者に耳をすますことを求めてくるところがあります。そういう意味では写真はちょっとかまってちゃんというか、存在としてわざとらしい部分があります(ちなみに、わたしのこの「音量写真論」において、音量がもっとも聞きやすく調整されている事例とするのは報道写真です)。そういう、音量控えめの写真が主流であるなかでは志賀さんの作品は特異なものであり、また重要であるということは疑いようのないこととも思います。
ちなみに、わたしが2025年、一番印象に残っているのは板橋のCOPY CENTER GALLERYで開催された細倉真弓さんの展覧会「曖昧な決定、肉、光」で発表された作品《光触》でした。
さきほどの志賀さんの作品について、わたしは「音量」という言葉でその体験を述べましたが、細倉さんの映像インスタレーション《光触》は、実際に大きな音がする作品で、「映像」という通り、厳密に写真と言えるかは微妙です。それでも、わたしは、これが紛れもなく「写真について」の作品であると感じています。
本作は、暴力的な打撃音として演出されているシャッター音とほぼ同期して、モニターにストロボを使用して撮影された木の枝の写真が映し出される作品です。
会場では、戦争映画か?と思うほど大きな音がして、びっくりするのですが、それよりも驚くのは、一瞬、映像が消えて真っ暗になったとき、自分の網膜に木の枝のイメージが稲光のように残像として生理的に焼き付くこと。自分の目がカメラとほとんど同じ機構であることを体感させられます。そして、この網膜に焼き付いて「見えている」残像が、実は誰とも共有できないことにも気づきます。細倉さんは、「この視点」を持っているのは「このわたし」だけであり、それを誰かと共有することはできない、という本来は孤独な「見る」という経験について、探究してきました。わたしは本作について、それを純化させた作品だと思いました。
銃撃の音のように演出されたシャッター音は、実際に耳に届く音としてはもちろん大きな音です。しかし、作品全体として「音量写真論」的に言えば、それは決して大音量ではなく、むしろ「見ること」や「撮ること」に伴う孤独や共有できなさをもっともクリアに伝えるために研ぎ澄まされた静けさだったと思います。本作は2025年2月に見た作品でしたが、わたし的には今年一番の「写真」でした!
来年の写真もたのしみです!ではまた!
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
時間を制する写真、「顔」を制す
文・村上由鶴
2025年10月31日

カルチャー
土を集める人を撮る人
文・村上由鶴
2025年9月1日

カルチャー
「みてね」と写真のなかの手
文・村上由鶴
2025年7月7日

カルチャー
想像力を節約する技術
文・村上由鶴
2025年5月31日

カルチャー
写真の(なんかゴタゴタした)夜明け
文・村上由鶴
2025年3月31日

カルチャー
映画「アプレンティス ドナルド・トランプの創り方」と写真戦略
文・村上由鶴
2025年2月28日

カルチャー
インスタグラムのアイデンティティクライシス
文・村上由鶴
2025年1月31日

カルチャー
2024年の写真のロマンティックを振り返る
文・村上由鶴
2024年12月31日

カルチャー
「リンダリンダ」と撮影できない展覧会
文・村上由鶴
2024年11月30日

カルチャー
写真は鏡であったり窓であったりする、けどその前に扉でもある
文・村上由鶴
2024年10月31日

カルチャー
実態のない「秋田美人」
文・村上由鶴
2024年9月30日

カルチャー
正しさよりも優れていること
文・村上由鶴
2024年8月31日

カルチャー
写真とエモーショナルな政治
文・村上由鶴
2024年7月31日

カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
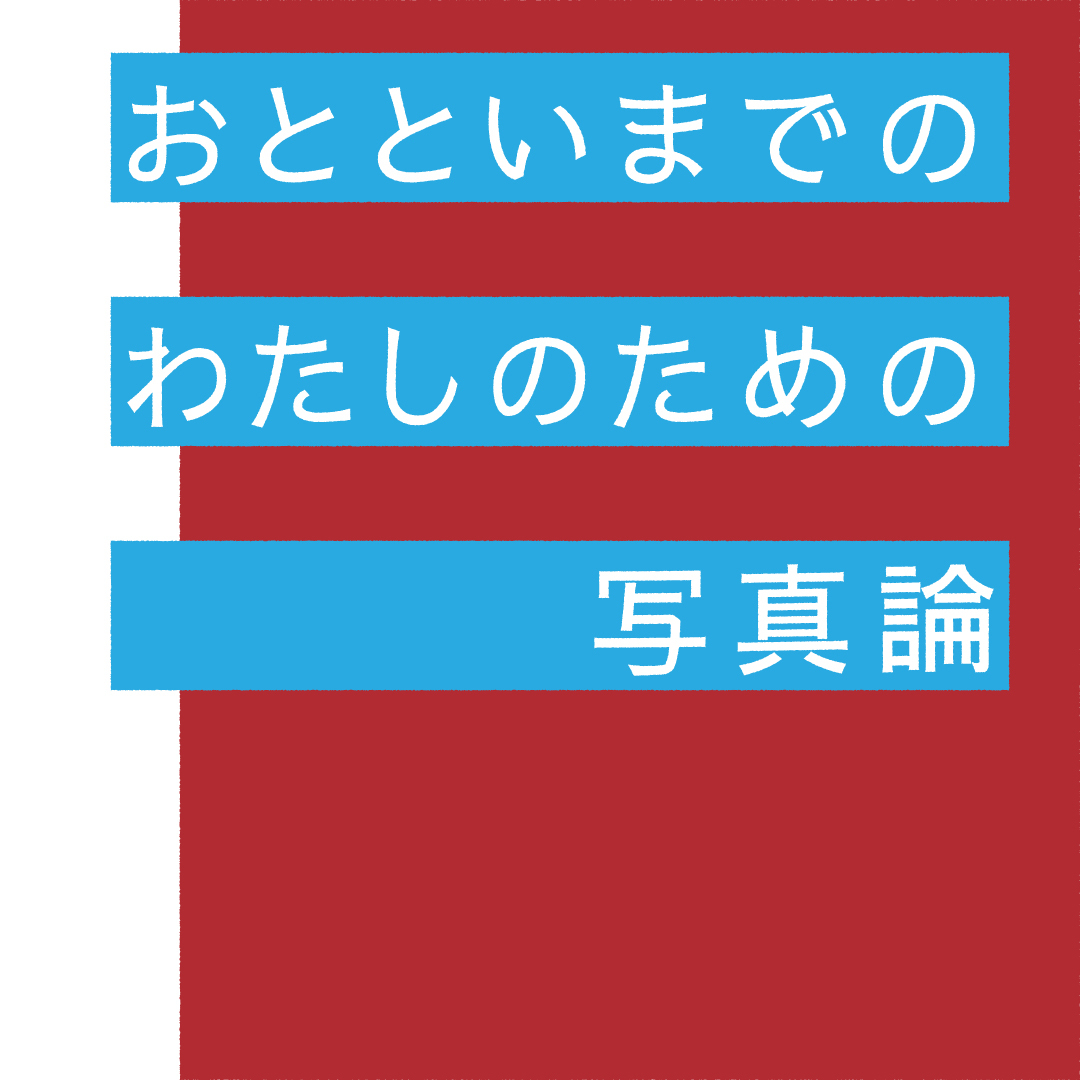
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
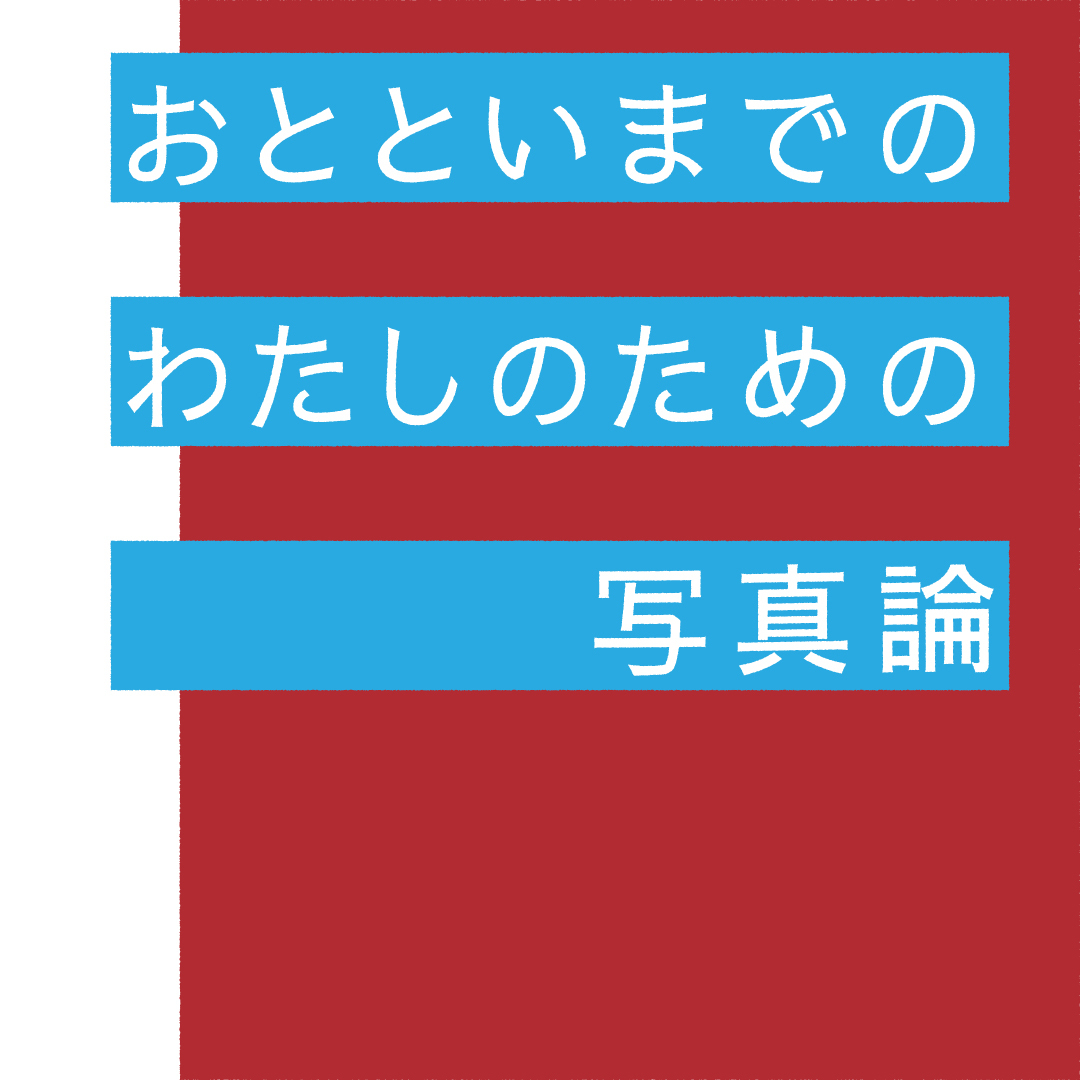
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
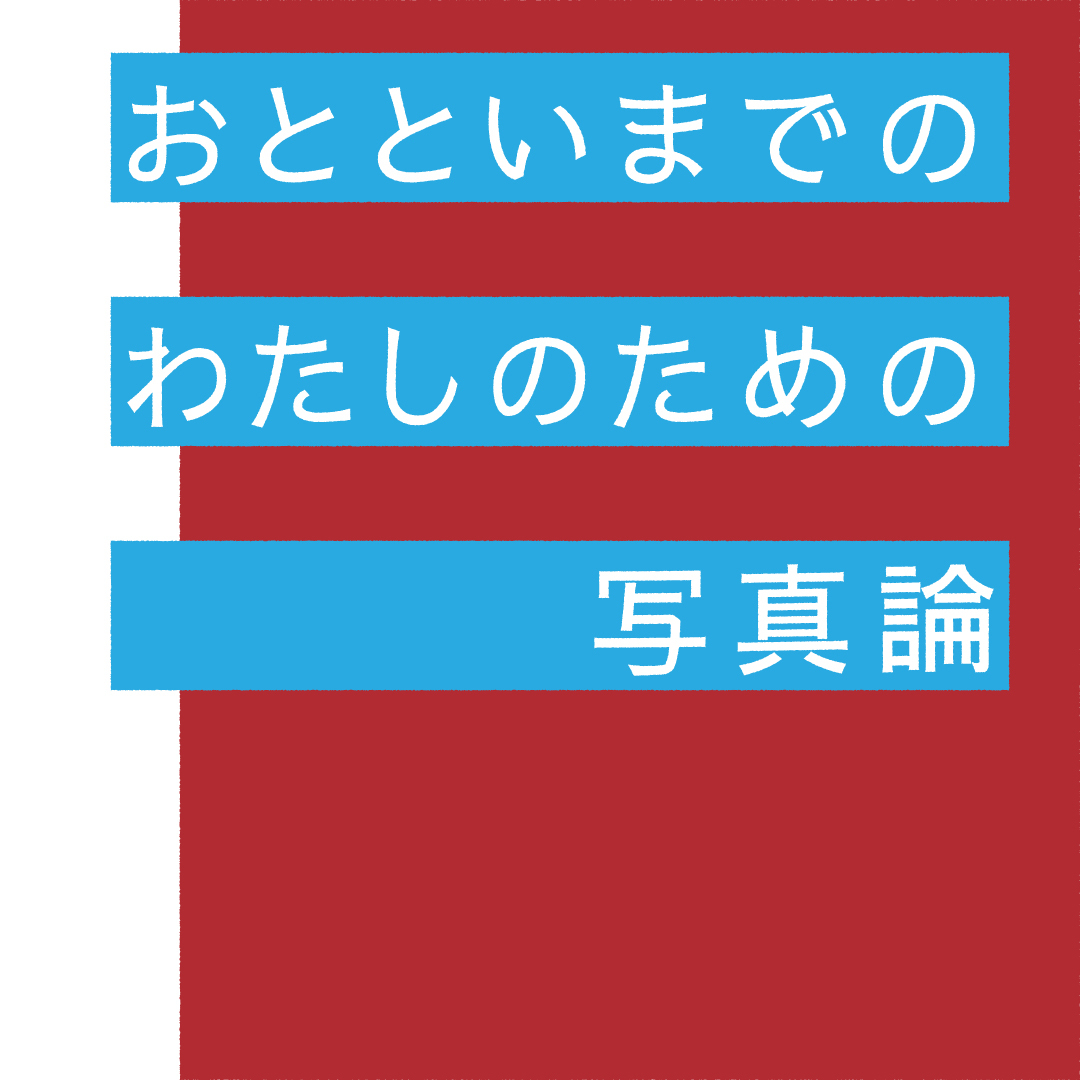
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日
ピックアップ

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日