カルチャー
「みてね」と写真のなかの手
文・村上由鶴
2025年7月7日
text: Yuzu Murakami
最近、はじめての甥っ子が爆誕しました。日ごとに顔つきが変わっていく新生児の成長を、家族アルバムアプリ「みてね」で共有される写真を通じて、毎日眺めています。株式会社MIXIが提供するこのサービスは、子どもの日々の記録を家族や親戚などと共有するためのアプリ。UIがジェンダーニュートラルなのもいいなと思います。
さて、日々アップされる赤ちゃんの写真をながめていて思い出したのが、ポーランドの写真家アネタ・グジェシュチコフスカによる《Mama》シリーズ(2018年)です。昨年、横浜トリエンナーレでも展示されていた《Mama》の世界は、「みてね」で共有される愛らしい日常の写真とはまったく違う性質のもの。ちょっと(っていうか結構)グロテスクにも感じられるし、いまにも危険なことが起こりそうな色調などが特徴的です。
なぜ「みてね」の、穏やかな成長記録の写真からグジェシュチコフスカの《Mama》シリーズの不穏な写真を思い出してしまったのか自分でも不思議なのですが、思い当たるのは「手の所作」にたくさんの情報が詰まっている、という共通点がある、というところです。
生まれたばかりの甥っ子の写真には、彼を抱く大人の手がいつも写り込んでいます。まだ首もすわらない小さな身体を壊れもののように優しく、でもしっかり支えないといけないというあの独特な手つき。そのひとつひとつの所作は、ぎこちなさと緊張感を伴いつつ、深い愛情を表現しています。
わたしがグジェシュチコフスカの《Mama》シリーズを思い出したのは、この作品が、まさにそうした「手の所作」を通じて、感情や出来事、物語を想起させるからです。
《Mama》では、その「手の所作」の主体となるのは、大人ではなく子供のほう。本作は、グジェシュチコフスカが、母としての自分をシリコン人形として複製してそれを娘に預け、娘が人形の自分を扱う様子を撮影したものです。
娘は、シリコン人形の母を抱きしめてタバコを吸わせてあげたり、お風呂に入れてあげたり、洗ってあげたり、お化粧をしてあげたりしていて、やっていることはおそらくおままごと的な遊びなのに、支配や無邪気な暴力の気配が漂います。
そのなかにお風呂のドアの隙間から撮影された、不気味な写真があります。娘フランチシュカの小さな手が、人形の肩に伸びている一枚です。この写真の主役はまさに娘の手と、そのあどけない所作。おそらく無意識であろう手の表情が、なぜか起こらないはずの暴力を想像させます。
また、手の所作ではありませんが、ある写真では、娘のフランチシュカが紫の水着とショートパンツを身にまとい、川辺に立っています。その隣に、手押し車に乗った母の(人形の)胴体が佇んでいます。この一枚を見るとなんだか「姥捨て山」(この場合は川だから「姥捨て川」?)を思い出してしまいました。とはいえ、別の写真では、ふたりが水に浮かびながら並ぶ姿もあって、娘さんご本人としては「川で水浴び」に連れて行ってあげる気持ちだった可能性もあるのか…?と、本人の意図に関係なく残酷な物語をついつい想像させるイメージに混乱させられます。
もちろん、写真家である母グジェシュチコフスカが画面の外側から演出を加えていることは明らかです。しかし、この写真を見ると、どうしても娘に主体性があるように感じてしまいます。写真のなかでは、一般的な「母子」の関係性がここでは完全に逆転しており、母に「手を下す」のは娘。一方で母のかたちをした人形は、ただなされるがまま。写真のなかの2人(というか1人と1つ)のパワーバランスは明らかに非対称です。
この「力」のアンバランスさに目を奪われていると、子供の無邪気さが、あるいは親の愛が暴走する物語を思い出してしまって、撮影する「本当の母」の存在をついつい忘れてしまうようです。
さて、このように、写真のなかの手は、いまや写真のなかの顔と同じくらい物語性を帯びるものと言えます。むしろ、いまや「顔」よりも正直といえるほど。
例えばAIによる画像生成でも、手の表現は苦手とされているようで、指が6本になっていたり、妙な方向に曲がっていたり、そんなふうな形にはならないだろう、という「写真の中の手」を目にします(最近は少し改善されてきた?)。これは手のほうが、顔よりも正しさや美しさを確定させにくいからでしょう。つまり手は多様であり多義的なのです。
と考えると、「みてね」のアプリ内に蓄積されていく日々の写真のなかには、写っている本人の顔以上に、そこに添えられた誰かの「手」が意味を持ち始めることがある気がします。もしかしたら、こうした写真のなかの「手」たちが、大きくなった子どもになにかを気づかせるのかもしれませんね。
本作は、メルボルンのBuxton Contemporaryで開催中の展覧会「the veil」で見られるそう。メルボルンのお近くの方はぜひです!ではまた!
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻助教。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
想像力を節約する技術
文・村上由鶴
2025年5月31日

カルチャー
写真の(なんかゴタゴタした)夜明け
文・村上由鶴
2025年3月31日

カルチャー
映画「アプレンティス ドナルド・トランプの創り方」と写真戦略
文・村上由鶴
2025年2月28日

カルチャー
インスタグラムのアイデンティティクライシス
文・村上由鶴
2025年1月31日

カルチャー
2024年の写真のロマンティックを振り返る
文・村上由鶴
2024年12月31日

カルチャー
「リンダリンダ」と撮影できない展覧会
文・村上由鶴
2024年11月30日

カルチャー
写真は鏡であったり窓であったりする、けどその前に扉でもある
文・村上由鶴
2024年10月31日

カルチャー
実態のない「秋田美人」
文・村上由鶴
2024年9月30日

カルチャー
正しさよりも優れていること
文・村上由鶴
2024年8月31日

カルチャー
写真とエモーショナルな政治
文・村上由鶴
2024年7月31日

カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
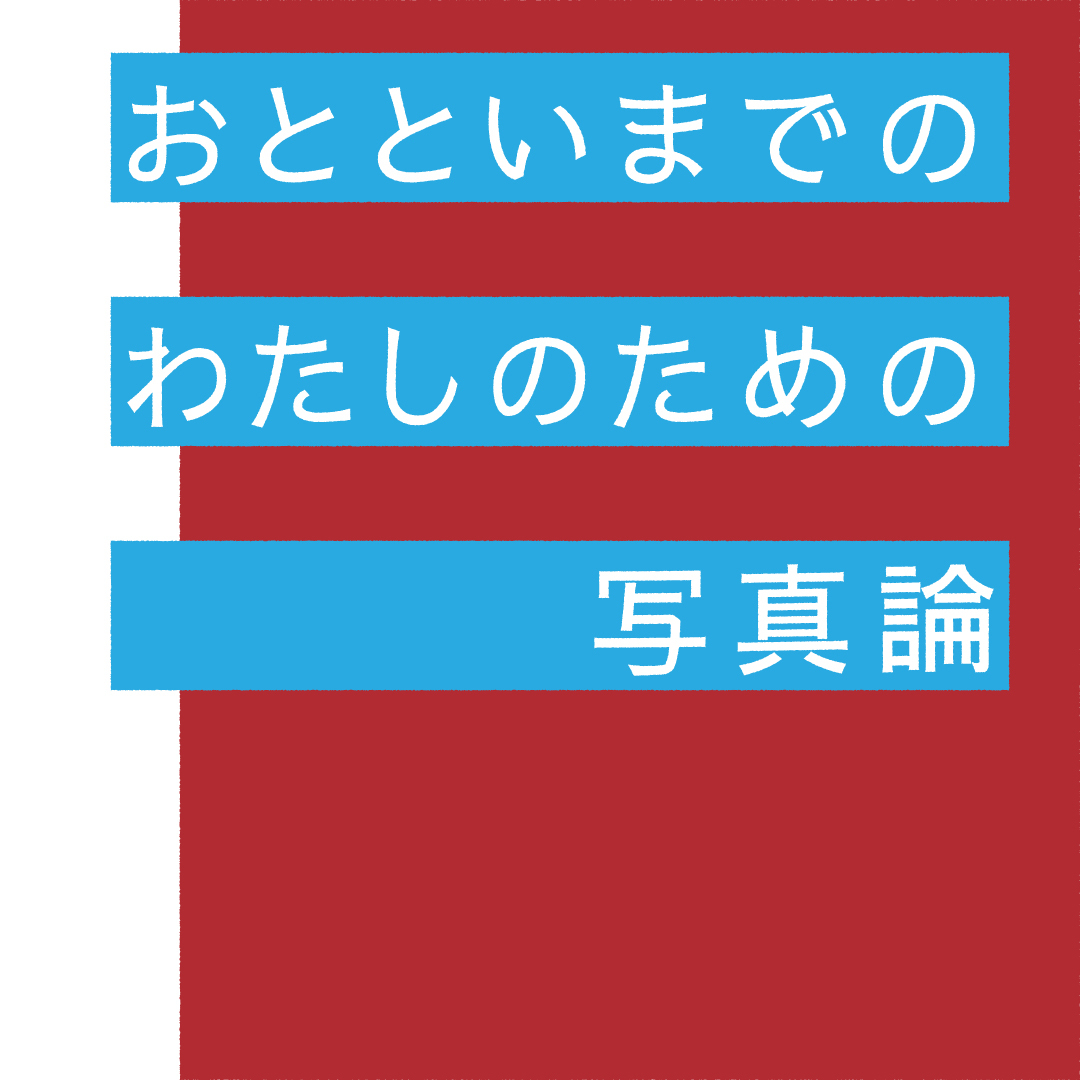
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
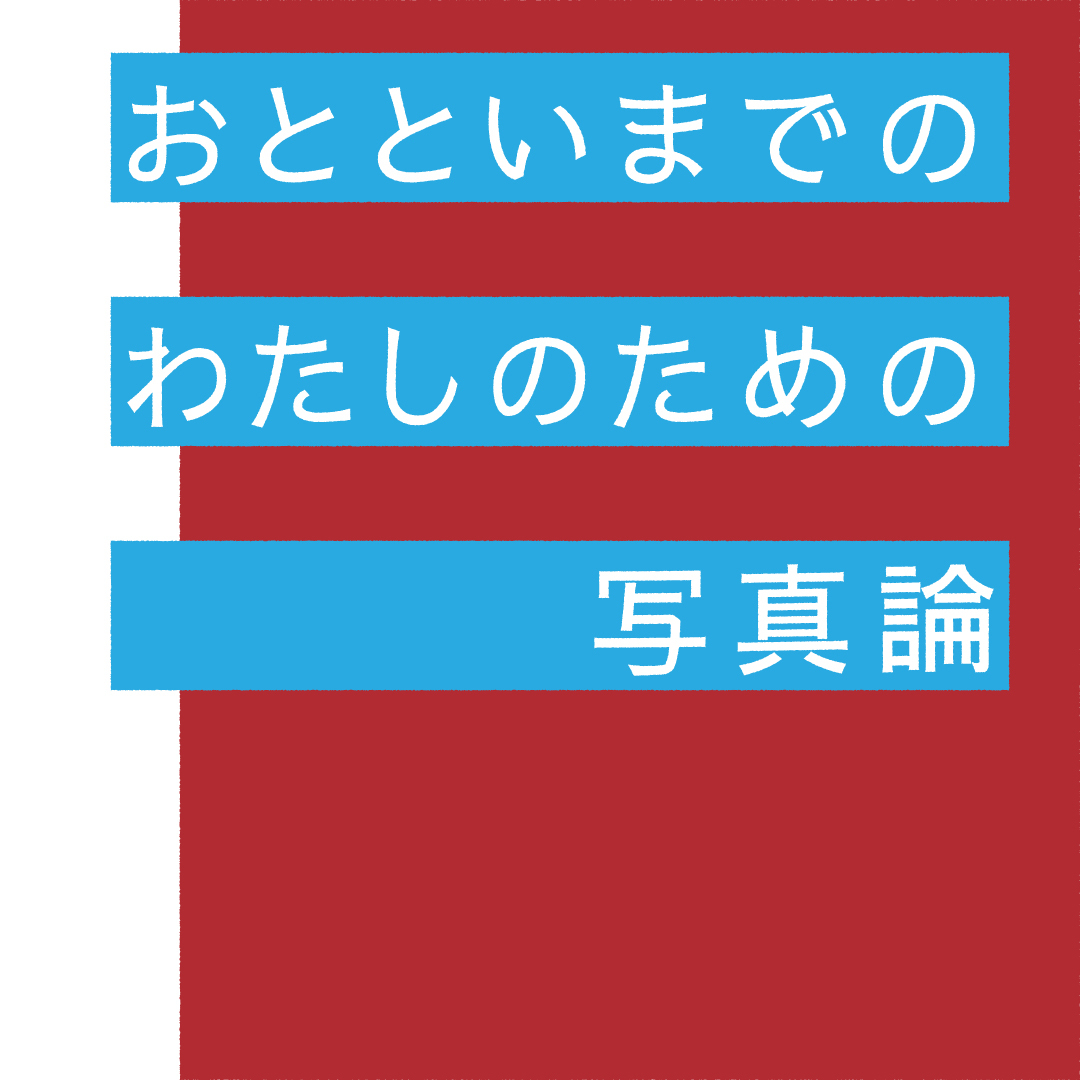
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
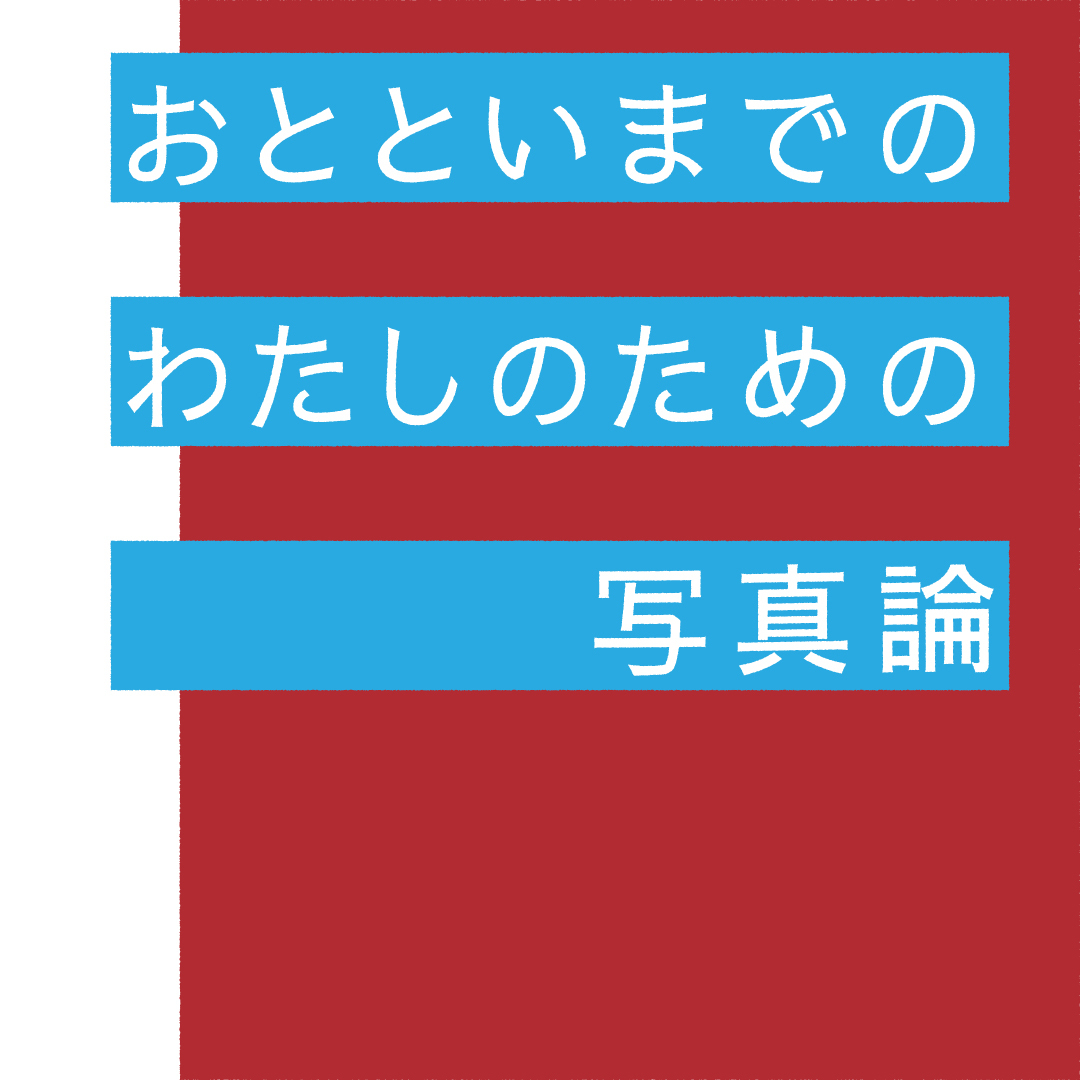
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日




