カルチャー
2024年の写真のロマンティックを振り返る
文・村上由鶴
2024年12月31日
text: Yuzu Murakami
2024年は、改めて、ロマンティックな写真の力に惑わされている…?と感じていた1年でした。
例えばこの連載でも、間も無く大統領に就任するドナルド・トランプが襲撃されたあの写真がもたらすエモーションや、中平卓馬の言葉の情緒などについて書きました(中平については、POPEYE WEBのPodcast「まなびじゅつ」でも「魔法」というキーワードでお話ししているのでぜひ聞いてください)。
また、パリオリンピックの写真についても、真実そっちのけで美しさを優先する傾向があると書きました。
こんなふうに、写真がそこに写るものや人を実際よりも特別なものに見せる力を働かせていて、そういう写真や映像に人は(いまも)感動させられる、という(基本的な)ことが、わたしはなぜだか気になっていたようです。
ところでこれは、実際の写真作品だけでなく、写真というもののとらえられ方にもあらわれていたようにも思います。
例えば、2024年1月に発表された韓国の歌手IUの楽曲「Love wins all」の超壮大なMV(BTSのVが出演していることで話題になり、12/30日現在の再生回数はなんと8500万回!)。
超大作ディストピアSF映画のようなトーンで撮影されているMVのなかで、重要な小物として出てくるのがカメラです。このMVのなかでは、カメラはいわば世界を「幸せだったあの頃」のように見せてくれる「魔法のアイテム」。写真を撮るシーンやファインダーをのぞくと、荒廃した残酷な現実からはなれられる、というものでした。
横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きている」で見たノーム・クレイセンのカウボーイのシリーズにも、写真の魔法のような力を感じさせられ、2024年に見た写真のなかではとりわけ印象にのこっています。
ナポレオンのようなロマンティックさをたたえたクレイセンの写真は1980年代後半にマルボロの広告に使用され、多くの人の目に触れました。
クレイセンはアメリカ西部のカウボーイたちとの共同生活を経て、馬にまたがりロープを振り回すその姿を美しい自然光を生かしてとらえました。その写真は、雑誌や新聞やビルボード広告を通じて、冷戦中のアメリカにおいて、マルボロを好む、理想的なアメリカの男性像をかたちづくったのです。
なお、この写真は現代美術においてはむしろ、リチャード・プリンスの作品として知られています。
「え?クレイセンが撮った写真じゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこのイメージは「シミュレーショニズム」や「アプロプリエーション」と呼ばれる美術の動向を牽引した現代美術家であるリチャード・プリンスが、クレイセン撮影のマルボロの広告をトリミングした写真を自作として発表し、注目を浴びました。
プリンスのこの手法には、威厳がありすぎるカウボーイのイメージから距離をとり、そこで象徴される理想を茶化す効果がありました。いわばクレイセンの写真は現代美術の世界からは常に茶化されてきたのです。
さて、あえて2024年に写真家ノーム・クレイセンの作品として改めてカウボーイの写真を見せる前提には、もはやプリンスが茶化すまでもなく「カウボーイ」というアメリカン・(男・)ドリームを、鑑賞者側がそのままに受け取ることが難しくなっているからか、あるいは、カウボーイ的な男らしさに対する「ノレない」感が共有された、という認識があるのかもしれません。
とはいえ、個人的には2024年の政治やら社会やらを見ていて、リーダーや救世主を求める願望や、理想化された「あの頃」を賛美する雰囲気ができあがりつつある気もしています。文脈を知らないとその写真の受け取り方に心的に大きな差が生まれる事例と言えますし、むしろこういう現実離れしたドラマティックな写真って、「普通に」歓迎すべきものとして受け入れられてしまいそうです。
一方、2024年に日本で公開されたクリストファー・ノーラン監督「オッペンハイマー」の映画では、ここまであげてきたような「理想化の魔法」的アイテムとは対局的なかたちで写真が用いられていました。
劇中、原爆投下後の被爆地の様子をスライドショーで伝えられるなか、オッペンハイマーが思わず目を逸らしてしまうシーンは、日本であの映画を見た観客にとっては非常に印象深いシーンのひとつとなっているのではないかと思います。
映画ではその写真自体は映されませんでしたが、おそらく、撮影者の意図や演出を排除した、被曝者の怪我や遺体などを含む生々しい被害の様子を伝える写真であったことが想像されます。
このように、写真はなんのフィルターも通していない現実を、ごろっと指し出すものでもあったのです。
しかし、この映画ではその写真がどんなイメージなのかが、観客に示されませんでした。これは、現代の観客が写真を直感的にリアルなものと信じられなくなっていることにも関係があるかもしれないし、あるいは、この記事のはじめに述べてきたように、「写真というもの」をロマンティックなものとして受け止めたいという(無)意識が広がりつつあることに対応しているのかもしれません。
年末の今日も、痛ましい事件、事故、戦争のイメージが、オッペンハイマーの生きた頃よりも早くそしてたくさん、わたしたちのもとに届いています。2025年、本当に見るべきものがあるとしたら、それからわたしたちは目を逸らさないでいられるのか、ロマンティックな写真に惑わされてしまうのか…!?というわけで来年もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた!
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。日本大学芸術学部写真学科助手を経て、東京工業大学大学院博士後期課程在籍。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」、幻冬舎Plus「現代アートは本当にわからないのか?」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
写真は鏡であったり窓であったりする、けどその前に扉でもある
文・村上由鶴
2024年10月31日

カルチャー
実態のない「秋田美人」
文・村上由鶴
2024年9月30日

カルチャー
正しさよりも優れていること
文・村上由鶴
2024年8月31日

カルチャー
写真とエモーショナルな政治
文・村上由鶴
2024年7月31日

カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
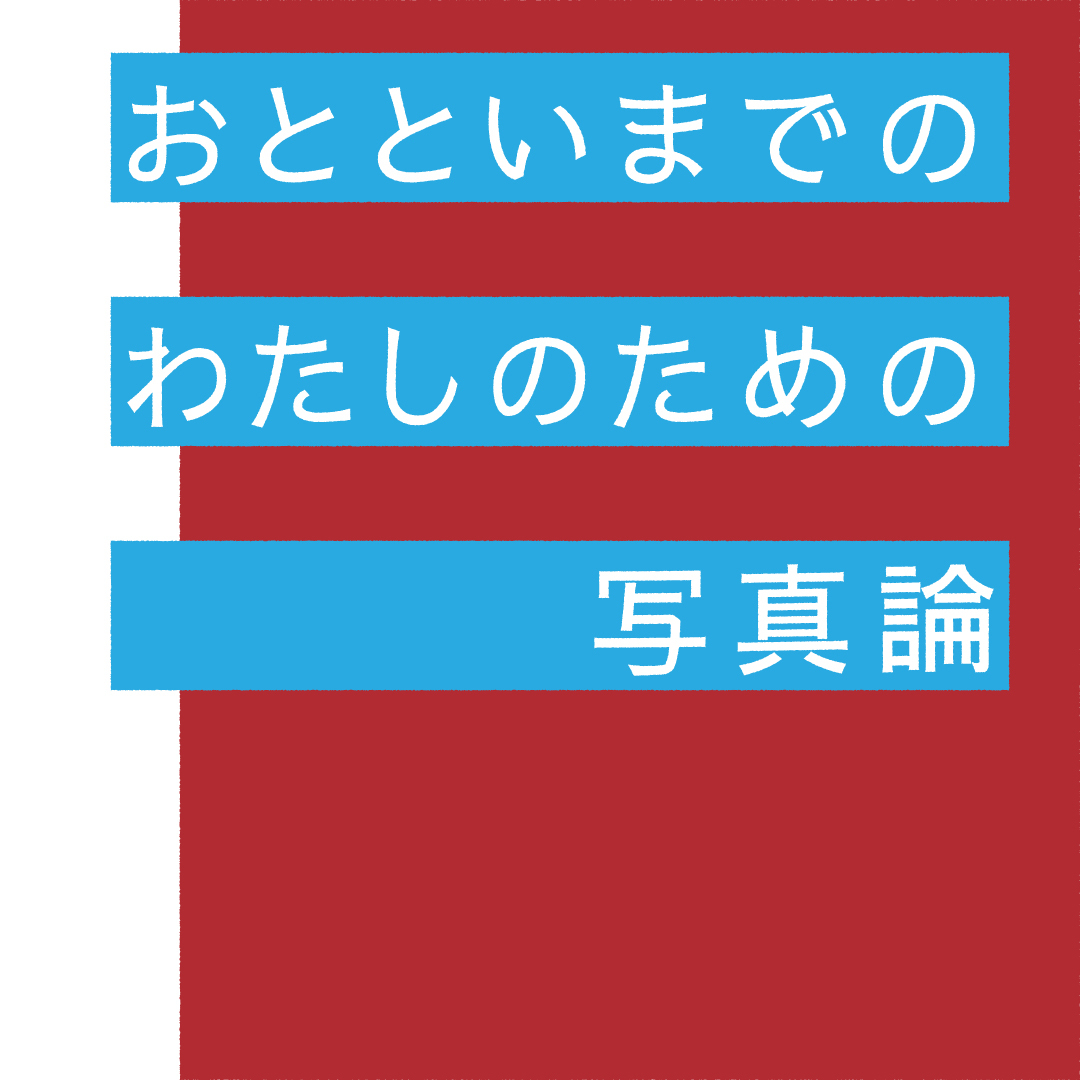
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
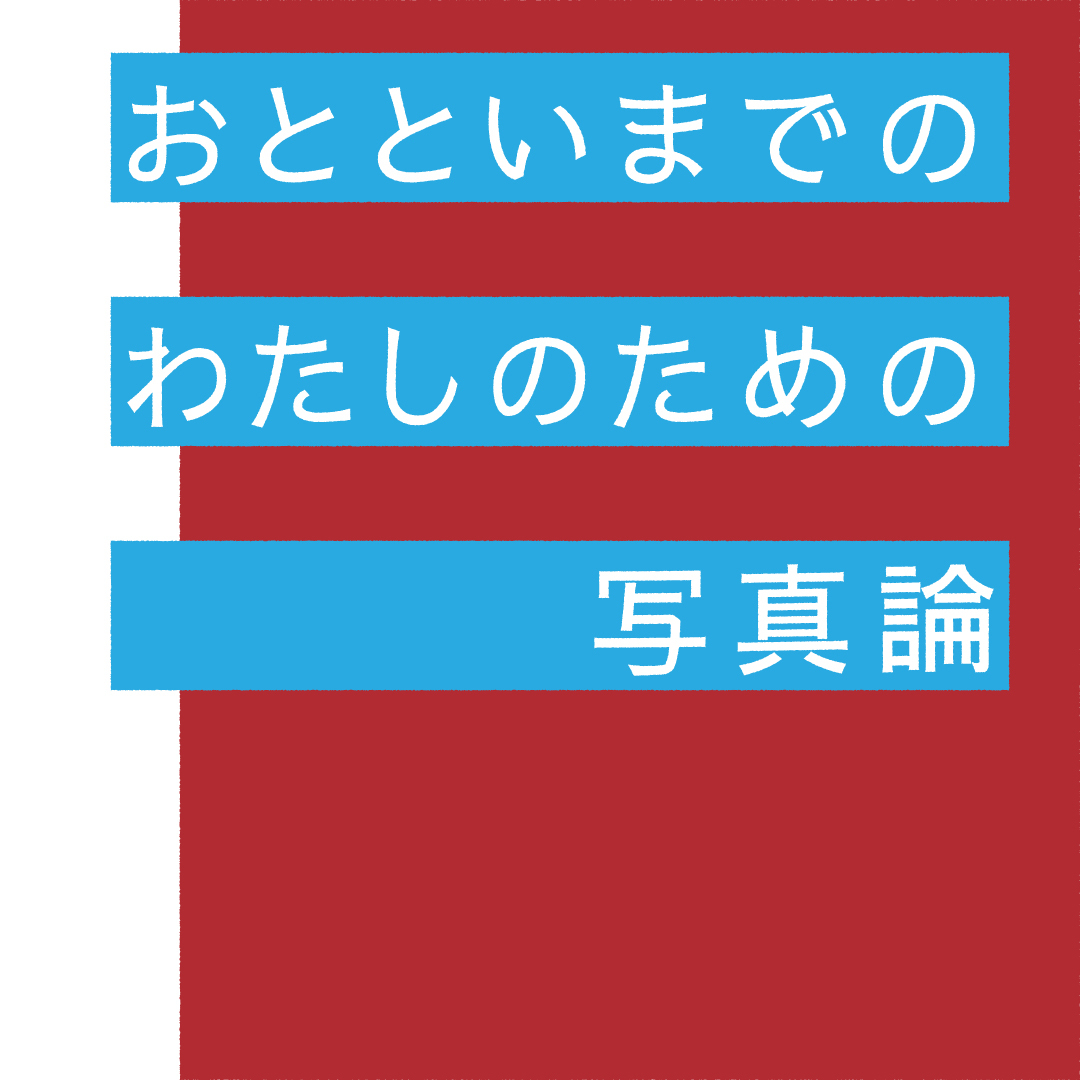
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
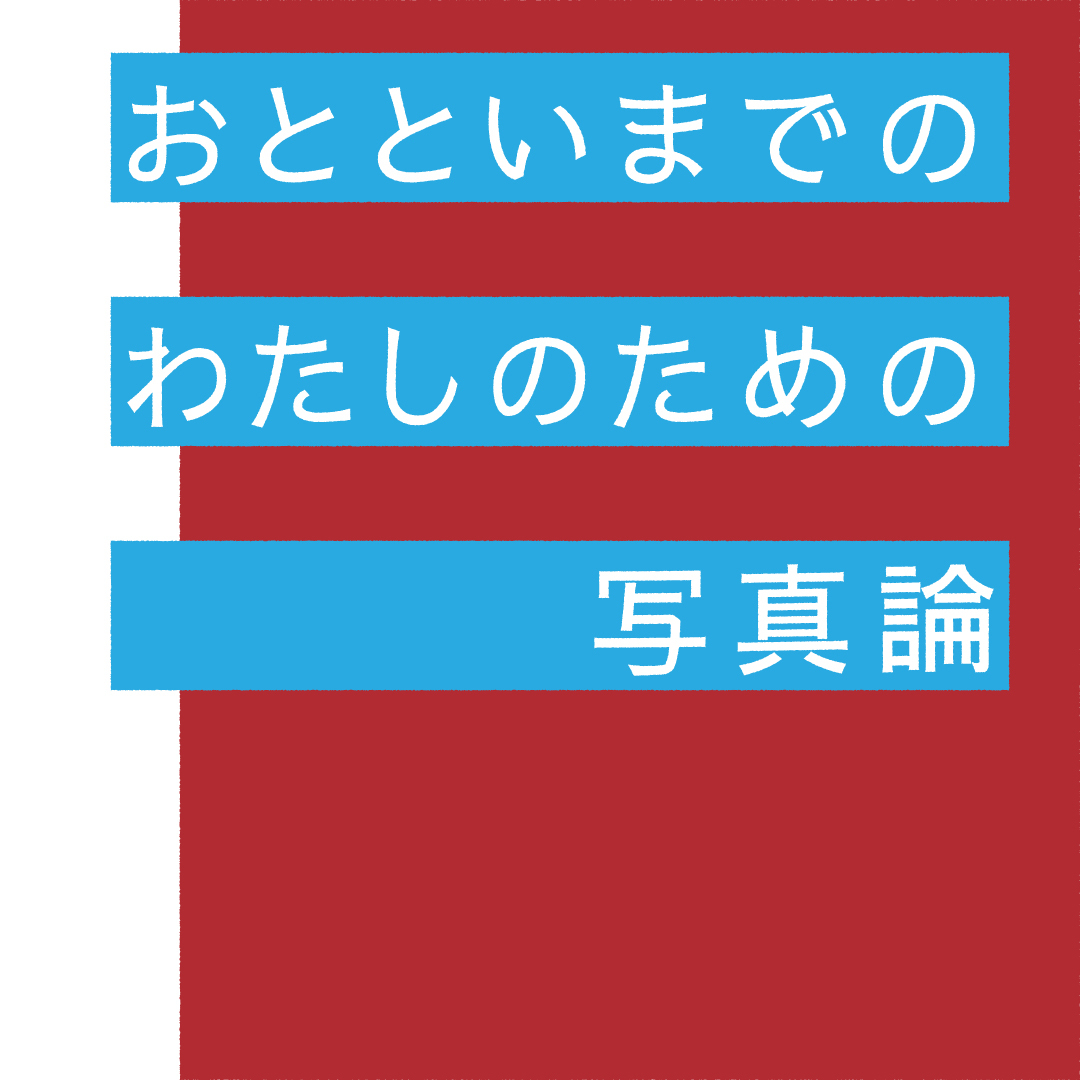
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日
ピックアップ

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日