カルチャー
写真とエモーショナルな政治
文・村上由鶴
2024年7月31日
text: Yuzu Murakami
最近は、バイデン大統領のインターネットミームを見るのがちょっとしたブームです。そんなわけで今月はインターネットミームの写真について書こうかな…なんてことを思っていたら、前アメリカ大統領ドナルド・トランプが選挙集会で銃撃されたというニュースがあの写真とともに飛び込んできました。
あの写真とは、もちろんエヴァン・ヴッチ氏撮影の、耳から血を流すトランプがSPに囲まれ、星条旗を背景に拳をつきあげている、あの写真です。
この写真についてはすでにさまざまに語られています。
例えば、ドラクロワ《民衆を導く自由の女神》との比較。この絵画は「自由」と「愛国」(とそれに付随する「暴力」)といった抽象的な概念を、そのままイメージ化した1830年の作品です。確かに例のトランプの写真にも構図をはじめとして似通ったところがいくつもあります。
《民衆を導く自由の女神》には細かいモチーフにさまざまな意味が張り巡らされていますが、他方、そのトランプの写真は当然絵画とは異なり、意図されたモチーフはないはずですが、そうであるにもかかわらず「民主主義」と「リーダーシップ」と「アメリカ」という概念を可視化したらこうなるのではないかと思えるほどよくできた、できすぎている写真です(そしてあの写真があまりに「できすぎている」ことによって、さまざまな陰謀論がはびこったようにも思われます)。
さて、「できすぎている」と言えば、写真は発明以来、長らく「撮る」ものでしたが、AIの登場によって、ここ数年の間に写真を撮影なしで「作る」ことができるようになりました。
この連載ではアナログからデジタルへの写真の変革が写真表現に大きな影響を与えたことにも繰り返し触れてきましたが、アナログであれデジタルであれ、写真は少なくとも「撮る」という行為で一貫した歴史を持っていたと言えます。ですから、もはや「撮る」ことも不要とするAIの登場は、写真の歴史を未来から見たときには決定的な出来事と言えるでしょう。
そんななか、わたしはエヴァン・ヴッチ氏が撮影したトランプの写真とそれへの反応を見て、AIによる写真が身近なものになりつつあっても、人が撮った写真のパワーと、その写真を人が見ることによって情動が引き起こされる(されてしまう)ことを改めて認識させられました。
大統領選挙をはじめ、昨今の選挙でも、そして戦争でも、インターネット上でのイメージの流布は重要な戦略のひとつとなっています。そのなかには真偽不明であったり、選挙の場合は対抗する候補者を貶めたりするものも少なくありません。スピーチの名場面だけを凝縮したり、メタファーやテロップなども駆使した端的でわかりやすいショート動画や、あるいはキュートにデザインされたインスタ用の画像などは、ごく短い時間で政治的な意思決定に大なり小なり影響を与える効力を持っています。
しかし一方で、最近のわたしたちはそうした切り抜きによる情報操作にすでに慣れ始めてもいる状況です。そのなかでもトランプのあの写真は「切り抜かれた」一瞬であることには変わりはありませんが、情報操作や真偽といった理性的な理解を超えて、情動を刺激してくる、なにか抗い難い求心力を持つイメージとなっていると思います。
トランプ氏が大統領に当選した2016年のアメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱選挙の頃から、政治にまつわる宣伝では理性的な判断を超えて人を感情的にすることが重視される傾向が高まり、近年の日本の選挙にも同様の傾向が見られます。こういう時代において、あの写真は政治にまつわる人々の冷静な判断を凌駕するものとして、最も優れたコミュニケーションです。
おそらく、あの写真がなにか特別なものとして受け入れられているのは、写真に撮られた一瞬が本当に存在し、その一瞬を実在の人間が捕まえたという事実に対する畏怖のような感情も伴っているでしょう。いわばこれは、表層的なイメージのインパクトではなく「この写真が撮られたという事実」によって掻き立てられる強いエモーションです。
例えば、同様のイメージであってもAIが生成したものであったとしたら、ここまで情動を刺激するものにはならないのではないはず。そして、さきほど「『民主主義』と『リーダーシップ』と『アメリカ』の可視化」と述べましたが、実際にAIにこのようなプロンプトで写真を作ったとしても到底作り出せないイメージであることは明らかです。
もちろん、負傷してもなお「英雄的な」トランプのふるまいが可能にした1枚であることは言わずもがな。トランプ自身がその後の指名受諾演説で「全能の神の恩恵で自分は今ここにいる」と発言し、それにひときわ大きな歓声があがったとき、人々の脳裏にはあの写真がよぎったはず。「全能の神の恩恵」という言葉が人々の素朴な感動を掻き立てるように、あの写真にもそういう力が、良くも悪くも宿っていることは確かです。
というわけで、写真が極めて情緒的なものであることを思い出し、そして、それが世界の動向を大きく左右するであろうことに深い恐怖を抱いた7月でした。写真がそうやって理性を軽々と飛び越えて届いていくものであることって、ちょっと忘れていたかもな。ではまた!
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。日本大学芸術学部写真学科助手を経て、東京工業大学大学院博士後期課程在籍。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」、幻冬舎Plus「現代アートは本当にわからないのか?」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
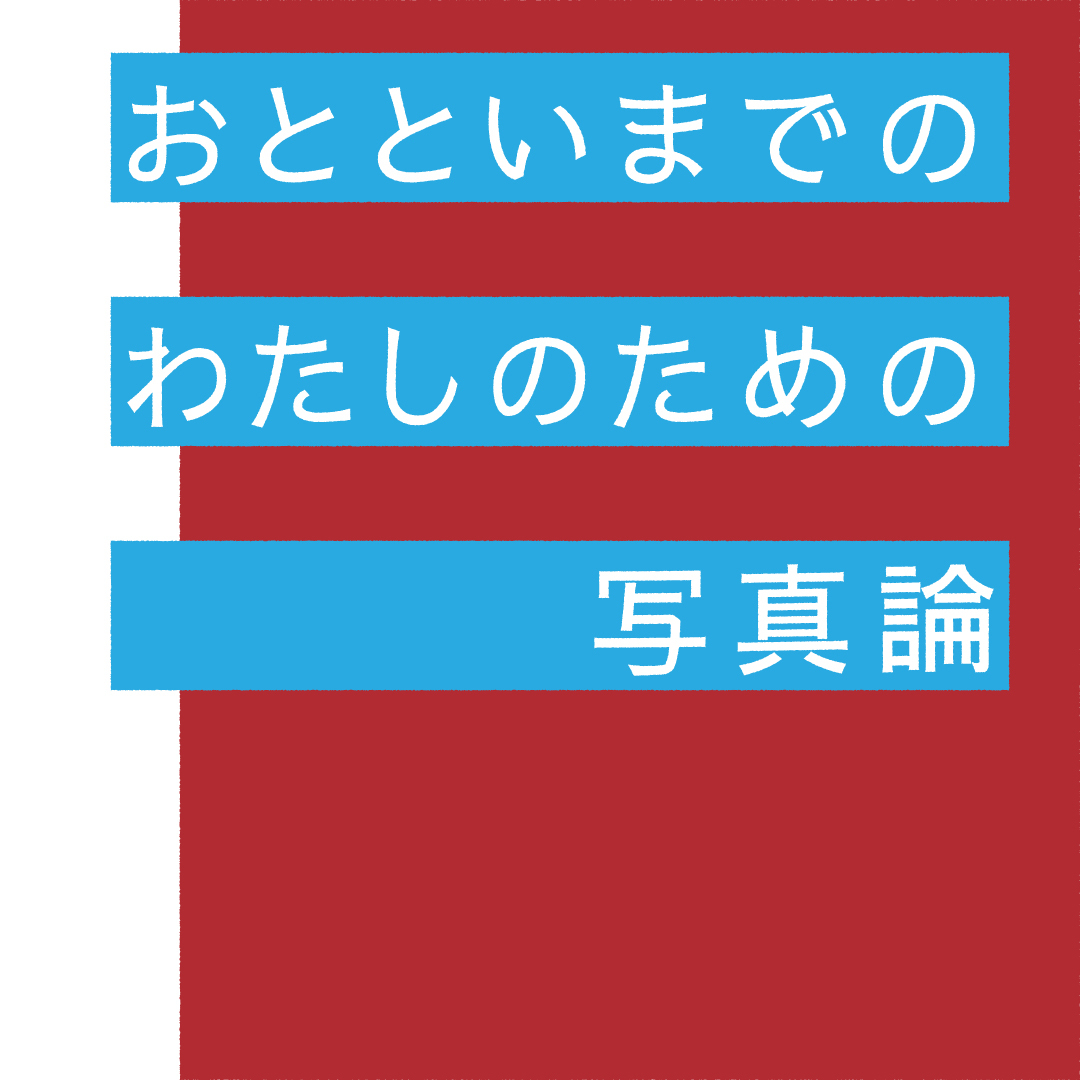
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
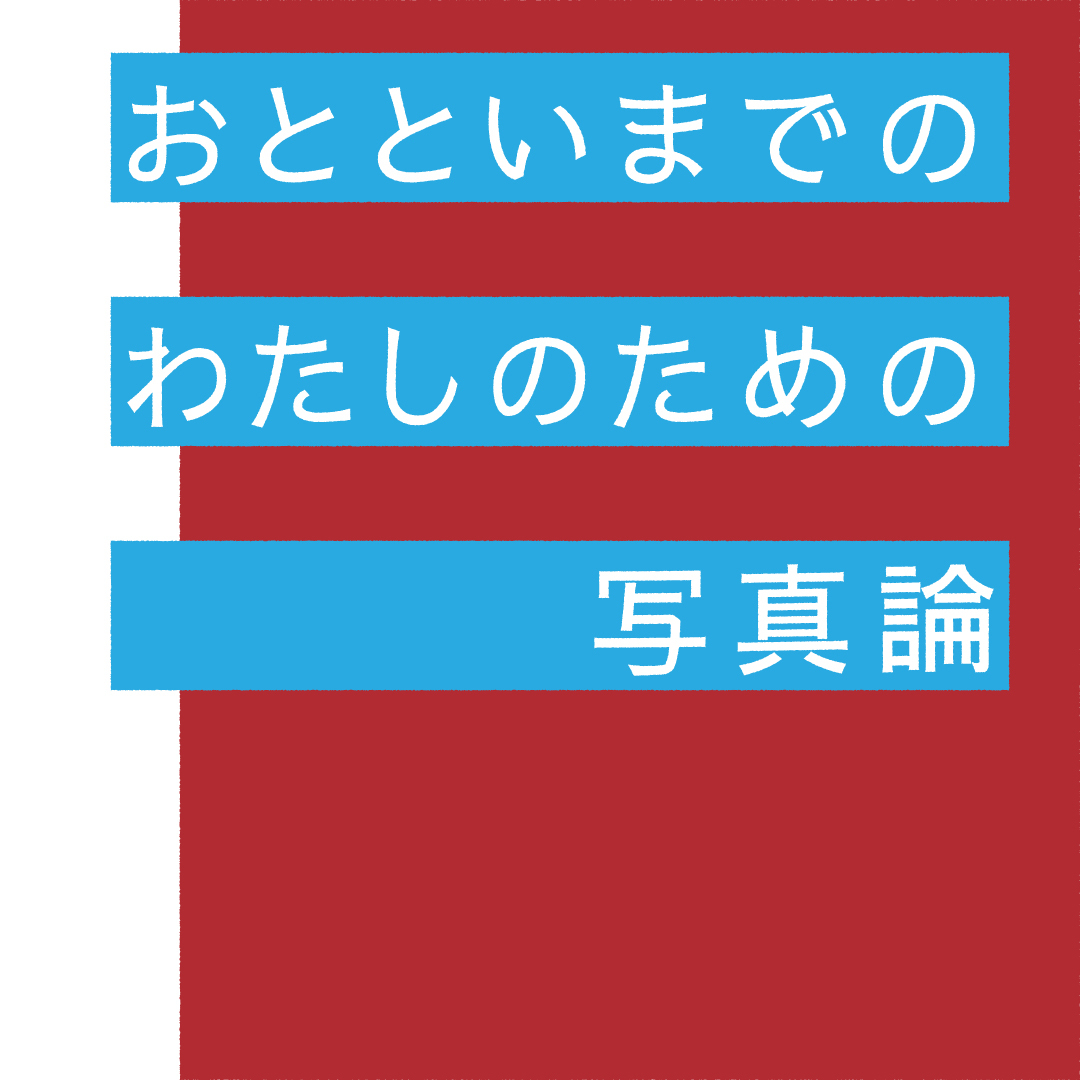
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
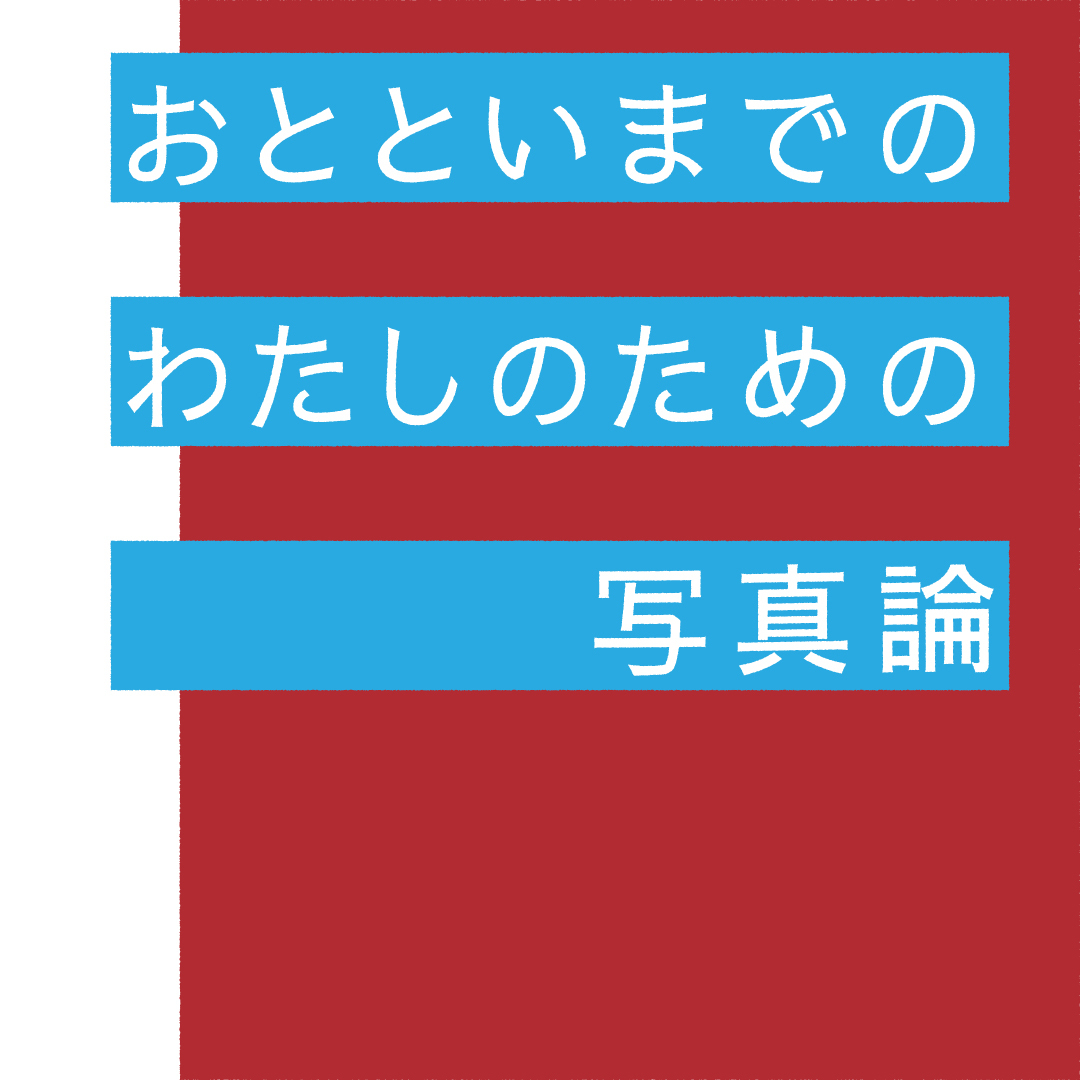
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日




