カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
text: Yuzu Murakami
ジョナサン・グレイザー監督の映画『関心領域』を見ました。
ジョナサン・グレイザー監督といえば20世紀を代表する超絶有名MVであるジャミロ・クワイの「Virtual Insanity」の監督でもありますが、本作は今年の米アカデミー賞で国際長編映画賞と音響賞を受賞した話題作で、日本では5月24日から上映がはじまっています。
『関心領域』は、「アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族」の映画。
わたしは先日映画館で見てから衝撃を受けて、早川書房から出ている原作翻訳本も手に取ったのですが、原作本の文学の表現と、映画化の際の脚色・編集・音響の表現よって、その体感に大きな違いがある作品になっています(映画化に際して主人公が実在の人物に変更になっていたりもします)。
写真についての文章を書くことを専門にしているわたしも、この映画に限らず、映画を見る時にはついつい写真だったらどうだろうとか、これは映画ならではの表現だ〜、などと思いながら映画を見てしまいます。そして『関心領域』もまさに映画であるからこそ可能なアイデアにあふれた作品でもありました。そういえば「Virtual Insanity」も、MVであることに自覚的だからこそのアイデアがあるMVでしたし(ちょっと怖かった)から、グレイザー監督は、自分が使うメディアに自覚的な人と言えそうです。
ところで、本作のような強制収容所に関する映画があるように、強制収容所を写した写真もあります。もちろん、その写真は著名なカメラマンが取材として撮影したのでは当然なく、そこでの強制労働に従事させられていたユダヤ人の「ゾンダーコマンド(特別労務班)」によって撮影されました。
ゾンダーコマンドとは、不当に収容された強制収容所で、囚人の遺体の処理を担当させられていた一部の囚人たちを指します。彼らにはその「労働」への拒否権はなく、彼ら自身もまた同様に虐殺されることによって口封じされる運命にありました。いわば、その写真に撮られた遺体と撮影者のゾンダーコマンドは運命を共にしていたと言えます。
そのなかで彼らは決死の思いで、自分が亡くなっても強制収容所のなかで起こったことをなんとしてでも未来に残そうと、その様子をナチス・ドイツの将校らに見つからないように撮影したのです。
なお、撮影された写真には、大量の遺体を焼却する様子がはっきりと写っており、この写真は、映画「ショア」の監督であるクロード・ランズマンや美術史家のジョルジュ・ディディ=ユベルマン、そして現代美術家のゲルハルト・リヒターを触発し、どのようにこのイメージが指し示す歴史を認識するべきかという葛藤と共に、議論を巻き起こしました。
(ちなみにこれらの写真についてはクリストフ・コニェ著(右京頼三訳)『白い骨片』で詳細な検証がなされています)
思えば、この写真は、写真が証拠能力を持つものとして信頼されていたからこそ撮られたもの。写真が歴史上最も切実な道具として存在していた時の写真です。そして、時にその存在すら否定されてきたホロコーストおよび強制収容所に関する歴史に、何度でも直面させるものでもあります。
ところで、この4枚の写真が「歴史認識」を問うのに対して、『関心領域』は、どちらかといえば「現状認識」のための映画と言えそうです。
この映画には人によっては「幸せに暮らす家族」の物語にしか見えないシーンも多数ありますが、いやでも耳に入ってくる音によってその光景が「アウシュビッツ収容所の隣で」あることを意識せずにはいられないようになっていると思います。
特に庭のシーンでは、同一のシーンの中で強制収容所で、その瞬間に起こっている暴虐を時間の流れと共に「感じさせる」演出がなされています。「感じさせる」というのは、先ほどのゾンダーコマンドによる写真が「見せる」のとは異なり、直接にそれを写すことは一切ないからです。ここにはあの暴虐の画面を虚構として作り出し、それを撮ることに対して、監督が抱いている抵抗感が読み取れます。
これまで、ナチス・ドイツによる人間の恥部と言えるような歴史を描いた映画やドラマでは、強制収容所の光景やユダヤ人の迫害の様子が描かれてきたし、それらは、人間はジェノサイドというものを起こしうるのだということを歴史から学べと訴えかけてきたように思います。
わたしもそういうものから学んだ人間のひとりですが、人間性の危機について反省するのではなく、むしろ、その人類の恥部を盾にするようにして今まさにジェノサイドが起こっているのには、この映画で示されるように「関心」や「意識」を都合よくコントロールできてしまう、悪い意味での人間性を感じずにはいられません。
本作の主眼は、まさにこの、人間はどこまでも無関心になり、無関心から利益を得ることができるのだという点に置かれているように思います。
そしていまわたしは、そういう人間性からどう足掻いても逃れられないからこそ、今どうするのか?が試されているのだと、この映画を見てより一層考えさせられています。
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。日本大学芸術学部写真学科助手を経て、東京工業大学大学院博士後期課程在籍。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」、幻冬舎Plus「現代アートは本当にわからないのか?」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事
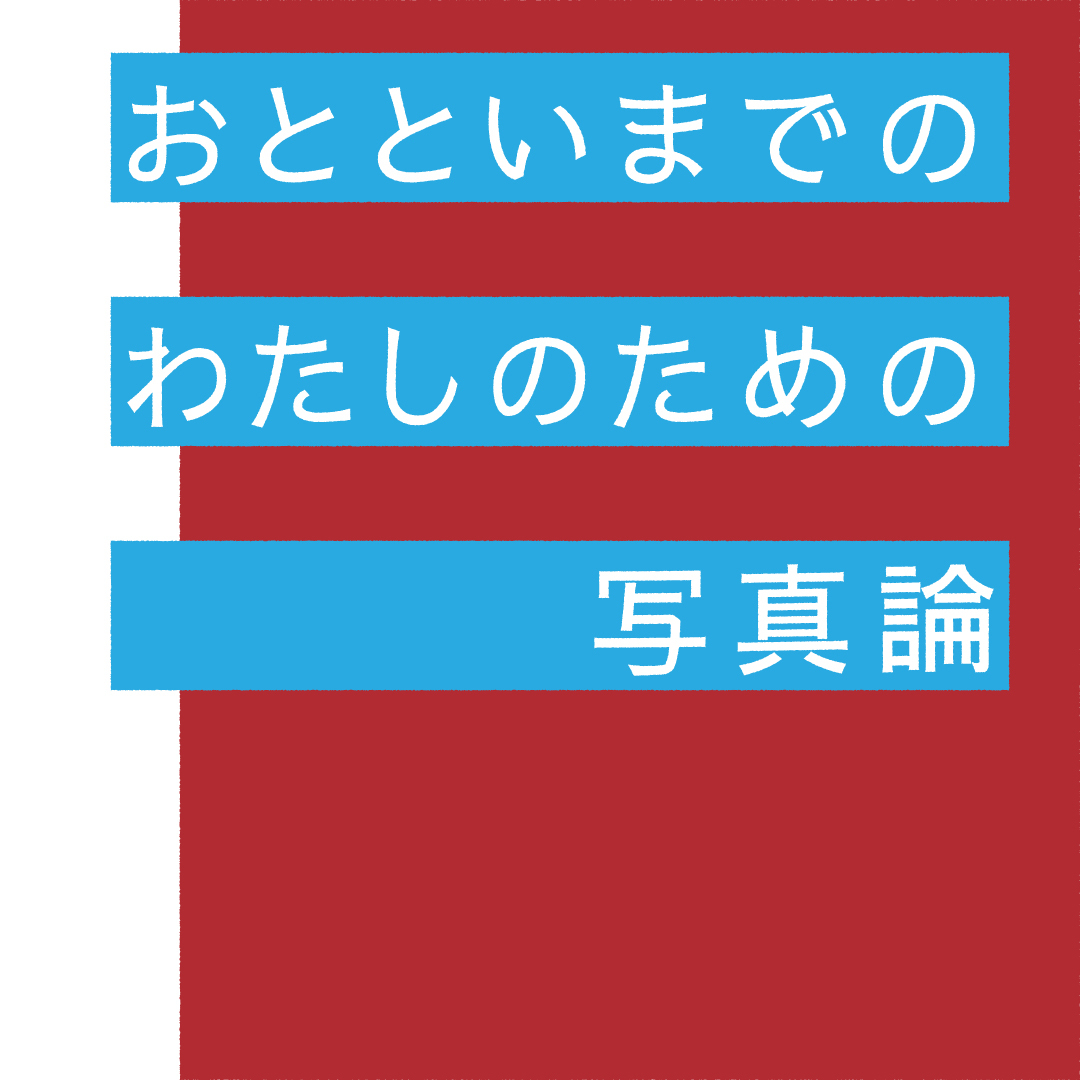
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
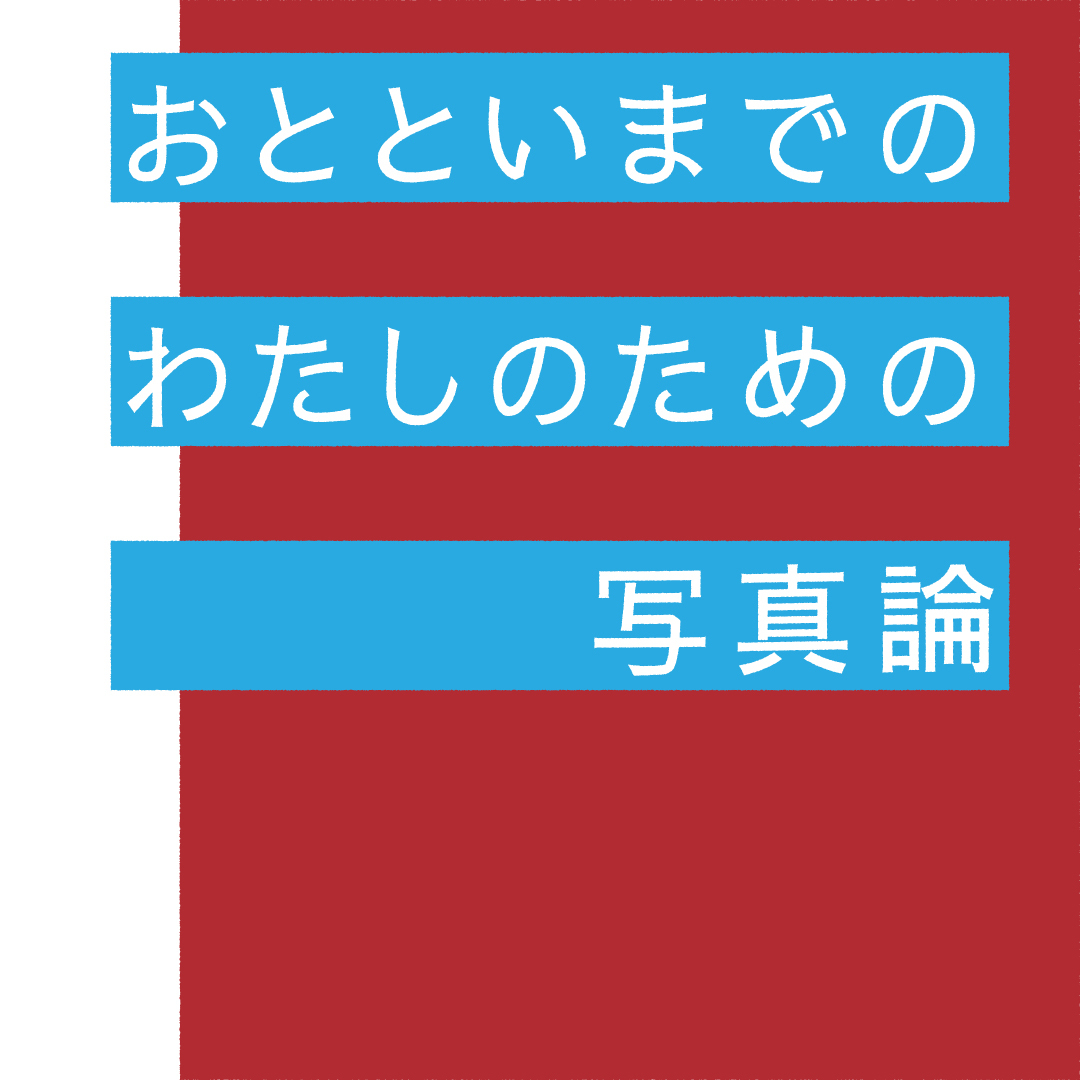
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
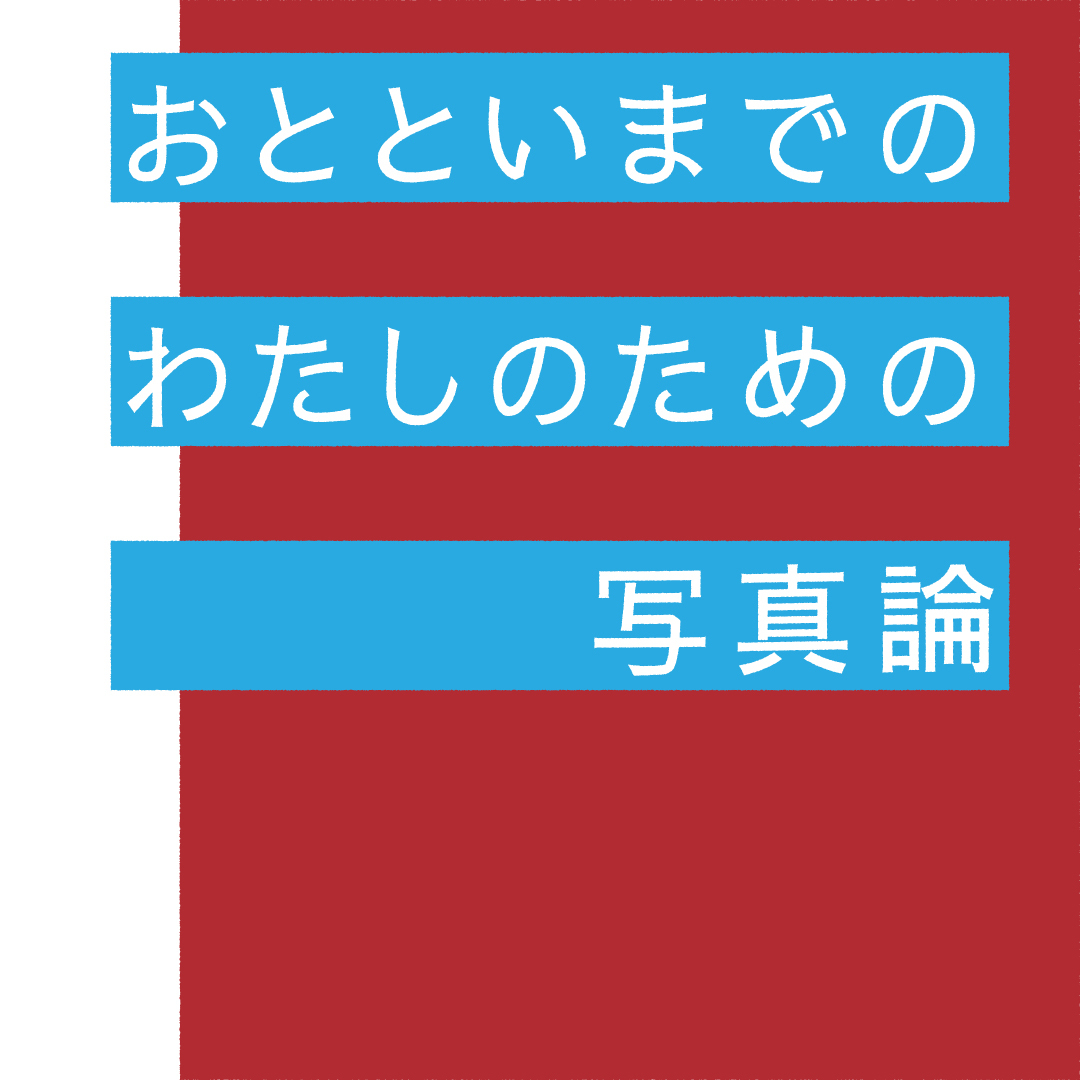
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日



