カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日
text: Yuzu Murakami
「誕生後150年経った1989年を境に、写真は死んだーーいや、もっと正確に言えば、150年前の絵画と同じように、写真は根底からその地位を永久に奪われてしまったのである」。
これは、ウィリアム・J・ミッチェルという人の『リコンフィギュアード・アイ』という本の一説です。書かれたのは1990年代のはじめごろ。デジタル写真が一般的に普及し始めたタイミングです。ここでの「写真は死んだ」というのは、デジタル写真の出現が、化学反応によってイメージを固定し保存するアナログ写真が持っている真実と結びついた「写真らしさ」を凌駕する存在感を示し始めた、つまり取って代わりはじめた、ということを指しています。
これは著者のミッチェルが、写真を「あくまで、自然にもとづいた化学反応によって、像を保存するもの」と定義していたので、「元に戻す」や「やり直し」ができ、しかも合成や加工もとても簡単で、自然な化学反応にもとづいてもいないデジタル写真を、それまでのアナログ写真に対して敵対する「脅威」のように設定したから。写真の技術がアナログからデジタルに進化/発展したと考えるのではなく、アナログとデジタルの写真をそれぞれ根底から全く別のものととらえたために、旧来の写真を「死んだ」/「その地位を永久に奪われた」と述べたのでした。
さて、それから30年あまり経過した現在から見れば、「写真は死んだ」という大胆な死亡宣告は、ちょっと言い過ぎだった感が否めません。
この頃に起こった技術革新の結果として、デジタル写真が主流になり、最近ではAI生成の写真(これをミッチェルはどう考えるのでしょうね)も出てきていますが、それでも「写真を撮りたい!」という気持ちは失われるどころか、増していると言っていいでしょう。
つまり写真は全く死んでいないわけですが、しかしながら当時「写真の死」は、写真家たちにとってはとてもリアリティのあることだったし、写真のデジタル化というメディアの変化による時代の変化を鋭敏に感じ取り、写真の写真らしさに目を向けたのでした。
例えば、「ジオラマ」、「海景」、「劇場」などのシリーズで知られる写真家/現代美術家の杉本博司は、デジタル写真が主流になりつつある状況に際して、「最後の写真家」と自身を語っていたことがあります。
確かに杉本の写真は、アナログの大型カメラで撮影される高精細で美しいプリントと、コンセプトが高いレベルで一致した作品であり、当時のデジタルカメラではおそらく不可能な表現だったはずです。
しかし(杉本博司の偉大さは認めつつも)やっぱり「最後の写真家」を宣言するには時期尚早過ぎたような気がするし、実際、写真とはなにか、について問う優れた写真家は以降にも現れているし、いまだにアナログ(フィルム)にこだわって写真を撮る人もいます。
さて、この「写真は死んだ」という宣言のなかにある「写真」と「死」の関係は、写真作品や写真芸術についてまわる「失われたもの/失われていくもの」を愛でる精神とも、関係があるかもしれません。
以前、ロラン・バルトの写真論についての回 で書いたように、バルトは写真の本質を「それは、かつて、あった」と述べて、写真はそこに写ったものを「現実のものであり過去のものである」と感じさせるものであるとしました。
「現実のものであり過去のものである」というのを最大限にかっこよく言ったのが「それは、かつて、あった」ですが、ちょっと具体的に言えばこれは「目の間に存在していたのに、もう失われてしまったもの」ということになるでしょうか。
被写体が「失われる」のは、写真家がその被写体(ある場所の風景)から移動したり、あるいは被写体(例えば動物とか)が移動したりする場合もありますが、そこに写っていた人やものが本当にもうどこにもいなくなってしまっているという場合もあります。
多くの人々が、表現としての写真に(趣味としても、鑑賞体験としても)惹かれるのは、この技術が本来的に持っていたロマンチックさや切なさによるところも大きいのではないかと思います。
つまり、写真がいまだに死んでいないのは、写真自体が想起させる「死」の感覚のようなものがまだ失われていないから。写真に染み付いた「死」の感覚はなかなかしぶといのです。
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。日本大学芸術学部写真学科助手を経て、東京工業大学大学院博士後期課程在籍。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post 連載「きょうのイメージ文化論」、幻冬舎Plus「現代アートは本当にわからないのか?」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
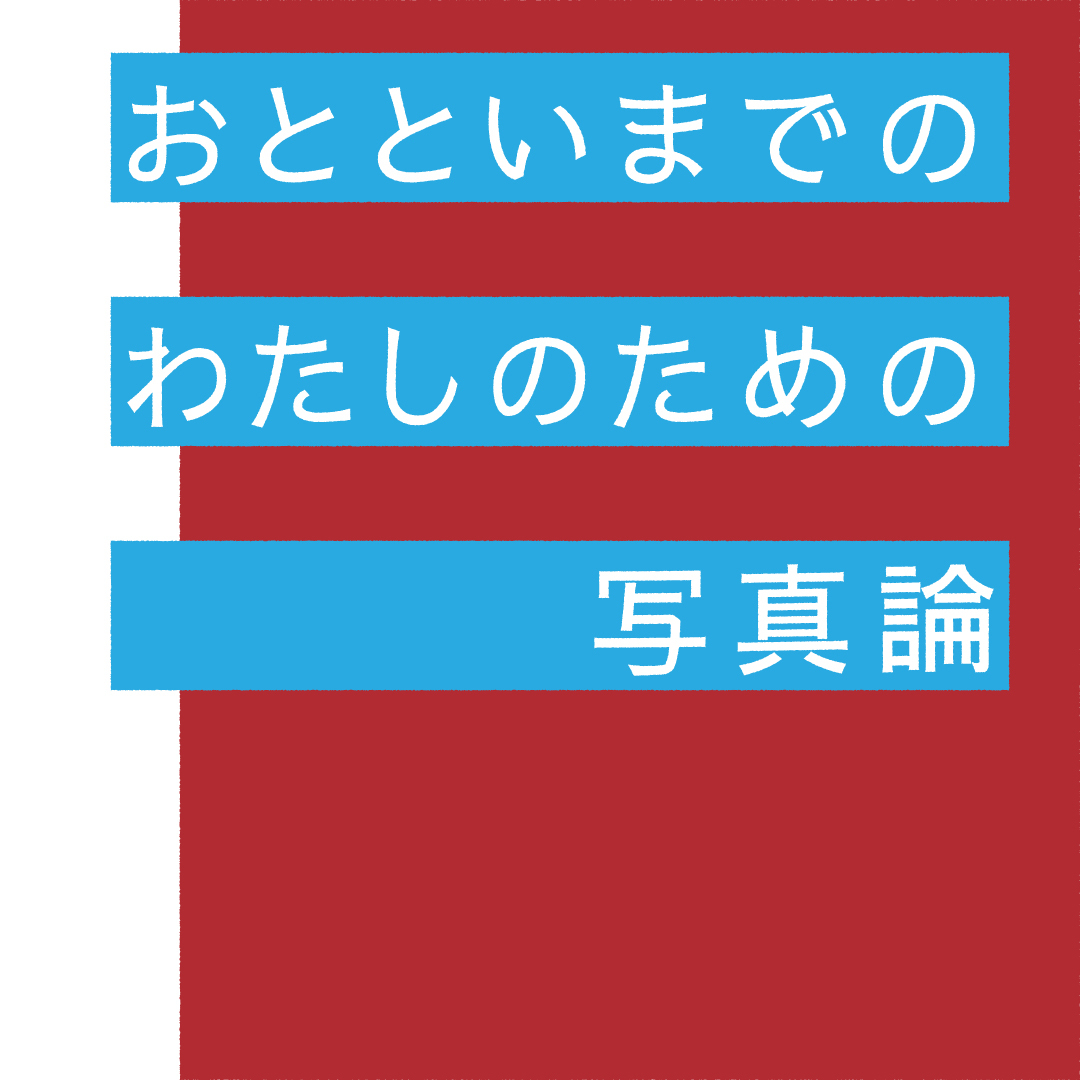
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
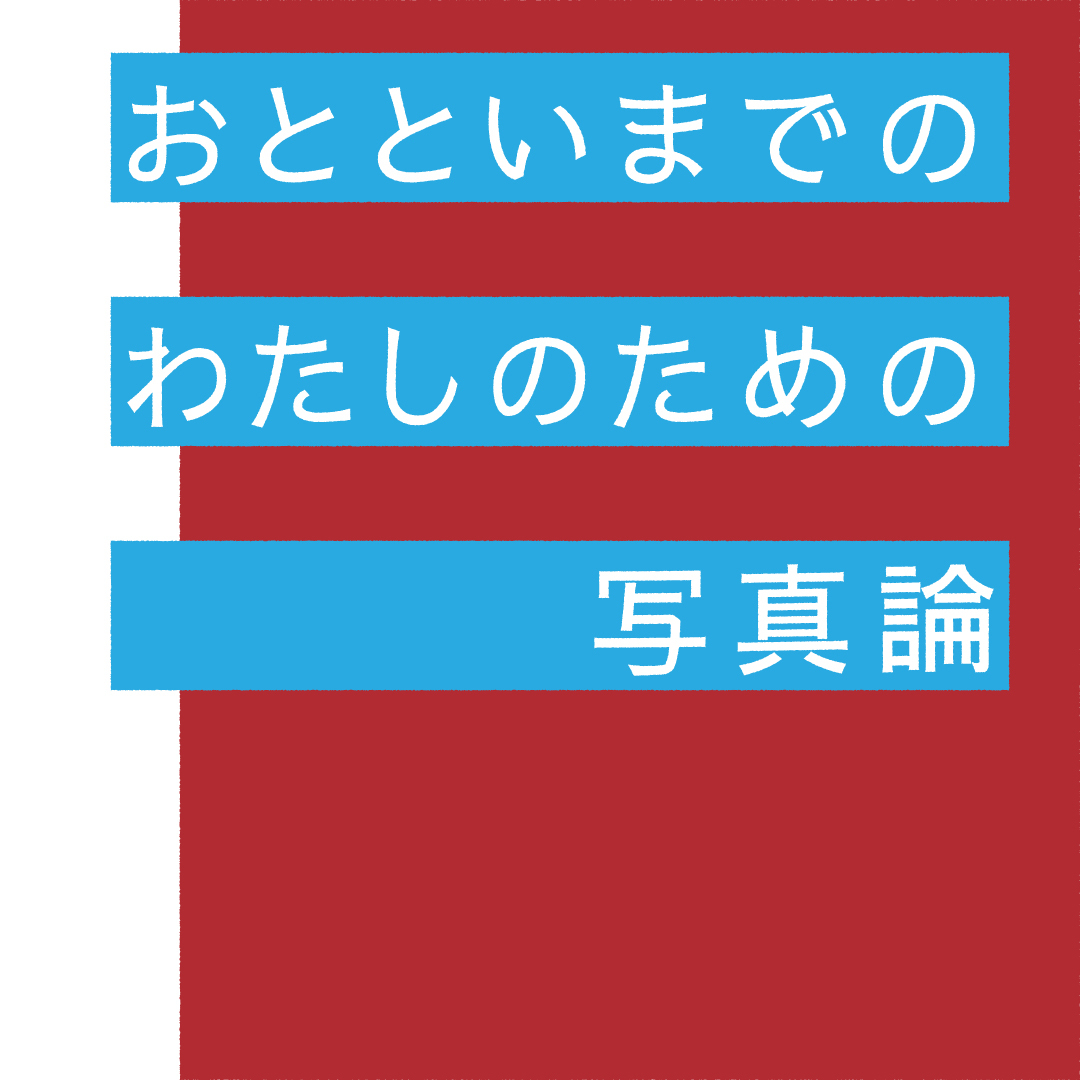
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
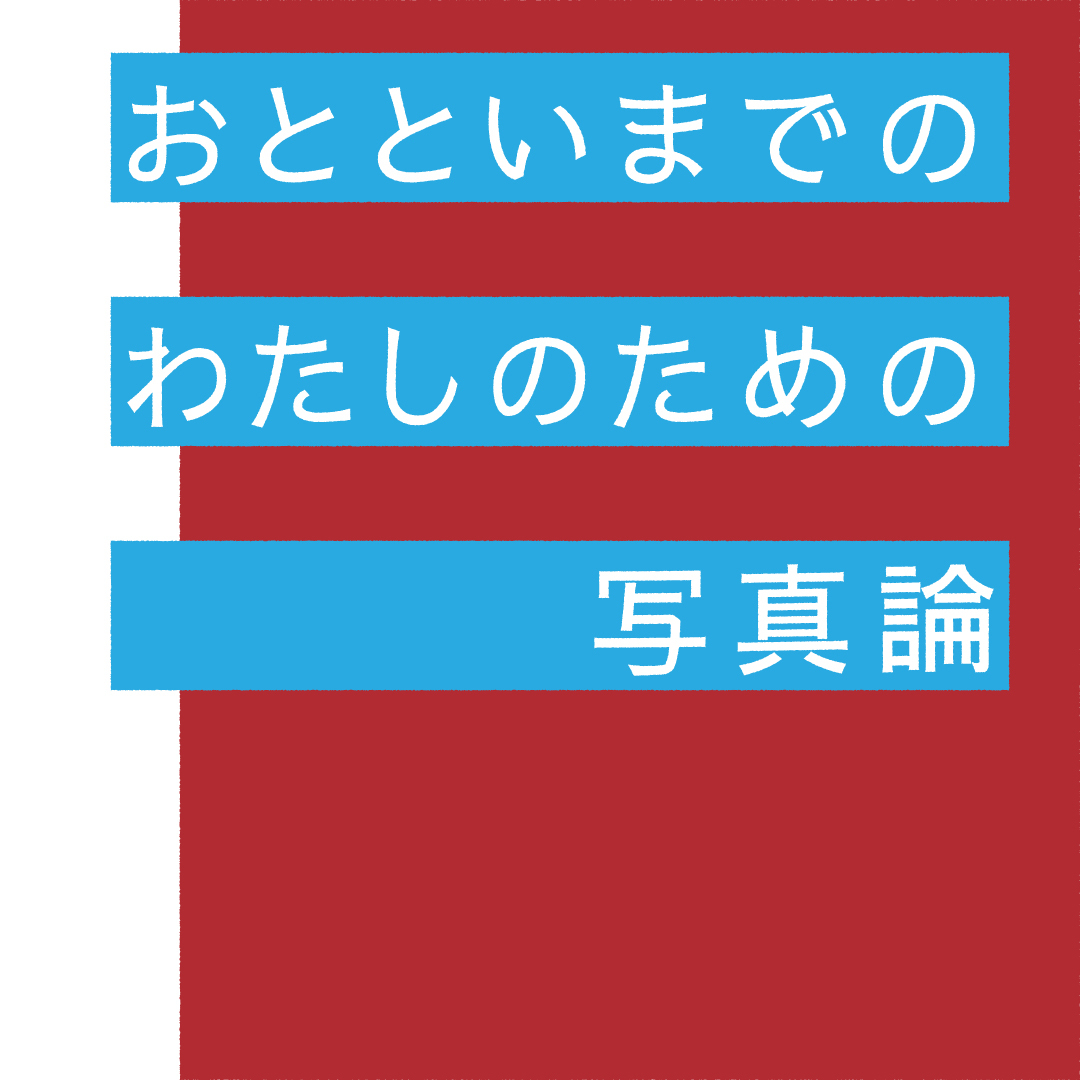
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日

カルチャー
写真の写真を撮る–アクスタ写真論
文・村上由鶴
2023年11月30日

カルチャー
無遠慮と無節操の芸術
文・村上由鶴
2023年10月30日

カルチャー
自分の土俵で横綱相撲
文・村上由鶴
2023年9月30日

カルチャー
写真はもう、感動的に映らない?
文・村上由鶴
2023年8月30日

カルチャー
熱狂の偽造
文・村上由鶴
2023年7月30日

カルチャー
禁じられた斜め
文・村上由鶴
2023年6月30日

カルチャー
土門拳と、続・写真「薄い」問題
文・村上由鶴
2023年5月31日

カルチャー
ティルマンスと「写真薄い」問題
文・村上由鶴
2023年4月30日

カルチャー
Y2Kとコンデジの質感
文・村上由鶴
2023年3月31日

カルチャー
冷蔵庫の熱いエモーション
文・村上由鶴
2023年2月28日

カルチャー
いま、写真に証明できるものはあるか?
文・村上由鶴
2023年1月31日

カルチャー
セルフポートレートの攻撃力
文・村上由鶴
2022年12月31日

カルチャー
スクショは写真なのか
文・村上由鶴
2022年11月30日

カルチャー
写真に宿る邪悪なパワー
文・村上由鶴
2022年10月31日

カルチャー
追悼:ウィリアム・クラインについて
文・村上由鶴
2022年9月30日

カルチャー
セルフィー・エンパワメント ー Matt氏に象徴される現代の写真論
文・村上由鶴
2022年8月31日

カルチャー
写真のイデオロギー 信奉と冒涜のあいだ
文・村上由鶴
2022年7月31日

カルチャー
写真に撮れないダンスから考える「見る」経験のいろいろ
文・村上由鶴
2022年6月30日

カルチャー
感受性スーパーエリート?ロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を噛み砕く
文・村上由鶴
2022年5月31日

カルチャー
ハッキングされているのは写真でありわたしであるー純粋に写真を見れると思うなよ
文・村上由鶴
2022年4月30日

カルチャー
写真をめぐる「・・・で?」の壁と「写真賞」
文・村上由鶴
2022年3月31日

カルチャー
スーパーアスリートとしての写真家ー「写真的運動神経」論
2022年2月28日

カルチャー
「写真家」と文明を生きるわたしたちに違いはあるのか―「あえ」る写真論
文・村上由鶴
2022年2月1日
ピックアップ

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日