ライフスタイル
百人町スナイパー/文・佐藤究
僕が住む町の話。Vol.19
2023年7月4日
cover design: Eiko Sasaki
text & photo: Kiwamu Sato
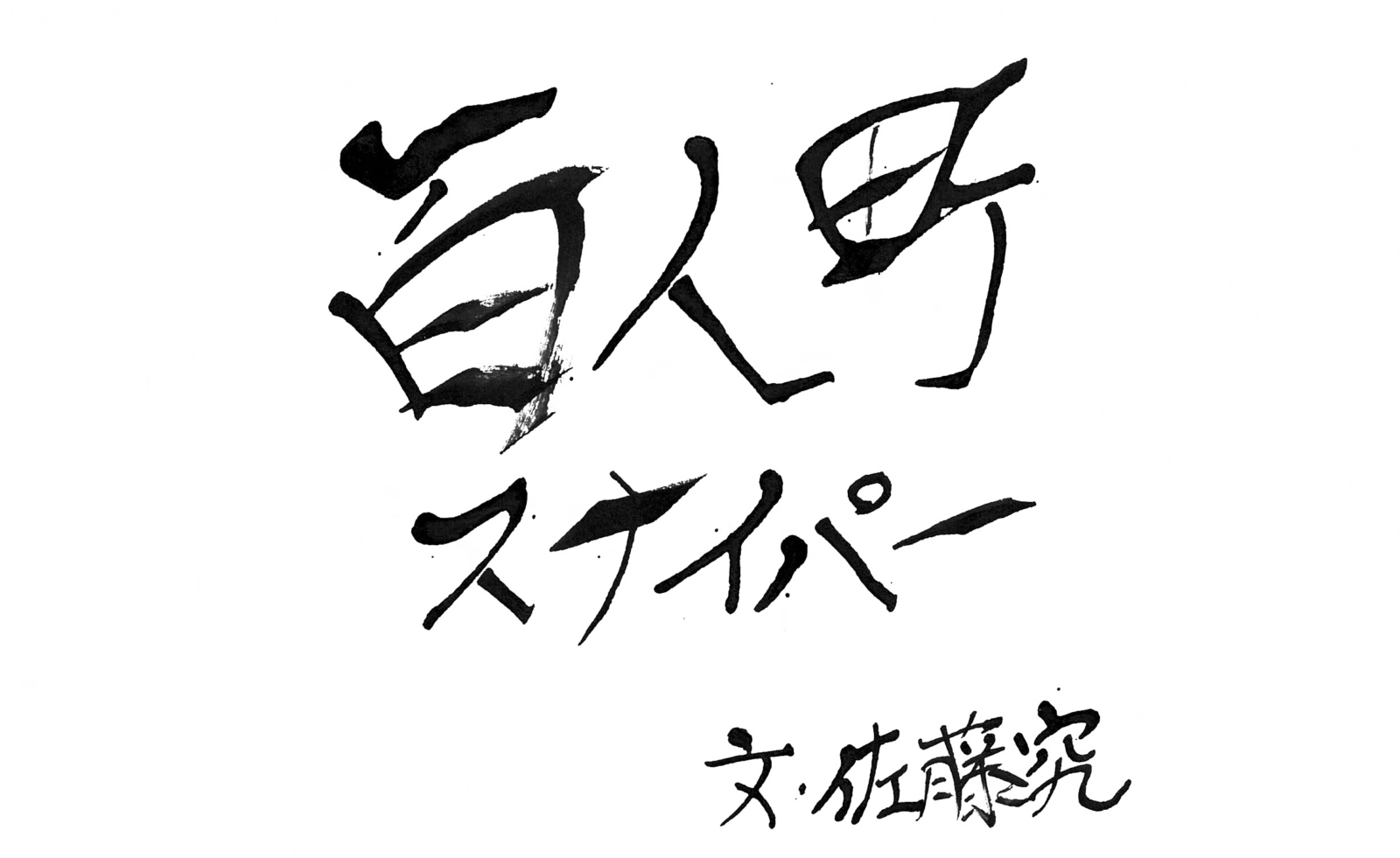

新宿区百人町一丁目は、大久保通りと職安通りに挟まれた一帯で、町内に伸びる細い路地を一方へ歩けば、韓流カルチャーで沸き立つコリアンタウンの大変な喧騒がひろがり、その騒がしさを避けて真逆に向かえば、東洋随一の歓楽街、歌舞伎町が待ち受けている。
たった数分歩くだけで、小さな町の両端に強烈なカオスが出現する。人も店も看板の数も並ではない。コリアンタウンと歌舞伎町に挟まれた町に住んでいたら、眠い目をこすりながらちょっと散歩に、と出かけたところで、ろくに目覚めないうちに群衆のなかへ放りこまれる。とくに昼間のコリアンタウンの混雑はすごかった。「竹下通りより人が多い」という声が聞こえてきたほどである。
まっすぐな路地を歩くひとときの静けさと、いきなり現れる過剰なまでのカオス、この両極端にひたすら翻弄される日々が、すなわち百人町一丁目に住むということだった。
私は2019年の夏までそこで暮らした。ひそかな散策の時間を持ちたいという人には不向きの町にちがいない。少し歩けば西大久保公園があったが、セキュリティ上の理由で夕方にはフェンスが閉ざされ、出入り口は施錠されてしまう。
作家として独立するつもりで福岡から上京した私にとって、百人町は東京という巨大な都市の魔力に面した境界であると同時に、この都市に根ざした過去のない部外者の自分を受け入れてくれるような、ある種の安らぎを味わえる町だった。
笑ってしまうほどに作家業はうまくいかず、三十代もアルバイトで食いつなぎ、仮に〈安定した人生〉という名の国があるとしたら、私はまちがいなくその国にとっての異邦人になっていたが、百人町はまさに異邦人のためにあるような町だった。
中国、韓国、ベトナム、ネパール、さまざまな国から海を渡ってきた人々が、かつて徳川家に仕えた鉄砲組百人隊の同心が住んだ町(それが町名の由来だ)に小さな部屋を借りて寝起きし、日本語を学び、コインランドリーで服を洗濯し、仕事を探し、それぞれの人生のチャンスを求めて生きていた。たとえ先が見えなくても、一日一日を生きる。その大切さを私に教えてくれたのは、多国籍化した百人町という町そのものだったといえる。
ところで百人町には、前述した鉄砲組百人隊の参拝した「皆中稲荷神社」がある。「皆中」は「かいちゅう」と読む。境内こそ小さいけれど、的に弾を当てるという霊験から転じて、〈賭け事〉のご利益がある神社として有名になった。
食えない作家をつづけるのも、賭けといえば賭けだ。稲荷神社は私のいた部屋のすぐ近くにあったが、当時の私はあえて参拝せず、何も祈願しなかった。作家というのは神の不在に向き合う仕事ではないか。たとえ知名度がまったくないとしても。
そんな百人町に暮らしていたある日、「今夜はスーパームーンが見られる」というニュースを耳にした。月が地球に接近し、しかも満月なので最大に見えるという天体現象である。
夜になって私は、せっかくだから路地に出て月を見上げようと思い立った。それなら何かレンズがあったほうがいい。あいにく双眼鏡も望遠鏡も持たなかったが、小説の資料として所有していた、東京マルイのトイガンのスナイパーライフルに付いているスコープに目をとめた。レンズ口径は小さいが、肉眼よりはましだろう。ただし、BB弾が出るだけのトイガンとはいえ、スコープ付きのライフルを抱えて堂々と表に出るわけにはいかない。
私は本体からスコープだけを取り外し、それを手にして部屋を出た。路地にはすでに多国籍の隣人たちがいて、一様に夜空を見上げていた。
全長30センチばかりのスコープを片目に押し当て、私が月を眺めていると、たどたどしい日本語で声をかけてくる人がいる。アジアの別の国からやってきたその女性は、私の持つスコープで月を見たがっていた。私は一瞬とまどった。貸すのはかまわないが、このスコープをのぞけば、長距離射撃用のレティクルと呼ばれる十字線が視野に現れる。見る人が見れば、すぐにそれとわかる。
しかし説明するのも面倒なので、私は黙ってスコープを彼女に手渡した。彼女はさっそく満月を眺め、するとその後ろに、路地で夜空を見上げていた数人が並びはじめた。無料の望遠鏡サービスは見逃せない、といった風情である。だが、皆が順番にのぞくのはふつうの望遠鏡ではなく、ゴルゴ13のようなスナイパーのためのスコープなのだ。
それはじつにシュールで微笑ましい光景だった。
今になって振り返ってみれば、私に作家の仕事がそこそこ来るようになったのは、あの町の路地に立って、スナイパー用のスコープで月を眺めたおかげかもしれない。町に息づく鉄砲組百人隊の魂がその様子を面白がって、運をくれたような気もする。だとしたら私は結局、皆中稲荷神社の霊験にあやかったことになる。
それはさておき、あの夜、十字に区切られた月をいっしょに眺めた人たちは、今ごろどうしているだろうか。
プロフィール
佐藤究
さとう・きわむ|小説家。1977年福岡県生まれ。2004年に佐藤憲胤名義の『サージウスの死神』が第47回群像新人文学賞優秀作に選出されデビュー。2016年に『QJKJQ』で第62回江戸川乱歩賞、2021年に『テスカトリポカ』で第34回山本周五郎賞、第165回直木賞を受賞。最新作『幽玄F』が『文藝』2023年夏号に掲載。
Twitter
https://twitter.com/sato_q_book
関連記事

ライフスタイル
あの世を臨む聖護院/文・尹雄大
僕が住む町の話。Vol.18
2023年3月4日

ライフスタイル
好きになれなかった三軒茶屋/文・福徳秀介
僕が住む町の話。Vol.17
2023年2月4日

ライフスタイル
ゴロゴロできる町/文・安藤なつ
僕が住む町の話。Vol.16
2023年1月4日

ライフスタイル
大崎一番大悟/文・松居大悟
僕が住む町の話。Vol.15
2022年12月8日

ライフスタイル
愛は町に無い。/文・小林私
僕が住む町の話。Vol.14
2022年11月4日

ライフスタイル
オレが撮らなかった町/語・井筒和幸
僕が住む町の話。Vol.13
2022年10月4日

ライフスタイル
誰も知らない高島平/文・峯岸みなみ
僕が住む町の話。Vol.12
2022年8月4日

ライフスタイル
コリアンタウンの猫/文・おいでやす小田
僕が住む町の話。Vol.11
2022年7月4日

ライフスタイル
ノマド的自主興行/文・須藤蓮
僕が住む町の話。Vol.10
2022年6月4日

ライフスタイル
東京日記(ふりかえり)/文・玉城ティナ
僕が住む町の話。Vol.9
2022年3月8日

ライフスタイル
風の迷路となるまちで/文・崎山蒼志
僕が住む町の話。Vol.8
2022年2月5日

ライフスタイル
東京すみっコぐらし/文・片桐はいり
僕が住む町の話。Vol.7
2022年1月8日

ライフスタイル
摩天楼とジーンズ/文・新川帆立
僕が住む町の話。Vol.6
2021年12月4日

ライフスタイル
鎌倉のチベット/文・角幡唯介
僕が住む町の話。Vol.5
2021年11月6日

ライフスタイル
横浜のチベット/文・xiangyu
僕が住む町の話。Vol.4
2021年10月2日

ライフスタイル
Hamilton/文・Phum Viphurit
僕が住む町の話。Vol.3
2021年9月4日

ライフスタイル
真のシロガネーゼ/文・板倉俊之
僕が住む町の話。Vol.2
2021年8月7日

ライフスタイル
オッケー、鴨川/文・大前粟生
僕が住む町の話。Vol.1
2021年7月3日
ピックアップ

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日

PROMOTION
雨の日のデーゲーム
POLO RALPH LAUREN
2026年3月10日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日

PROMOTION
坂本龍一の音楽とともに。渋谷PARCOは「人」から伝える。
渋谷PARCO
2026年3月12日

PROMOTION
Gramicci Spring & Summer 26 Collection
Gramicci
2026年3月10日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日

PROMOTION
もし友達が東京に来たら、教えてあげたいことがある。
EX旅先予約で巡る、1日東京アートデート。
2026年3月11日

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日