ライフスタイル
Hamilton/文・Phum Viphurit
僕が住む町の話。Vol.3
2021年9月4日
cover design: Eiko Sasaki
text & photo: Phum Viphurit
coordination: domu
translation: Erika Minegishi
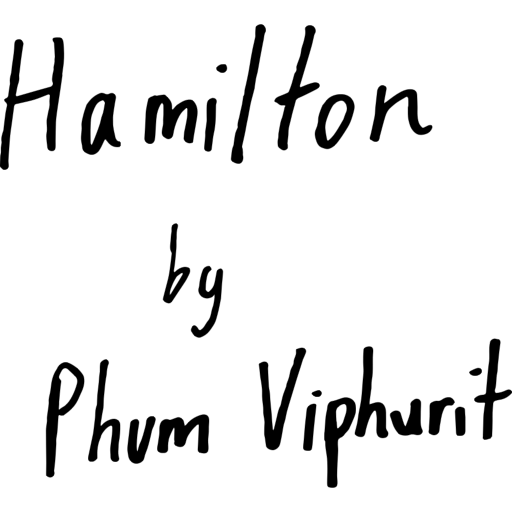

かつての異国の地にあったあの記憶は、ぼくを故郷へと連れ戻した
9歳の少年が、12時間かけて家族とともに、小さくて一面木々に覆われた地方都市へと飛んだのは、ひんやりとした8月のある日のことだった。その子は若く未熟で、そよ風の肌寒さや、遠く離れた地の冷たい風に迎え撃つにはまだ早かった。そのときは、外から内を見る気持ち——自分は外国から来たよその人間だという孤立感に苛まれていた。いずれそこが、本当の故郷だと言えるようになるとは思ってもいなかった。
ハミルトンは2005年当時、人口約40万人の学園都市だった。この町は、ニュージーランドで最も退屈な都市のひとつとみなされていて、特に有名な観光地でも、とっさに注目されるような都市でもなかった。9歳から10歳になろうとしていたとき、英語力はゼロに近い状態で、まるでアイスクリームの上にぽつんと置かれたチェリーみたいに、自分の置かれた環境に戸惑い、不安を感じていたことを覚えている。迷子っていうわけではないけれど、しっかりとした足場がなくて、不慣れな水の上に浮かんでいる感覚だった。
引越し先の1軒目は、大通りに面した家だった。通りの名前ははっきりとは覚えていないけれども、ハミルトン・ガーデンズ——インドやイタリアの植物園なんかの、世界の文化をテーマにした手の込んだデザインを有する広大な庭園——に程近かった。2階建ての地下付きの家で、中に入る前の坂道の玄関アプローチは、まるで雑誌にでてくる郊外に住む家族の家みたいな、理想的なニュージーランドのマイホームを思わせた。ぼくの頭の中は、スケートボードでコンクリートの坂を下ってガレージを突き破り、優雅に転がりながら地下にあった自分のベッドにたどり着けたらどんなに楽しいかっていうことだけでいっぱいだった。
合わせて3人——ぼくと母と兄 は、窓の一切ない地下の部屋で6カ月は過ごした。こうやってタイプされた文章を読むと怖そうだけれど、実際、こんなにも快適で安全な場所は他にないほどだった。確かにもう少し自分だけの空間が必要だったかもしれない。とはいえ、そのときはそれで十分だった。部屋のレイアウトはシンプルで、ぼくと兄は二段ベッドへ。部屋を見渡せる上の段はぼくがゲット。母はいつもながらにクイーンサイズのベッドの上で雑誌を読んでいるか、外へ出て仕事をしているかで、兄は二段ベッドの下でやりたいようにやっていた。ドアの横には古びたソファーがあって、掃除機できれいにしても何かといつもほこりっぽかった。母が家にいないときは、ソファーに勢いよく飛び乗ったり、使い古した柔らかい枕を敷いて、ブラウン管のテレビに釘付けになったりして楽しんでいた。たった2つのニュース番組と1つのローカル音楽番組が、ぼくの想像力を、あの暗い箱部屋の外にまで広げることになるなんて誰も予想していなかった。こぢんまりとしたあの家も楽しかったけれど、また引っ越すまでにそんなに長くはかからなかった。
ハドソン・ストリート8A番地の家は、前の地下の家と比べたら申し分なかった。もう、オーナーの家に間借りをしなくてよくなったから。そこはおしゃれな住宅街で、フェンスのないレンガ造りの家にダークブラウンの木枠があしらわれ、上品な小庭がついている、というのがよくある光景だった。ぼくらの家は、スコットランド人の家の裏手にあって、コンクリートの道を少し行くと、長方形の平家にコンパクトなガレージと、ちょっとした庭のスペースがあった。ガラスの玄関ドアを開けると澄み切った空気が家中に広がり、まるでオフィスのような大きなブラインドがあるリビングには、いつもたくさんの日差しが入ってきた。外が寒くても、リビングにいれば自然の暖かさを感じられた。母がMacのデスクトップを置いていた仕事エリアを抜け、人生初のオーブン付きのキッチン——長年かけて、アップルクランブルのレシピを完成させていった場所でもある——へと続いた。どこにでもある、ありふれた空間のひとつにしか過ぎないけれど、ぼくにとってはかけがえのない場所だった。
この2軒目の家には、ニュージーランドでの残りの数年を過ごした自分の寝室があった。今までの地下の共同部屋よりも狭い部屋とはいえ、ようやく自分だけの部屋ができて、自立の一歩を踏み出せた気分だった。気温が0度を下回る夜には欠かせない、愛用の電気毛布も常備していた。ぼくが初めてカバー曲をレコーディングしたときは、ベッドの向かいの白い壁が完璧な背景になったし、その家から見える景色はそれほど素晴らしいわけではなかったものの、家のフェンス越しに地平線が見えて、日の出と日没を眺める独りの時間は特別だった。何年かたって皮肉にも、休暇で家族とタイに帰省している間に、誰かがあの壁を超えることになる。あの夏、家に泥棒が入ったことがわかった——キッチンの窓は強引に開けられていて、床一面に泥まみれの大きな足跡が残っていた。空になった家に戻ったとき、頭にきたし多少の怖さはあったけれど、それでもここは自分の家だって感じた。時間がたつにつれて、また日常の生活に、ゆっくりした平和な日々に戻っていき、あの長方形の建物は息を吹き返したようだった。
ぼくがこうやって、これまでの生活を語ることで、ハミルトンへの間違った印象を与えたくはない。実際、目を見張るような素晴らしい場所や思い出がたくさんある。ただここに収まりきらないだけで。ぼくの人生は今、世界中をツアーで駆け巡ることもなく、ゆったりとしたペースに戻っている。ここ、バンコクの実家に落ち着いて、相変わらず不自由なく過ごしていると、たびたびあの小さな四角い部屋の記憶がよみがえる。飾り気のない素朴でむなしい部屋だったけれど、成長するための時間と場所があれば、そこにどれだけの命を吹き込むことができることか——。いつだって、あれは本当の故郷、真の我が家と言ってふさわしい。あのハミルトンの小さな一角を懐かしく思う。

プロフィール
Phum Viphurit
instagramは @phumviphurit
関連記事

ライフスタイル
僕が住む町の話。/文・久住昌之
三鷹。吉祥寺の隣町
2021年4月13日

ライフスタイル
僕が住む町の話。 / 文・いしわたり淳治
空白を彩った自由が丘
2021年4月15日

ライフスタイル
僕が住む町の話。/文・今泉力哉
私と新橋について
2021年5月18日
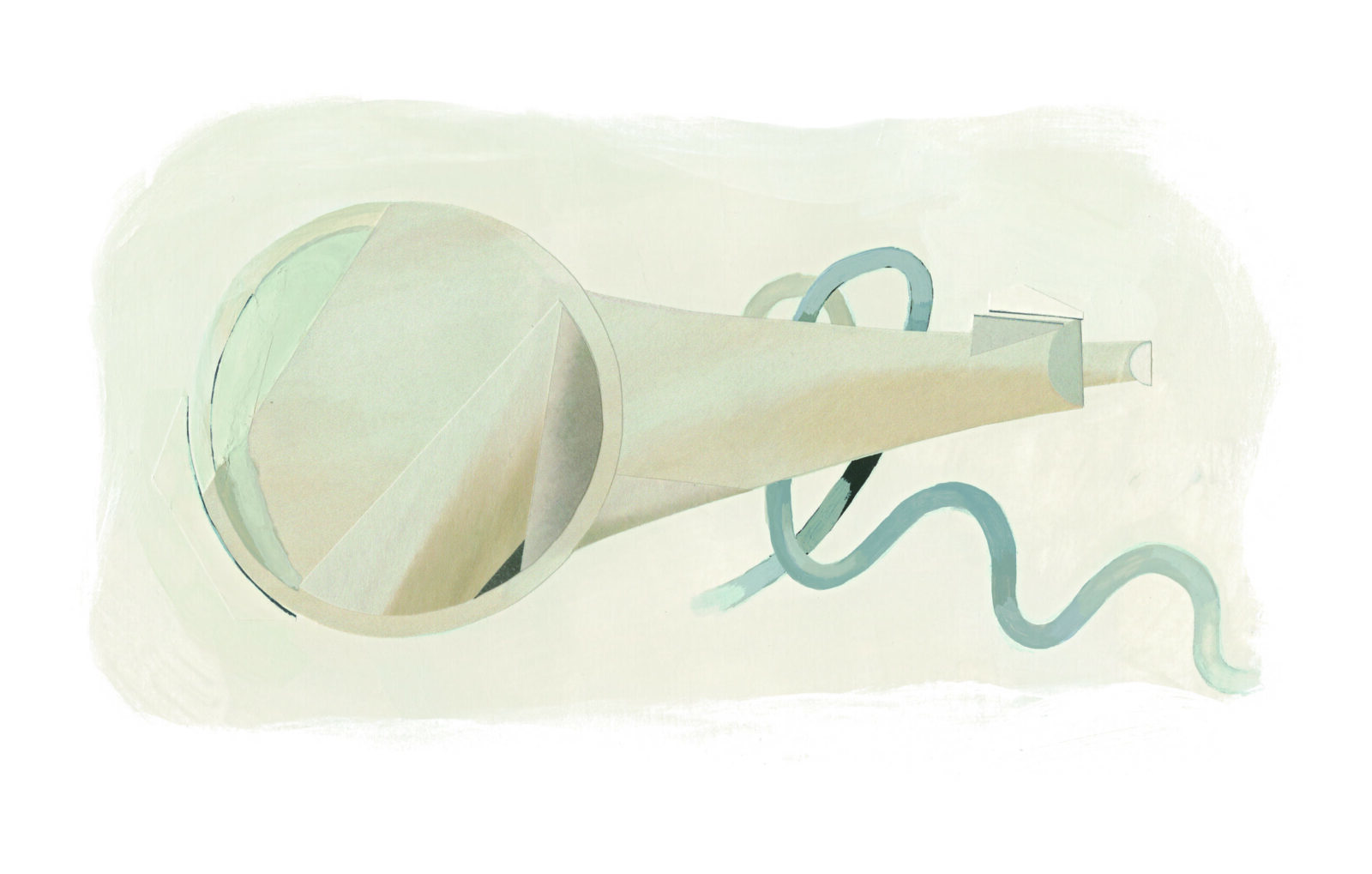
ライフスタイル
僕が住む町の話。/文・飯尾和樹(ずん)
のんびり下馬
2021年6月7日
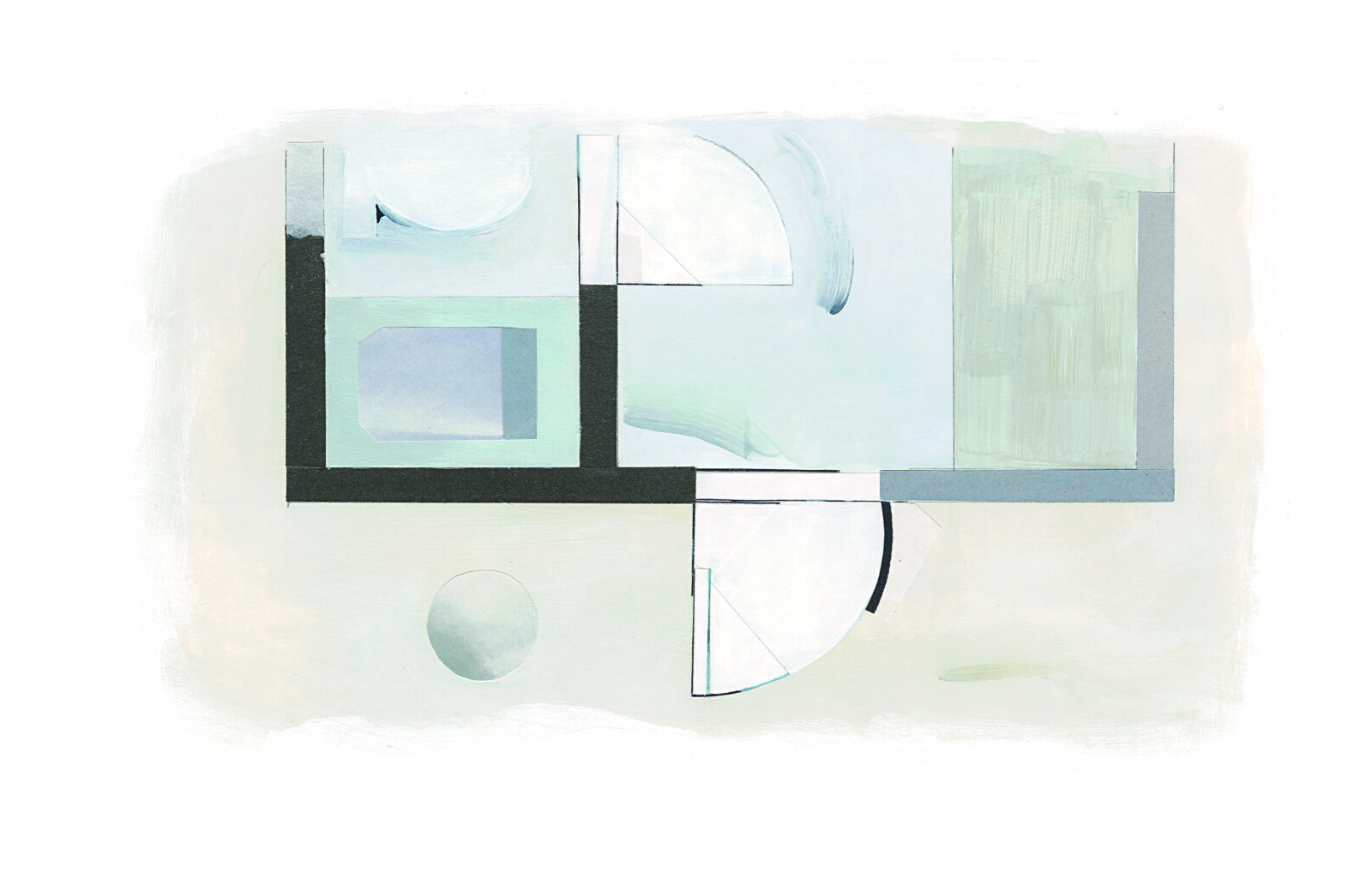
ライフスタイル
僕が住む町の話。 / 文・鴻池留衣
大井町
2021年5月28日
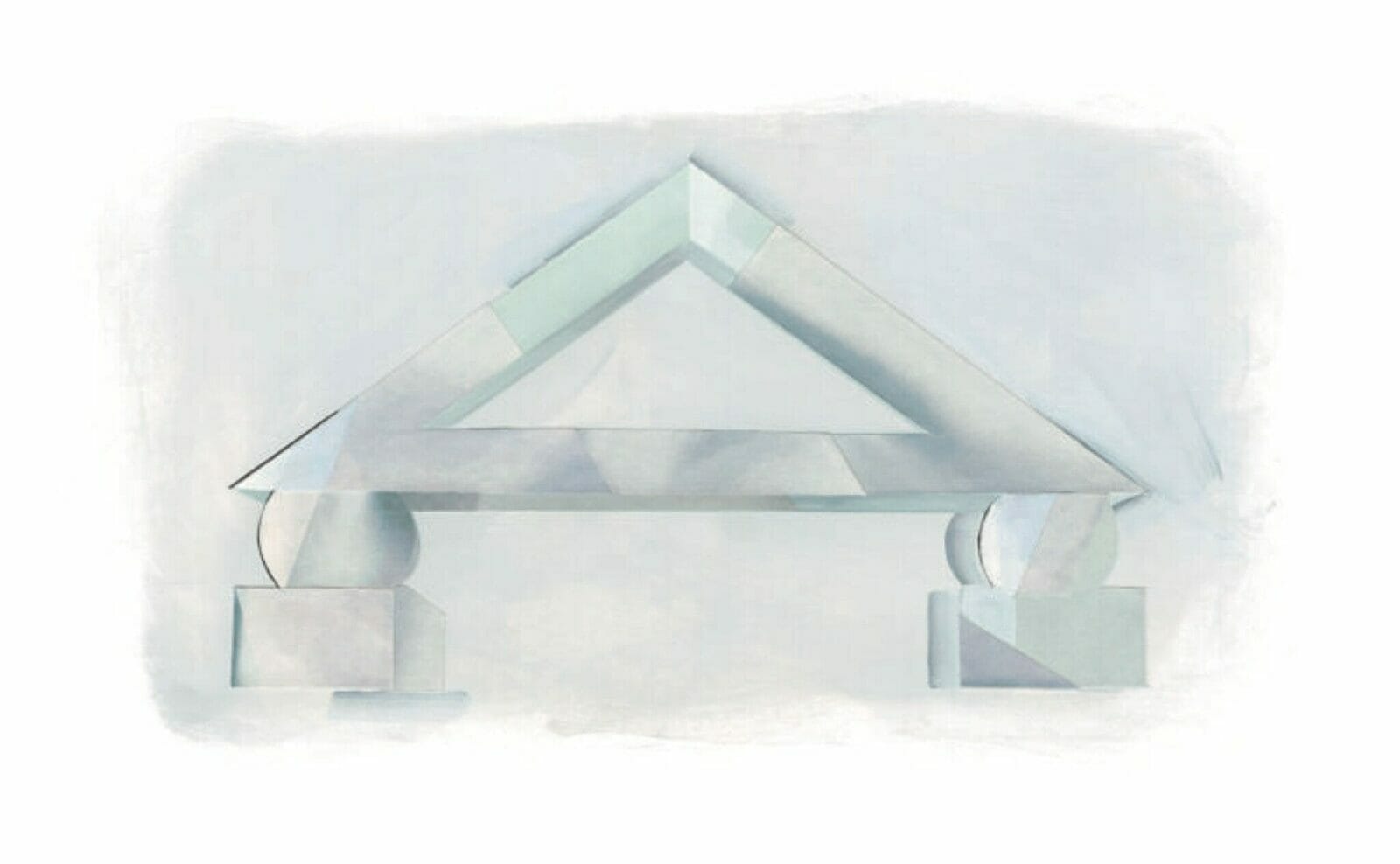
ライフスタイル
僕が住む町の話。/文・ラランド サーヤ
八王子ユーロード
2021年4月27日

ライフスタイル
僕が住む町の話。/文・江原茗一
歩きの街、池尻大橋。
2021年5月7日

ライフスタイル
オッケー、鴨川/文・大前粟生
僕が住む町の話。Vol.1
2021年7月3日

ライフスタイル
真のシロガネーゼ/文・板倉俊之
僕が住む町の話。Vol.2
2021年8月7日

ライフスタイル
City of Mine #Vol.3 by Phum Viphurit
2021年9月4日



