カルチャー
写真は鏡であったり窓であったりする、けどその前に扉でもある
文・村上由鶴
2024年10月31日
text: Yuzu Murakami
写真作品を見ている時、「勿体ぶっていてなにが言いたいかわからない」と思うことがあります。
写真に写っているものは当然具体的で具象的なものなのですが、それを見る感覚は、抽象画を見ている経験に近いのではないかとすら思います。そこに何が写っているかは認識できても、それが何を意味するのかがわからない。こういうなんだか煮え切らない写真の鑑賞経験によってわたしはネガティブな意味で写真に興味を深めていったので、いまだに時々ポカンとしながら写真を見ています。
ニューヨーク近代美術館(MoMA)の写真部門のディレクターを務めたジョン・シャーカフスキーという人がいました。
彼は、写真という、絵画や彫刻から遅れて到来した「技術」を「芸術」に高めるのに大きな功績を残した人物です。そんな彼が企画した展覧会のひとつに「鏡と窓」展という展覧会があります。
この展覧会は写真作品を、自己表現(selfexpression)とする鏡タイプと、外の世界に目を向け探検し発見する(exploration)窓タイプに分類するという見取り図を示したものです。こうした写真の整理はいまだに有効であり、「美術館で写真を見ても写真の見方がわからない」という人にとっては大きな助けになるのではないでしょうか(なお、シャーカフスキーは全ての写真を鏡と窓にはっきりと分離できると捉えているのではなくて、鏡と窓というキーワードをグラデーションの左右の極としてとらえることを提案しています)。
なかでも、シャーカフスキーが鏡タイプとしてまず名前をあげたのはマイナー・ホワイトで、他方、窓タイプの代表としたのはロバート・フランクでした。
マイナー・ホワイトの写真ははがれたペンキや水面をゆらめく昆布などを写し、間接的に自分の心情や思想を投影するものとして読み解かれていて、一方のロバート・フランクは『アメリカ人(The Americans)』のように、部外者の視点でアメリカ(人)の姿を(意地悪に)発見したものとなっていて、「鏡と窓」の対比をはっきりと示す好例と言えるでしょう。
さて、この展覧会が1978年の企画だったことを考えると、隔世の感があります。写真はその後、カラーが主流になり、そしてデジタル化し、いまやAIが生成するものになりつつあるところです。写真表現もずいぶん多様化して、「鏡と窓」のグラデーションからはみ出るような作品も出てきていますし、逆に「鏡と窓」に引き寄せて考えるならば、現代のわたしたちにとって最も身近な「鏡と窓」はスマホかもしれません。
話を写真に戻すと、最近のわたしが思うのは、鏡か窓か、の前に、写真は扉でもあったはず、ということです。
というのは、ある作品を「これは鏡タイプだな」とか、「この窓タイプの写真がこんな世界に通じていた!」と気づく以前に、「この扉のなかに入ってみたい!」と思わせたり、あるいは「この扉をただただ眺めていたい」と思わせたりするような、シンプルな吸引力を持つ写真に、最近、なかなか新たに出会えていないと、個人的に感じているからです。これは特に最近の、東京で開催されているいくつかの写真展を見ていて思ったことでもあります(わたしが疲れているのかもしれないけど)。
つまり、魅力的だ、と思わせるような「扉の外観」というものがあるはずで、それはすなわち写真の外見的な魅力ということになりますが、個人的に、最近は改めてそのような「写真のルックス」に、良くも悪くも誘惑されていないなと思います。
近年、写真表現がよりコンセプチュアルになり、抽象性が高まったり、制作プロセスという「行為」自体を作品とする写真があったりして、そのなかで、必ずしも写真の外見的な魅力が問われないような傾向があったと思います。そしてわたしはそういう写真が好きですし、「写真表現のルッキズム」的傾向への抵抗として賛同しつつ受け取っていたのですが、もしかしてそれが、視覚的要素から写真に興味を持つ人を、「扉」の外に締め出していたかもしれません。
これはある意味で「結局見た目が大事ってこと?」というような、表層的で卑近な話という気もしますが、写真以外のあらゆる芸術作品にも言われてきたことです。例えば、現代アートで言えば、抽象表現主義からミニマリズム、そしてコンセプチュアルアートへの流れ、そしてそこに与しない具象絵画の登場など、美術の歴史では作品を通じて議論されてきています。
写真を含む芸術一般から視覚的な要素がなくならず、外見的な魅力にはいまだに美的な価値が置かれています。そして、それがなかなか無くならないのは、鏡であったり窓であったりする前に、視覚芸術一般が「扉」として、その奥に鑑賞者を誘うものだからでしょう。その誘惑は、時々、星のカービィのような吸引力と強引さで鑑賞者を扉の奥に引き入れるのであり、それが芸術の恐ろしくて美しいところ、という気がします。
「真剣に考えてもらうには、結局ルックが重要」というと元も子もないですが、そうした要素を全く無くしたとき、写真は(そして写真以外のあらゆる視覚的な表現は)鏡でも窓でも扉でもなく、単なる壁のように他者を拒絶するものにもなってしまうかもしれない、と思うのでした。ではまた!
プロフィール
村上由鶴
むらかみ・ゆづ|1991年、埼玉県出身。写真研究、アート・ライティング。日本大学芸術学部写真学科助手を経て、東京工業大学大学院博士後期課程在籍。専門は写真の美学。光文社新書『アートとフェミニズムは誰のもの?』(2023年8月)、The Fashion Post連載「きょうのイメージ文化論」、幻冬舎Plus「現代アートは本当にわからないのか?」ほか、雑誌やウェブ媒体等に寄稿。
関連記事

カルチャー
実態のない「秋田美人」
文・村上由鶴
2024年9月30日

カルチャー
正しさよりも優れていること
文・村上由鶴
2024年8月31日

カルチャー
写真とエモーショナルな政治
文・村上由鶴
2024年7月31日

カルチャー
なかなかしぶとい
文・村上由鶴
2024年6月30日

カルチャー
映画『関心領域』と写真
文・村上由鶴
2024年6月5日
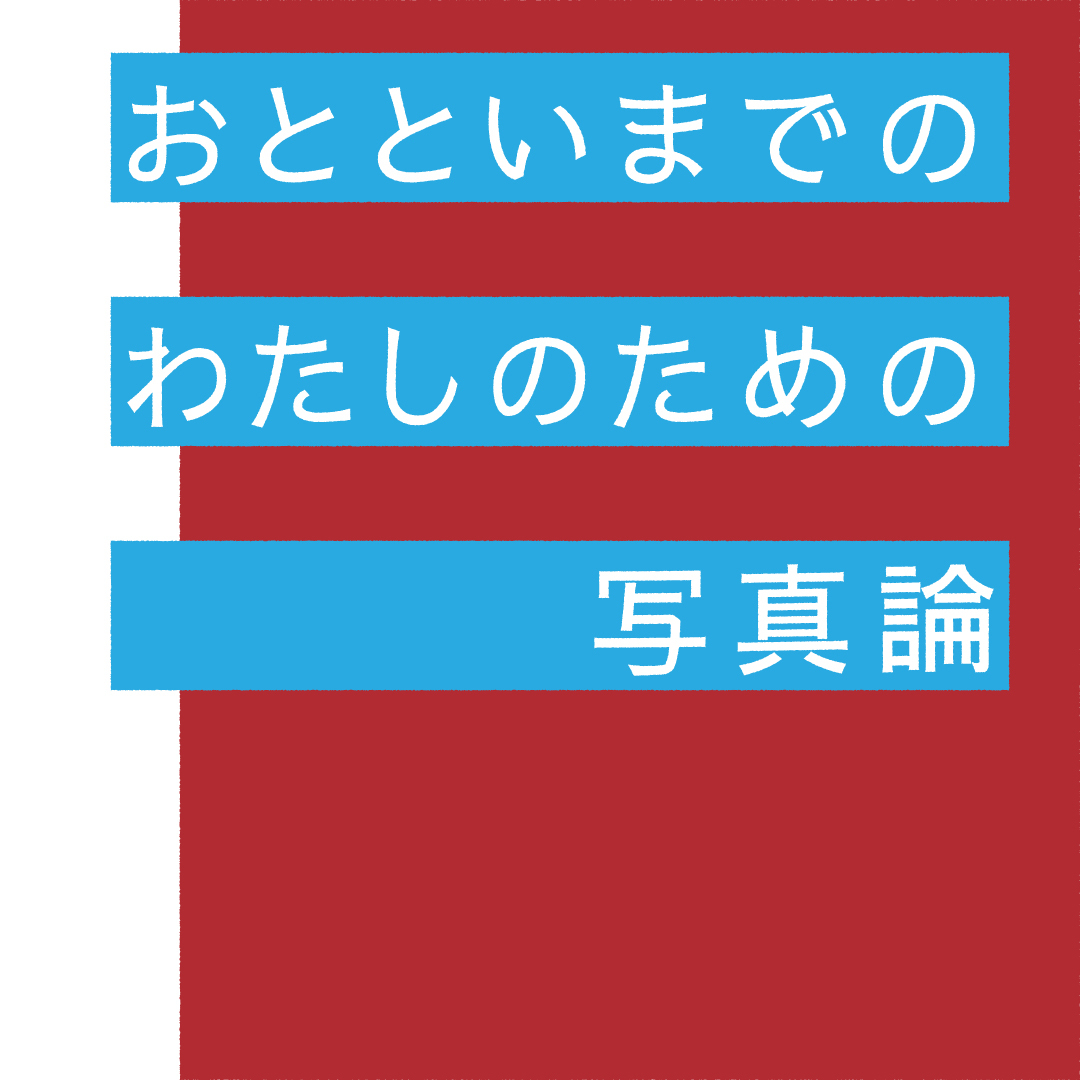
カルチャー
見慣れないでいること
文・村上由鶴
2024年4月30日
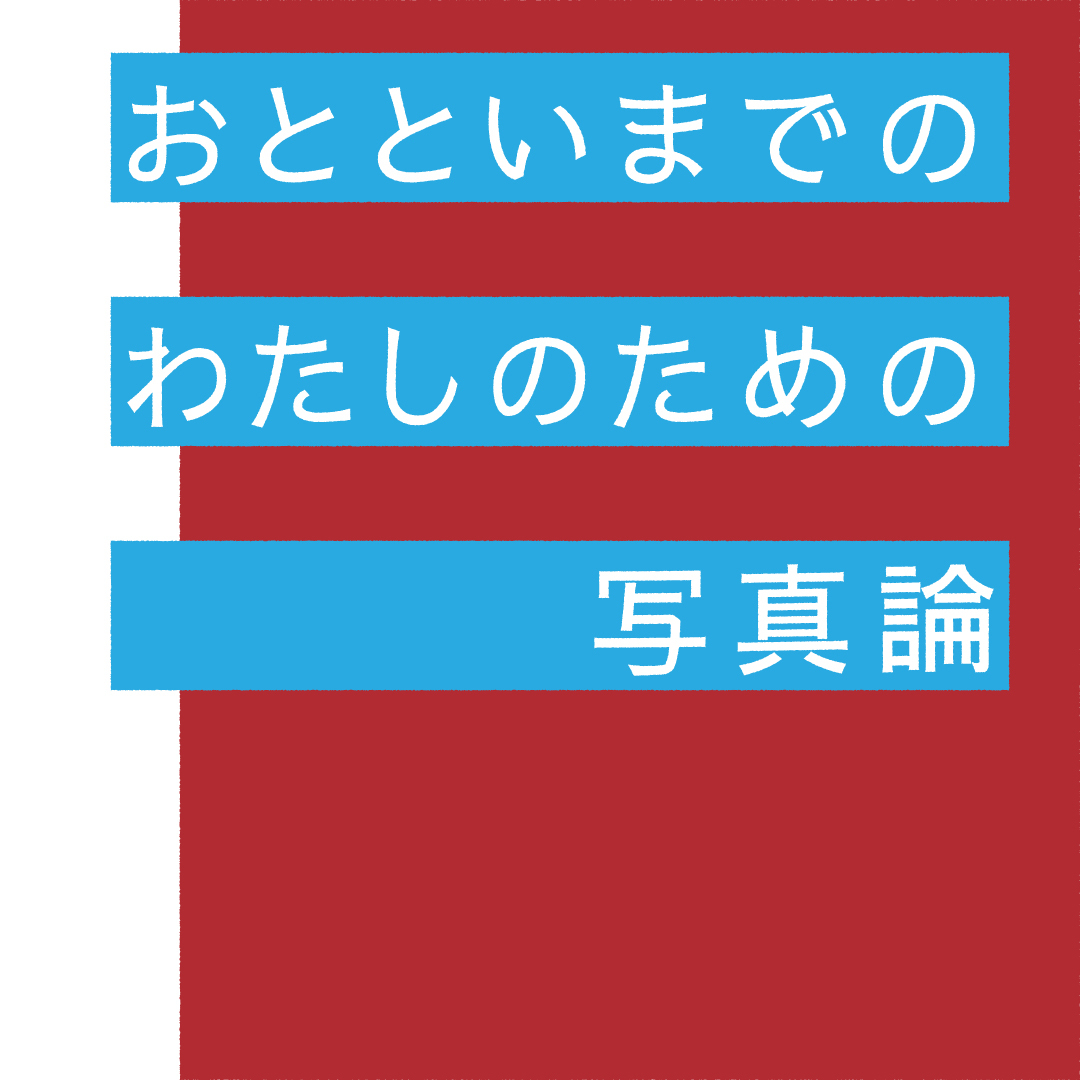
カルチャー
おうち探しと写真
文・村上由鶴
2024年3月31日
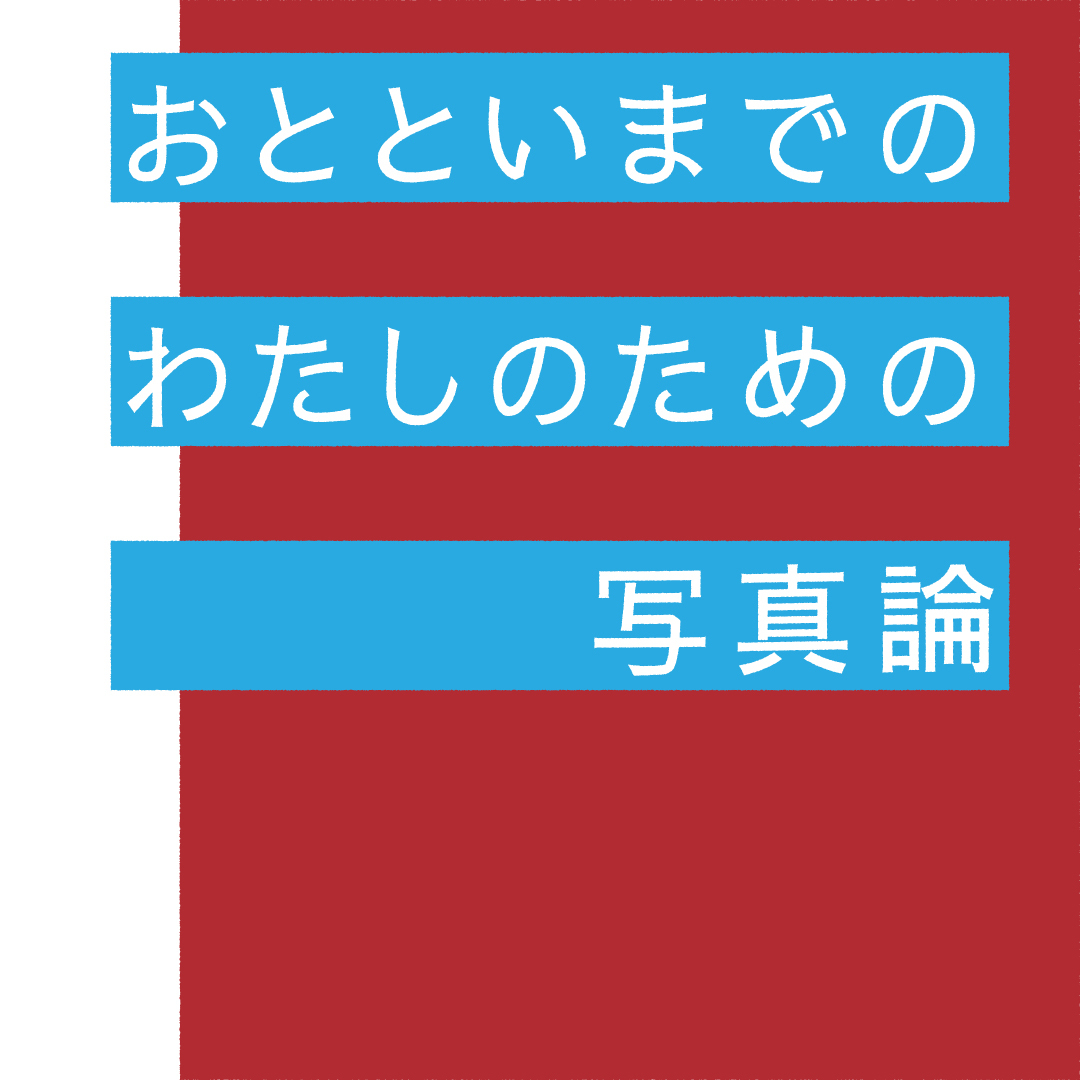
カルチャー
中平卓馬の言葉のフィルター
文・村上由鶴
2024年2月29日

カルチャー
写真の人–篠山紀信について
文・村上由鶴
2024年1月30日

カルチャー
2023年の「写真?」を振り返る
文・村上由鶴
2023年12月30日
ピックアップ

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日