カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.23
紹介書籍『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
2024年6月15日
text: Densuke Onodera
photo: Yuki Sonoyama
edit: Yu Kokubu
新自由主義に抗うための労働と読書の両立
「子どもが生まれてから20年間、本なんか一冊も読んでないわ」
仕事の休憩時間に私が本を読んでいると、ベテランパートスタッフの女性がそう言った。すると、周りにいたパートの女性陣が「わたしもよ」「夫が何もしないから、仕事終わって家帰って家事こなしてたら、自分の時間なんてないわよねぇ」と続いた。
その後はひたすら家庭の愚痴を聞き続けたっけなぁ、と数年前の出来事を思い出しているのは、私にも子どもが生まれ「こりゃ本なんか読んでる時間ねえわ」と実感しているからだ。
「クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書」なんてタイトルで本を紹介するコラムを書き、読書を通じてこのクソみたいな世界に抗いたい、なんて野望を抱く読書狂の私も、労働を終えて家に帰り、子どもを寝かしつけて家事を済ませた後に本を開いたら3分で寝落ちする。
とは言え、本を読まないとこの原稿も書けないので、私は妻に子守りを託し、一冊の本を携えて近所のファミレスに来た。さて、集中して本を読むぞと思って頁を開くと、隣の席からこんな会話が聞こえてくる。
「とりあえず、オルカン?」
「エスアンドピー500?ってやつにしとけばいいっぽいよ」
おそらくIDECOか新NISAでも始めるのだろう。郊外のファミレスで若くていかつい兄ちゃんが資産運用の話をする時代かぁ、と考え込んでいると、向かいの席にいる老夫婦の元に店長らしき若い男性が来て、何やら話し込んでいる。
今度はそっちに耳を傾けると、どうやらお爺さんがトイレに行った際に間に合わず糞尿を漏らしてしまい、それが店内を汚してしまったこと、そしてそれは今回が初めてではなく、先週にも同じ出来事があったことを告げていた。お爺さんは自分が漏らしたことを気づいていない様子だ。
「オムツを着けて来店していただくか、お手洗いに行く際は誰かが同行して介助をしてもらえなければ、今後の入店はお断りせざるを得ない」
若い店長はとても丁寧に老夫婦に説明していた。お婆さんは納得したようで「もう来れないわね」と言い、二人は店を後にした。
猫型配膳ロボットが通り過ぎる傍らで、店長は汚れた床を掃除していた。
私は本を読むことを忘れ、しばらく考え込んでしまった。
労働と育児で疲弊する私、投資をしなければ資産形成できない若者、ファミレスから追い出される老夫婦、残された糞尿の始末をするファミレス店長。それぞれに生きづらさや困難があり、それが「自助努力」「自己責任」で片付けられてしまうのが新自由主義的思想が蔓延る現代の資本主義社会だ。
思考がうずまき、なかなか本を読み進めることができず、それでも気持ちを切り替えて持参した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読み進めて思ったのは、やっぱりこの社会はクソだよなということだ。
著者の三宅香帆は、本書のまえがきでこう綴る。
「労働と文化の両立の困難に、みんなが悩んでいる。その根底には、日本の働き方の問題があります。(中略)現代の労働は、労働以外の時間を犠牲にすることで成立している。」(P.20ーP.21)
ここでいう「文化」とは、本を読むことだけではなく、労働と両立させたいこと全般を指す。映画を観ることや音楽を作ること、絵を描くことといった文化的な趣味はもちろん、家族と過ごす時間や、育児、介護といったケアの時間も含まれてくる。
確かに、労働と何かを両立させることは困難だ。まず、労働だけで疲弊する。週5日8時間+残業で時間と体力がだいぶ奪われる。余暇の時間は、横になってスマホばかり見てしまう。そんな状態に育児や介護が乗っかると「20年間一冊も本を読めない」状態になる。
「どういう働き方であれば、人間らしく、労働と文化を両立できるのか?」(P.23)
この命題に「労働と読書」という切り口から向き合う本書が見据えているのは、社会変革だ。なぜ労働と文化が両立できないのかを紐解いていけば、男は全力で働き、女が全力で育児家事をするという昭和の家父長制的価値観で形作られた日本の働き方がアップデートされないまま、そこに新自由主義的思想による競争の原理がインストールされ、自己責任と自己決定の名のもと自分で自分を搾取してしまう社会に仕上がっているからだ。
本書の最後に著者は、そんな社会を変えるためにある具体的な提言をする。
それは、私たちひとりひとりの考え方を変えることで、社会の風潮を変えていこうとする試みだ。本書の肝なので、その具体的な内容をここで引用することは避けるけど、私はその提言に激しく同意した。
クソみたいな社会を、クソな状態のまま次の世代に引き継ぐのも嫌なので、現役で働く自分達の世代が生き方、考え方を変えなければダメだよなぁ、と思った。自分だけが社会を生き抜こうとする術ではなく、若者から高齢者までみんなが安心して暮らせる社会を思い描きたい。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という読書家にとって魅惑的なタイトルでベストセラーになっている新書の中身は、新自由主義に抗い社会を変革しようとする姿勢に満ちたパンク的名著だった。
紹介書籍
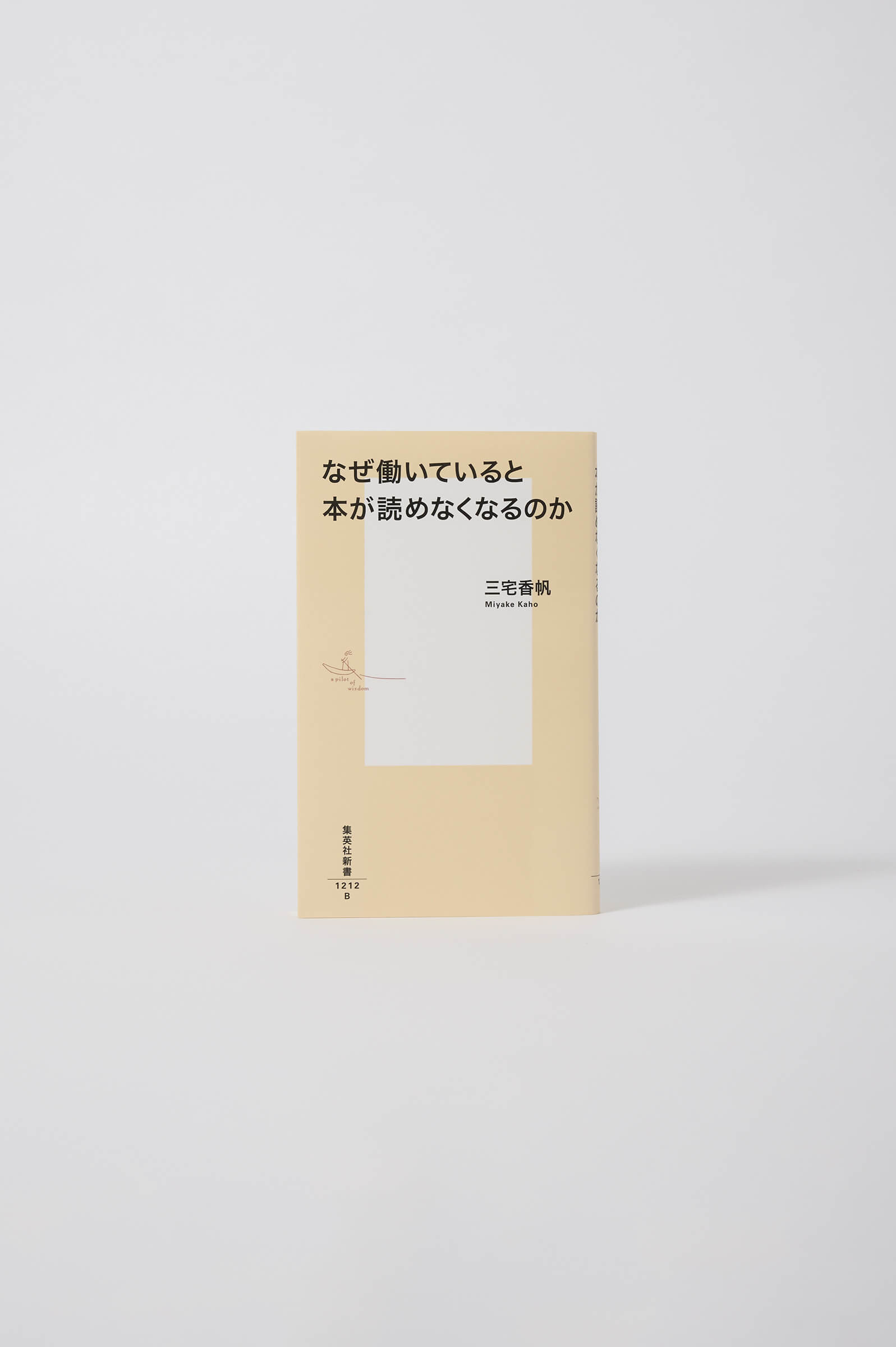
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
著:三宅香帆
出版社:集英社
発行年月:2024年4月
プロフィール
小野寺伝助
おのでら・でんすけ|1985年、北海道生まれ。会社員の傍ら、パンク・ハードコアバンドで音楽活動をしつつ、出版レーベル<地下BOOKS>を主宰。本連載は、自身の著書『クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書』をPOPEYE Web仕様で選書したもの。
関連記事
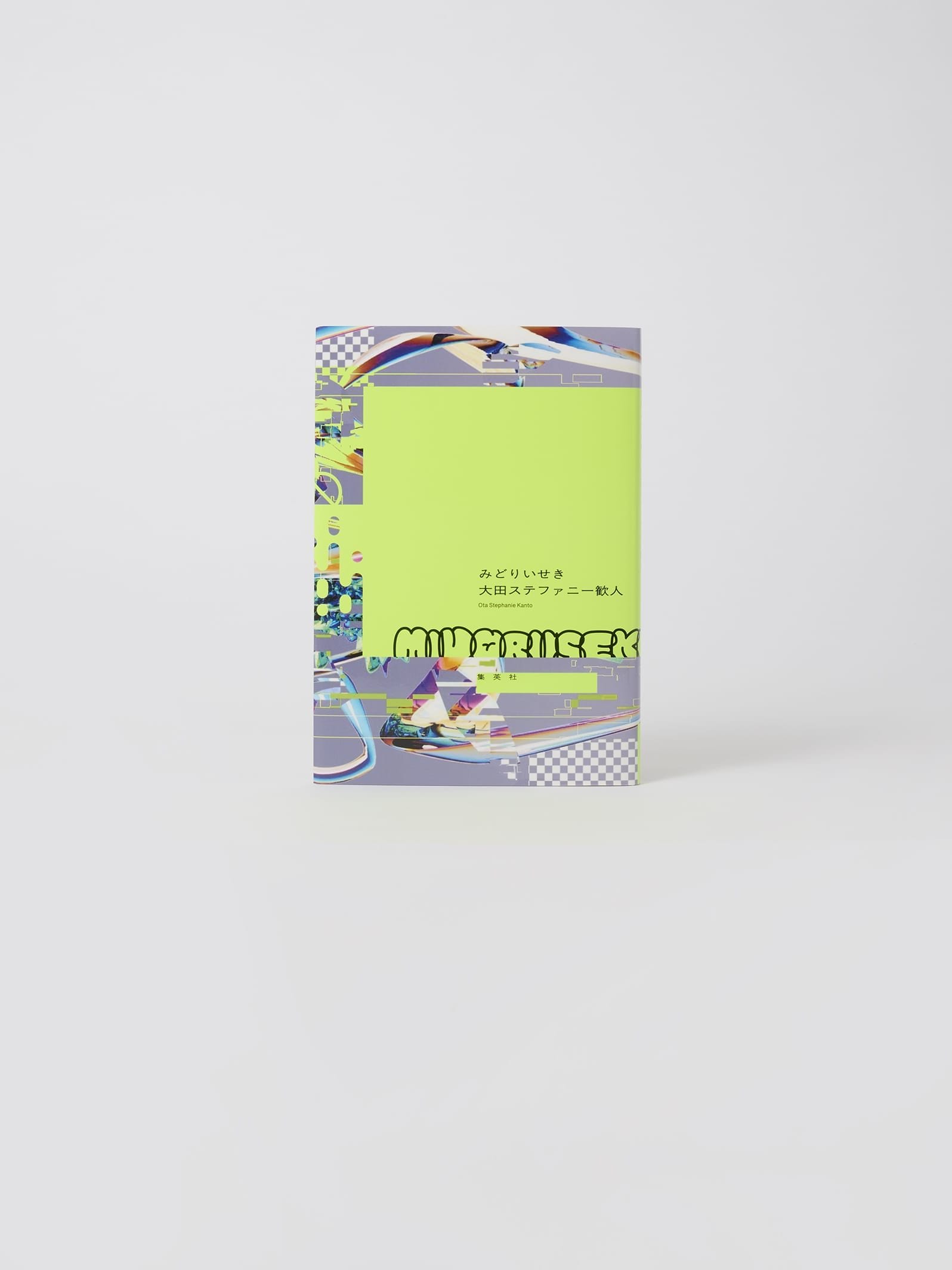
カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.22
紹介書籍『みどりいせき』
2024年4月15日
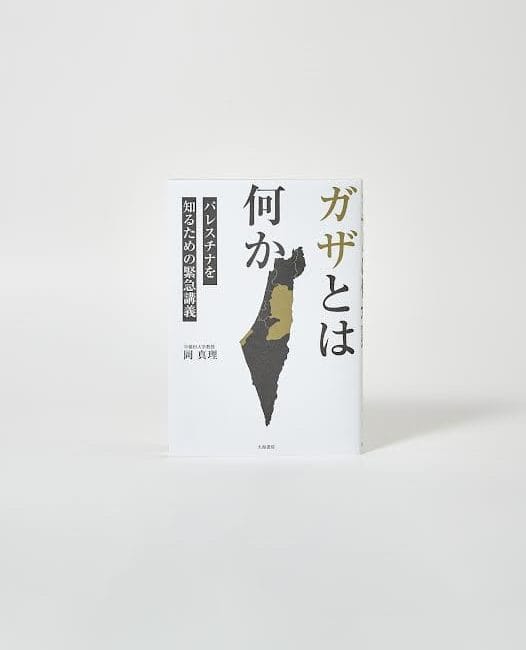
カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.21
紹介書籍『ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義』
2024年2月15日

カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.20
紹介書籍『東京ヒゴロ1~3巻』
2023年12月15日
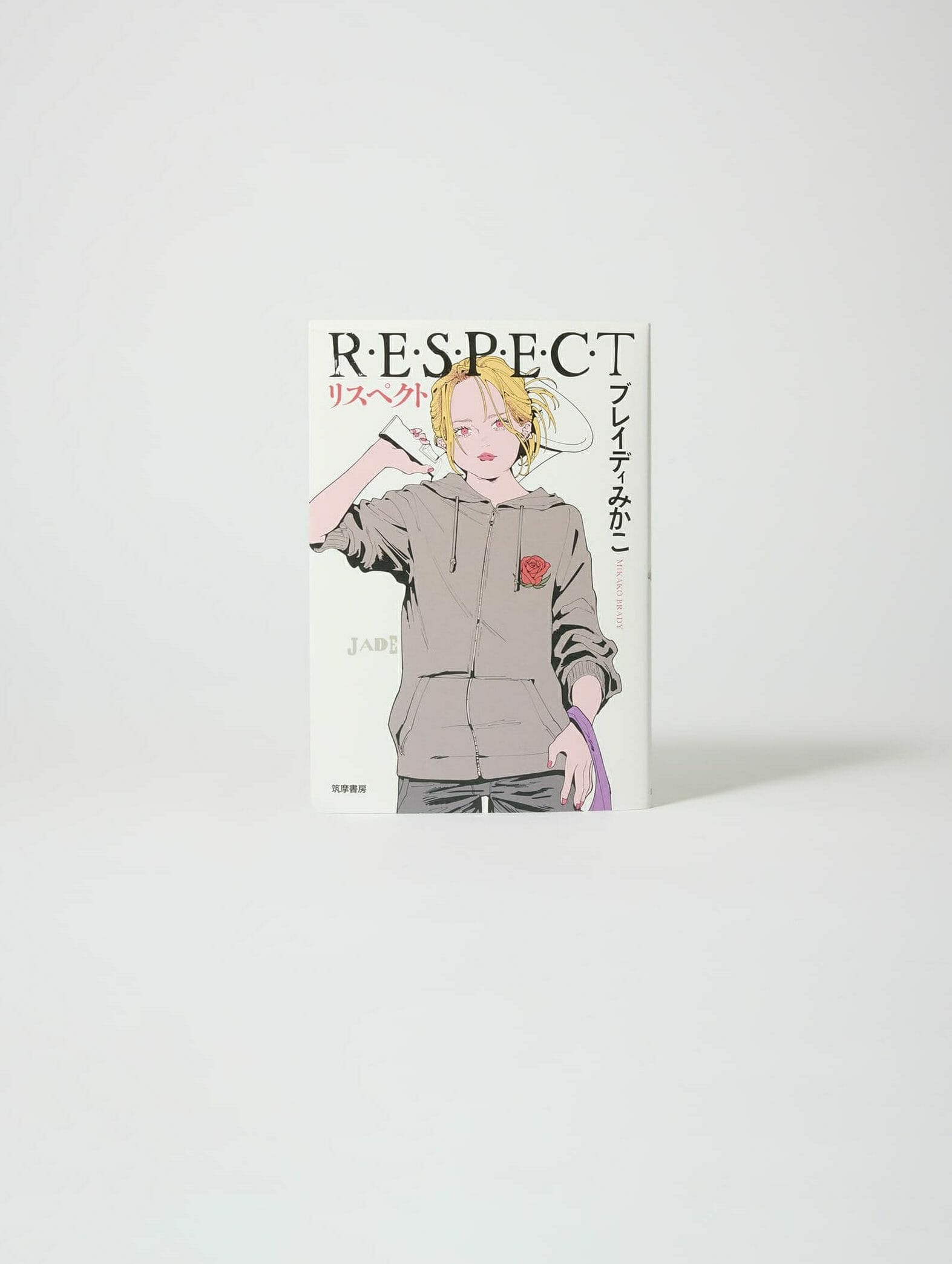
カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.19
紹介書籍『リスペクト ─R・E・S・P・E・C・T』
2023年10月15日
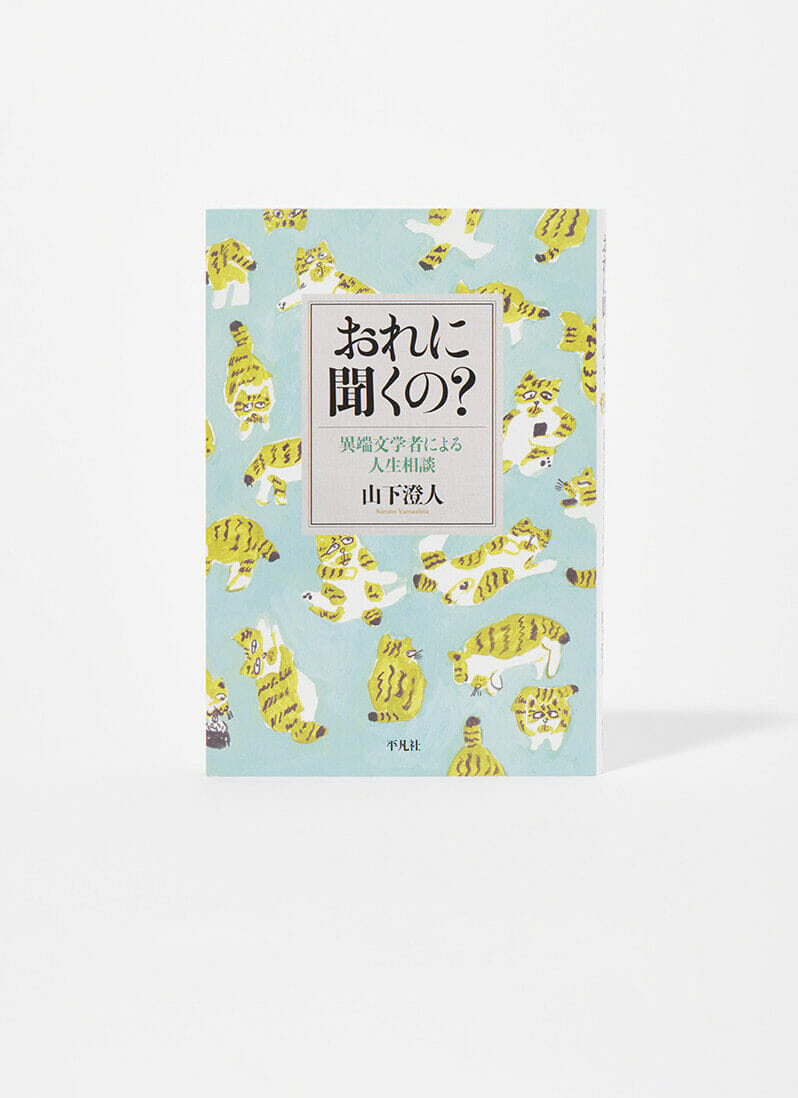
カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.18
紹介書籍『おれに聞くの? 異端文学者による人生相談』
2023年8月15日
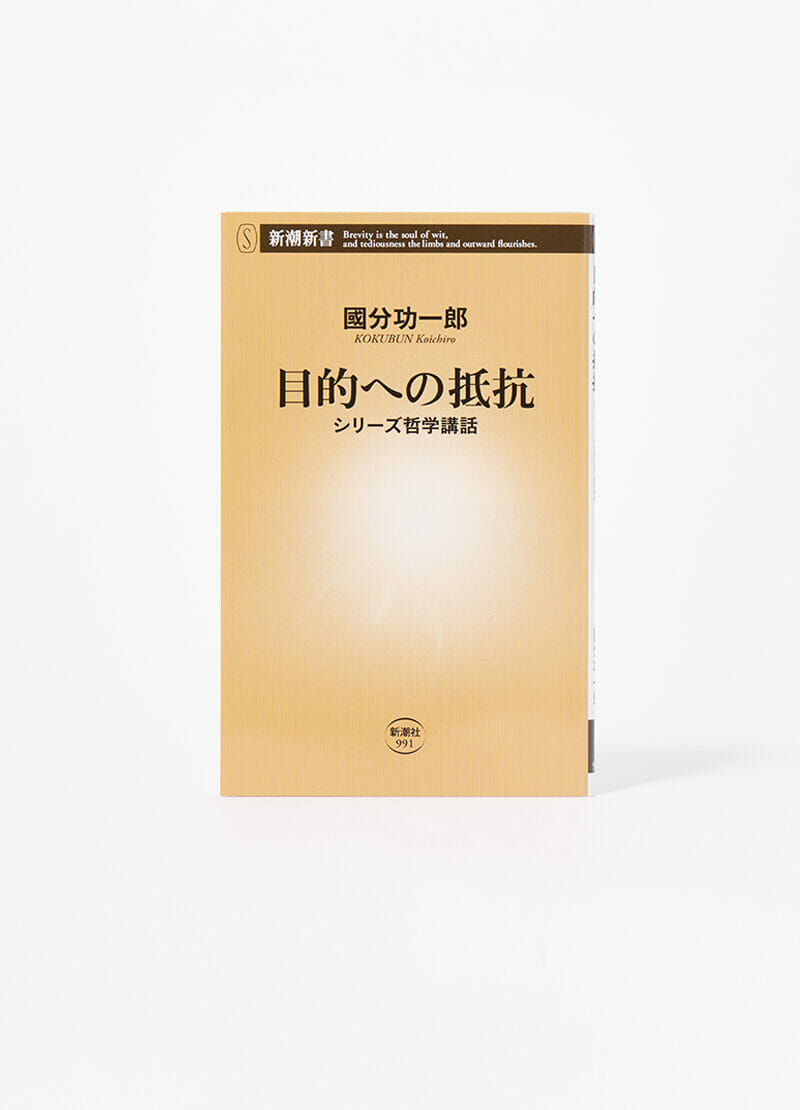
カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.17
紹介書籍『目的への抵抗』
2023年6月15日
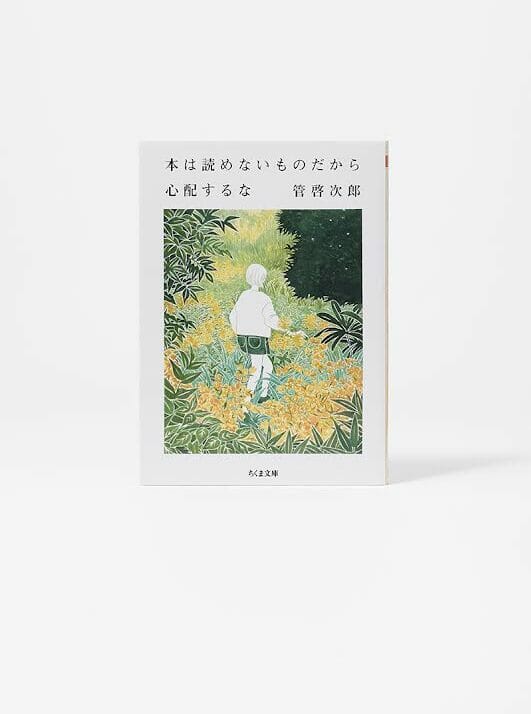
カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.16
紹介書籍『本は読めないものだから心配するな』
2023年4月26日
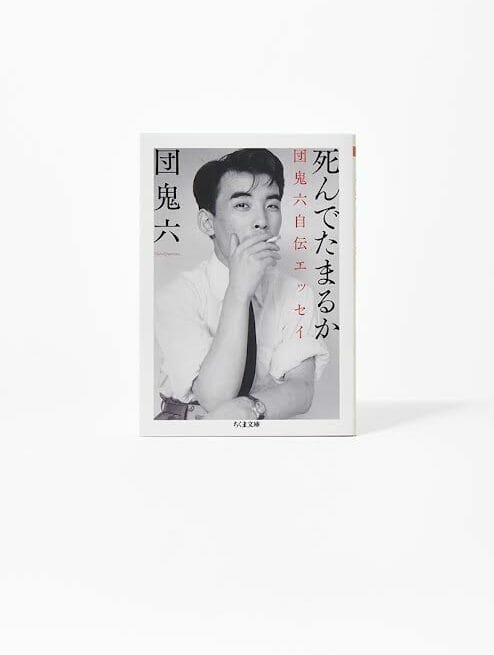
カルチャー
クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書。Vol.15
紹介書籍『死んでたまるか 団鬼六自伝エッセイ』
2023年3月15日


