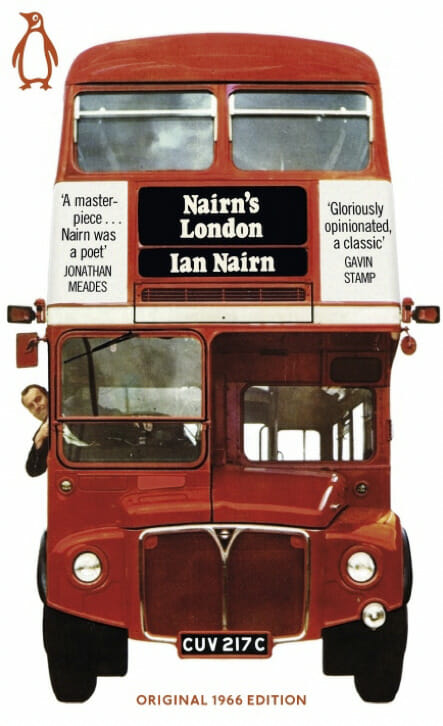カルチャー
僕の駆け出し時代/田原総一朗
2021年3月31日
illustration: Kazuma Mikami
text: Hiroaki Nagahata
2021年3月発売 『POPEYE特別編集 こんな仕事があったのか。』掲載
落ちこぼれのアシスタントはテレビのいい加減さを追い風に伝説を残す。

「カメラのバッテリー忘れましたって、何もできないじゃねえか!」
ある日の撮影現場。そこには、カメラマンに叱り飛ばされる新入りアシスタント。周りのスタッフは「またあいつか」と冷たい視線を彼に飛ばす。絶望的に仕事ができないその新人こそ、若き日の田原総一朗さんである。
「大学の頃はマスコミ志望で、片っ端からテレビ局を受けたものの全滅だった。最後に何とか引っかかったのが岩波映画製作所。カメラアシスタントの仕事を任されたんだけど、ミスばっかりしていてね。三脚のネジを緩めたときに誤ってカメラを落としたり、現場に必要なものを忘れたり。そんなんだから、1か月半でカメアシを降ろされてしまったんだ。ただね、僕は反省できない性格だから、あんまり深刻に考えなかった。会社に行ってもやることがないから、大した政治思想もないのに安保闘争に参加したりして暇を潰していたね(笑)。そんな状況を見かねたのか、会社の先輩が『たのしい科学』っていう番組で撮影アシスタントの仕事を振ってくれたんだ。しばらくそこを手伝っているうちに、今度は脚本の社内公募が回ってきたんで、当時流行していたポリオ(小児麻痺)の企画で応募してみた。それが何と採用されて、白金台の東京大学医科学研究所に保管されていたポリオウイルスの映像を撮影することになった。撮影当日、演出家が風邪で休んじゃって、仕方ないから自分が現場を仕切ったんだよ。よせばいいのに、個人的に好きだったヌーベルバーグの手法にならって、手持ちのカメラでグラグラの映像を撮った。演出家にそれを見せたら案の定『こんな絵で放送できるか!』と怒られ、プロデューサーにも再撮影の費用を出してもらえなかった。『せっかく先輩からもらったチャンスを台無しにするなんて、やっぱりおれはダメだ』と思い、勢いで辞表まで書いたんだ。ところが、同期から『辞める前に、自分で編集したらどうだ』とアドバイスされたので、アラン・レネが撮った『世界の全ての記憶』というドキュメンタリーの構成を完全に真似して編集してみた。そしたら、あんなに怒っていたプロデューサーがそれを観て『放送しよう!』と。しかも、この番組がテレビの賞まで取った。こうして、カメアシも満足にできない男が、演出家として独り立ちしたわけです」
しばらくして、今度は「NETテレビ」(現・テレビ朝日)のディレクターにある番組の構成を依頼される。
「最初の打ち合わせがあった日の夜に急いで脚本を書いて、その2日後には撮影だと言われた。岩波時代は何度も脚本を練りなおすのが普通だったから、まさか修正ナシとは予想もしていなかったし、そもそもこんなにめちゃくちゃなスケジュールがあるのかと驚いた。でも、そのテレビの“いい加減さ”が素晴らしいと思ってね。自分の性には合っていた。それがきっかけになって、開局したばかりだった『東京12チャンネル』(現・テレビ東京)に入社したんだ。当時はまだインディー局で、制作費が大手の5分の1くらいしかなかったから、同じ土俵で闘うことができず、奇抜なことや過激なことばかりやっていたよ」
その後、田原さんは言葉どおり、今では深夜でも放送できないような内容の番組をゴールデンで流すなど、演出家としての伝説をいくつも残した。
「周りが自由にやらせてくれたから、それは感謝している。演出家として新人時代を過ごした『東京12チャンネル』は、今でも心の故郷だね」
プロフィール
田原総一朗
発売中!
POPEYE特別編集 こんな仕事があったのか。
ポパイが過去に話を聞いてきた、74人分の仕事についての取材&インタビューを一冊に再編集。
どのようにその仕事に出会ったのか、実際に就いてみてどうだったのか。進路に悩む人、就活に悩む人、いまの仕事がしっくきてない人。すべてに届く実録集です。東京で働く若者はもちろん、日本各地、そして、ロンドン、パリ、LA、ベルリン、メルボルンなど海外の若き職人取材も。