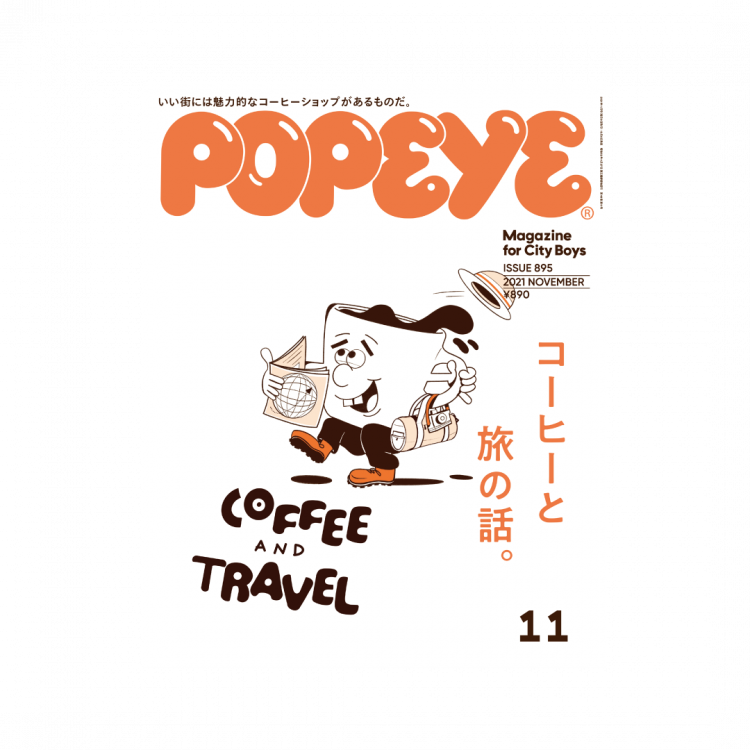カルチャー
実現したカウボーイの旅/文・椎名誠
2021年10月20日
旅とは何かということについて思うところを書いていこう。ぼくの旅は子供の頃から青年期にかけて読んだ本や見た映画などに影響されたものが多い。誰に頼まれたわけでもないのに砂漠や無人島などをめざしてわざわざ苦労しに行くゴクロウサマな日々をずいぶん送ったものだ。
まあ冒険、探検ごっこだ。
その夢の舞台を外国に求めるようになってくると、そこで体験したことなどを本に書いてけっこう読者によろこばれたりした。
『わしらは怪しい探険隊』などはシリーズになって永く続き、今は〝怪しい雑魚釣り隊〟と看板をやや大人らしくさせてまだ続いている。
それらのおびただしいガラクタ旅の軌跡の一覧を眺めていて「ああ、若い頃はあんな旅をしたんだ!」と我ながら少々あきれつつ、けっこう感動もした思い出があった。
その中でたぶん日本人としてはあまり似たような旅をしたことがないのではないか、と思うものがいくつかあるのでこんな機会に思い出話を語らせていただきたい。
カウボーイの旅である。
青年期の頃、テレビのシリーズものでよく見ていた。十数人のカウボーイたちが数百頭の牛を移動させていく物語である。主役は若い頃のクリント・イーストウッドだった。毎日の荒っぽい牛追い旅のあと、夜は焚火を囲んでウイスキーをのみ、遠くでおびただしい牛の群れが鳴いている。そんな光景をうっとり眺めていたものだ。
現代のその牛追い旅を体験した日々があるのだ。場所はブラジルのパンタナール。世界最大の湿原だ。アメリカの牛の移動はトラックでやるようになってしまい、カウボーイはいなくなってしまったが、そこではまだ西部劇みたいに馬に乗った十数人の男たちが沢山の牛を移動させる仕事をしている。
そのひとつの牧場に下働きのカウボーイとして雇われた。
ブラジルではカウボーイのことを「ピオン」と呼ぶ。それぞれ馬に乗りムチと投げ縄を持ち480頭の牛を追い、荒野を野営しながら移動していく。
ぼくはそのピオンの一員として雇われた。
言葉はポルトガル語なのでなんだかわからない。でも11人の仲間と牛の群れを囲み、草原の濃い藪や疎林にすぐ逃げ込もうとする牛を追っていって本隊に戻す、という自分らの役目はすぐにわかった。雇用の試験というのは特にないが、基本は馬を自在に乗りこなせることだった。これは当たり前のことでセールスマンが言葉をしゃべれるかどうか、というようなものだ。ぼくは永い間の世界各国の旅で絶対必要なのは馬を自在に乗りこなす、ということだったのでこれは自信があった。
ネッカチーフをまきテンガロンハットをかぶる。22口径の拳銃を持ち、使いこなせるのなら長さ4メートルほどの革のムチを持てる。拳銃は落馬して、足がアブミから外れず引きずられたときに馬を撃つため、と聞いたが、拳銃を扱い慣れていない者にはあまり実用的な話じゃない。かえって暴発して自分を痛めてしまいそうだからぼくは持たないことにした。
なんだかよくわからないうちに砂ボコリの中、出発した。我々より1時間ぐらい前に2頭のロバにいろんな道具をしばりつけたじいさんが出発した。今日の昼めし、夕めしを食べるところで食事を作って待っているのだという。アメリカのカウボーイ物語『ローハイド』にもまったく同じ役割の人が出てきた。
480頭の牛が一斉に出発する砂ボコリがすさまじい。テレビや映画で見ていたカウボーイらがみんなネッカチーフをしている理由がわかった。あれはおしゃれなんかではなく砂ボコリだらけになったときに素早く鼻や口を覆うためだとわかった。水筒など持っていても激しい動きですぐ飛んでしまうので、けっこうあちこちで出くわす幅5メートルぐらいの小さな川を渡るときに馬の上から帽子を水の中に入れてツバを持って汲みあげ、それで水をのむ。残った水ごと頭からかぶる。いろんなことがわかってくる。
やがてちょっとした林の中で、ロバのじいさんがピラニア(渡ってきた川にけっこういる)のカラアゲとパンの昼めしを作って待っていた。
ここで30分の昼休み。すでに足がガニマタ化していてうまく歩けない。
多くのピオンは昼めしを食うとそこらの日陰でつかの間のヒルネで体を休めている。カウボーイというのは思った以上の重労働なのだった。
午后は同じことのくりかえしだ。
あてがわれた馬との相性もできてきて、2~3メートルの距離でくるくる方向転換することも自在になってきた。
午后の難所は幅30メートルぐらいのピラニアがうんざりいる川を渡ることだった。牛たちは本能的に危険がわかるらしくなかなか渡ろうとしない。ピオンたちは銃やムチで脅し、それを渡らせようとする。うまくいかない時は一番年寄りのへたばった牛をイケニエのように川に流しピラニアをそこに集中させてその隙に本隊が渡るのだという。
夕暮れ近くになると牛に草を食わせ人間たちも夕食になり、そのままその日のキャンプになる。焚火にウイスキーなどというのはまったくなく、何よりもみんな疲れているのでめしを食うとそのまま地べたにころがって寝てしまう。ぼくの足は昼よりさらにガニマタ化して硬直し、まともに歩けなくなっていた。翌日も同じような一日だった。青年時代に抱いていた夢はどんどん遠のいていった。
プロフィール
椎名 誠
しいな・まこと|1944年、東京都生まれ。東京写真大学中退後、百貨店専門誌の制作会社に勤務。その後、同僚らと書評誌『本の雑誌』創刊。書評を皮切りに執筆活動を始め、『さらば国分寺書店のオババ』でデビュー。吉川英治文学新人賞、日本SF大賞受賞。『インドでわしも考えた』『零下59度の旅』など旅エッセーにもファンが多い。
関連記事

COFFEE AND TRAVEL
NO.895
2021年10月8日

カルチャー
あの人がメキシコへ向かう理由。/きゃりーぱみゅぱみゅ
原宿からメキシコへ。雑貨が世界を広げる。
2021年5月2日

カルチャー
あの人がメキシコへ向かう理由。/中原慎一郎
蒸留酒万歳! 現地で飲んでみてわかったメスカルの引力。
2021年5月5日

ライフスタイル
芦沢一洋さんとアーバン・アウトドア・ライフ。
2021年9月27日

トリップ
手の旅のはじまり。
写真・文 坂口恭平
2021年7月7日

カルチャー
伝承あやとりを取ってみる。
2021年4月11日

フード
今日は「さぼうる」、明日「トレヴィ」。
2日で巡る、2軒の異国。
2021年7月12日