カルチャー
寺尾紗穂は『少年』を観て戦後日本に残る戦争の爪痕に思いを馳せた。
今日はこんな映画を観ようかな。vol.9
2026年2月18日
illustration: Dean Aizawa
text: Keisuke Kagiwada
毎週、1人のゲストがオリジナリティ溢れる視点を通して、好きな映画について語り明かす連載企画「今日はこんな映画を観ようかな。」。今回のゲストは、シンガーソングライターとして活動する傍ら、最近は文筆家として『日本人が移民だったころ』なども発表した寺尾紗穂さん。紹介してくれたのは、”松竹ヌーベルヴァーグ”を牽引した大島渚監督の初期作『少年』だ。
今日の映画
『少年』(大島渚監督、1969年)
当たり屋をしながら生活費を稼ぐ4人家族が日本を横断していく姿を、長男である”少年”の目を通して描くロードムービー。1966年に実際に発生した、当たり屋一家事件がベースになっている。
2024年に公開の『マミー』という和歌山カレー事件の家族を描いたドキュメンタリー映画を見たときに印象的だったのが、林眞須美容疑者の地元の人々が一様に事件の話を避けたがる様子でした。わかる気もするけれど、違和感が残った。眞須美の夫は、自らヒ素を飲んで保険金をもらう詐欺を繰り返していた、という普通ではない人物なんですが、実は近所の仲間たちもそれに倣って保険金のために眞須美に少量のヒ素を盛ってもらっていたということが監督の取材でわかります。
お金のために体を危険にさらして詐欺をする。今の常識から考えると理解されない。結果眞須美は普段から毒を盛っていたモンスターで、犯人に間違いないという見立てが広まりました。冤罪の可能性は今も残っています。驚いたのは1990年代の田舎町で、そうした危険を伴う詐欺への抵抗がない人たちが一定数いたことでした。近隣住民が黙して語らない背景に、ヒ素の詐欺に関わった人が林夫妻だけでなく複数いたことも関係しているのかも、と気づかされました。
思い出したのは大島渚監督の『少年』でした。1960年代に起きた「当たり屋」一家の詐欺事件を描いた作品です。
傷痍軍人で糖尿病も患う父親が、息子を車に当たらせて、示談金で生計を立てていきます。一家は高知から転々と稚内の岬まで行くのですが、そこで樺太の方向をみて少年が「日本がもっと広いといいになあ」と言うんです。そしたらもっと当たり屋でお金が稼げる。何気ない一言ですが、戦争中は樺太も満州も朝鮮も台湾も南洋も日本の領土だったこと、それを失った現在が一家のどん詰まり感と共に描かれる重要なシーンです。
戦前から戦時中にかけては土地をもらえた長男と違って次男以下の男性は、国内の余剰労働力として開拓や植民地へ、そして戦地へと送り出されました。戦後狭い日本に戻ってきても土地はなく生活は苦しい。『少年』の父親もまた6人兄弟の3男でした。戦後満足に働ける身体でもなく、息子を危険にさらす「当たり屋」生活へと入っていくのです。日本の戦後が思われているよりもずっと長く、戦争の爪痕と共に貧困を引きずっていたこと、その中で今の価値観では理解しきれない事象が起きていたことを感じさせられた映画体験でした。
語ってくれた人

寺尾紗穂
てらお・さほ|1981年、東京都生まれ。東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。2006年にシンガーソングライターとしてミニアルバム『愛し、日々』をリリース。07年にアルバム『御身』でメジャーデビュー。文筆家としても活躍中。著書に『原発労働者』『南洋と私』『あのころのパラオをさがして 日本統治下の南洋を生きた人々』など。最新著は『日本人が移民だったころ』。
Official Website
https://www.sahoterao.com/
関連記事

カルチャー
ドンデコルテ渡辺は、『ノロイ』で恐怖演出の真骨頂を味わった。
今日はこんな映画を観ようかな。vol.8
2026年2月11日

カルチャー
シム・ウンギョンは『プレイタイム』で魔法のような映画体験をした。
今日はこんな映画を観ようかな。vol.7
2026年2月4日

カルチャー
芸人の鳥居みゆきが、「自分が自分じゃないかも」って疑いたくなるときに観る映画。
今日はこんな映画を観ようかな。Vol.6
2023年10月31日

カルチャー
精神科医の斎藤環が、もう一度観たい未ソフト化映画。
今日はこんな映画を観ようかな。Vol.5
2023年7月27日
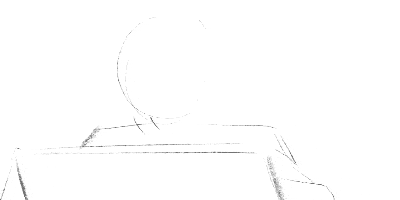
カルチャー
劇団・東葛スポーツを主宰する金山寿甲が、高騰するヴィンテージTシャツを見て懐かしんだ90年代映画。
今日はこんな映画を観ようかな。Vol.4
2023年6月28日

カルチャー
映像作家の倉知朋之介が、キメ顔や大袈裟な仕草に影響を受けた映画。
今日はこんな映画を観ようかな。Vol.3
2023年5月28日

カルチャー
小説家の小川哲が、映像ならではの表現に感動したSF映画。
今日はこんな映画を観ようかな。Vol.2
2023年4月27日

カルチャー
女優の長澤まさみが「こんなシーンを演じてみたいなぁ」と思った映画。
今日はこんな映画を観ようかな。Vol.1
2023年3月31日
ピックアップ

PROMOTION
雨の日のデーゲーム
POLO RALPH LAUREN
2026年3月10日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
Gramicci Spring & Summer 26 Collection
Gramicci
2026年3月10日

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日

