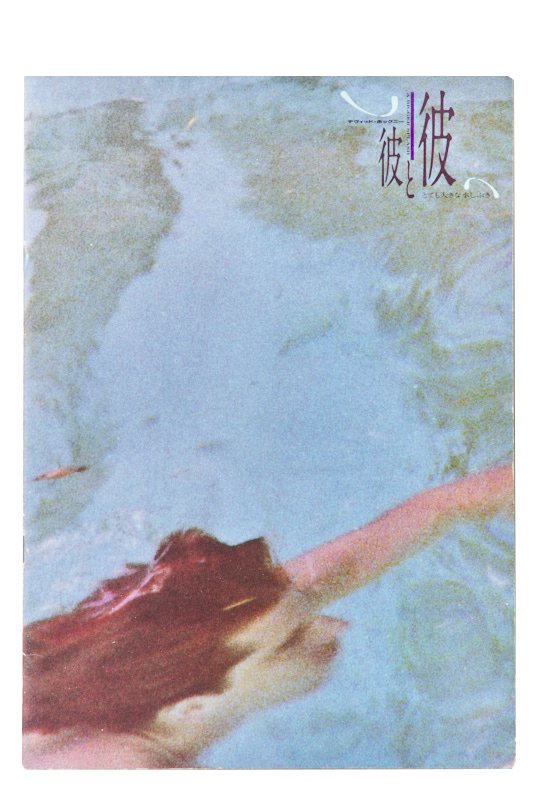カルチャー
ホックニー・プレイズ・ホックニー。
D・ホックニーが「主演」した、不思議な“半”ドキュメンタリー映画。
photo: Wataru Kitao(VHS, Pamphlet), Hiroshi Nakamura(Magazine)
text: Kosuke Ide
edit: Yu Kokubu
2024年6月7日

あの「代表作」の裏側にあった、愛と彷徨の記録。
スティングの名曲『イングリッシュマン・イン・NY』に倣って言えば、『イングリッシュマン・イン・LA』だろうか。と言っても、謙虚さや礼節を重んじない大都会の空気にちらりと違和感を覗かせたスティング(が友人のために書いた歌らしいが)とは違って、デイヴィッド・ホックニーにはアメリカ西海岸の青空を吹き抜ける乾いた風がしっくり来たのに違いない。
イギリスの田舎町でつつましく暮らす美術好きの父と母のもとで育ち、街角の看板やポスターに美しい文字やイラストを描き込む職人たちの姿に見惚れたホックニー少年は、ほとばしる情動を筆に滴らせ続けた画狂人ピカソを敬愛した。しかつめらしい抽象表現主義が幅を効かせていた1960年代初頭から具象表現にこだわり続けた彼は、’64年にロンドンからロサンゼルスに移住した後も、「描きたいものを描くんだ」とばかりに自らの日常の断片を次々とモチーフにしていった。ビバリーヒルズの風景、プールサイド、花、愛犬、そして友人ら愛する人たちの肖像……。比較的新しい素材だったアクリル絵具やクレヨンなどで描かれたそれらの作品群は、絵画ともイラストレーションともつかぬ、というかそうしたカテゴライズをすべて跳ね除けてしまうかのような、率直でセクシャルで、みずみずしいパワーに満ちている。
1980年代の初め頃から始めた、被写体に対して少しずつ視点をずらして撮影した数十枚のスナップ写真を繋ぎあわせて作る「ジョイナー・フォト」と呼ばれるフォト・コラージュ作品のアイデアも、「絵を描くように写真を撮ることはできないだろうか?」という彼のシンプルな疑問と遊び心から生まれたものだ。
そんなホックニーの代表作として知られる絵画のひとつが、1972年の作品『芸術家の肖像―プールと2人の人物―〈Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)〉』だ。プールサイドに佇んで水面を見下ろすジャケット姿の男と潜水して泳ぐ人物を描いたこの作品は2018年、ニューヨークでオークションにかけられ、存命の画家の作品としては過去最高の9,030万ドルで落札された。

『Pictures by DAVID HOCKNEY 』(Harry N.Abrams/1979) 表紙に「芸術家の肖像―プールと2人の人物―」を使用した、詩人で編集者のNikos Stangosのセレクト・解説による作品集。
実はこの作品の制作の裏側を描いた映画が存在する。’74年にジャック・ハザン監督により制作された『彼と彼 とても大きな水しぶき(A BIGGER SPLASH)』は、当時のホックニーと友人、関係者たちが出演して自ら「本人役」を務め、「リアルライフ」を演じて見せた “半”ドキュメンタリー作品だ。

『彼と彼 とても大きな水しぶき』
原題:A Bigger Splash
1974年/105分/イギリス
原題の「A Bigger Splash」は1967にホックニーが制作した絵画作品のタイトルでもある。彼独特の特殊なリトグラフの技法「ペーパー・プール」による作品の制作過程から、日常生活のシーンまで、貴重すぎる記録。本作は2019年にニューヨークのミニシアター「Metrograph」で本作の4Kデジタル修復版が上映された。©︎Collection Christophel/アフロ
舞台は’70年代初頭のロンドン。30歳過ぎにしてアート界のスーパースターになっていたホックニーだが、ゲイである彼はパートナーの画家ピーター・シュレシンガーに去られ、心に大きな痛手を負っている。行き場のない寂しさに苦しみながら、孤独なアトリエで、ホックニーは別れた恋人の巨大な肖像画に取り組んでいるが、やはりその筆は重く、制作は一向に進まない。
そんな彼の姿を見かねたニューヨークの芸術家仲間からロンドンを忘れてアメリカに来るように勧められ、ホックニーの心は揺らいでいる。失恋の哀しみから精神的に追い詰められた彼はついに、数ヶ月を費やして描いた肖像画をナイフで切り裂いてしまう。そんな画家の姿をずっとそばで見ていたボーイフレンドのモー・マクダーモットは、彼に再び絵筆を持つよう働きかけ、自らモデルの代役を務める。ホックニーは傷ついた心を抱えながら、再起を期して新たなシュレシンガーの肖像画に取りかかり始めた。別れた彼を再び呼び寄せてポーズをとらせ、プール・サイドに佇むその姿を描いていく……。
こうした物語においてホックニーが自ら“ホックニー役”を演じる本作では、ドキュメンタリーとフィクションの境界が曖昧にされている(例えば展覧会のオープニングパーティーのシーンは、実際に開催されたパーティーの現場で撮影している)。撮影は’71年夏から2年半にわたって行われ、ホックニーの友人、仕事仲間、ボーイフレンドらも多数“出演”している。
ホックニーがシュレシンガーとかつて恋仲にあったこと、そして撮影時にはすでに別れていたことは事実であり、また作品制作にまつわるエピソードも史実に限りなく近い。元恋人のシュレシンガーに頼み込んでモデルを務めてもらったという経緯も、事実だとホックニーが認めている。
しかし、すべてが真実というわけではない。撮影は物語上の時系列とは異なる順番で行われ、出演者にはストーリーラインさえも知らされていなかったというから、結果的にその内容の多くは監督の演出による産物=「ほぼフィクション」と考えるのが妥当なのだろう。
先鋭的でチャレンジングな手法によって完成したこの映画に公開当時の観客たちは当惑したのか、特にアメリカでの反応は芳しくないものだったようだ。その理由のひとつとして、当時の同国においてまだ同性愛の存在が広く受け入れられていなかったことを監督自身が振り返っている。
どうやらホックニー自身もまた映画の出来には満足しなかったらしく、一時はフィルムネガを買い取って「お蔵入り」にしようとまでしたこともあったという。しかしそれでも、この作品には若くエネルギーに溢れた一人の画家と彼を取り巻いていた人々のリアルな佇まい、表情、声、しぐさ――が独特の映像美とともに克明に記録されており、その生々しいヴァイブスが忘れがたい魅力を放っている。
肌に灼けるように降り注ぐ陽光、きらきらと波紋を描く真っ青な水面、時間が静止したような、ある夏の夢みたいなワンシーン。眩しいほどに明るくのびのびとしていながら、同時に狂おしいほどの哀愁が漂う。そこに、アーティストとそれを取り巻く人々の愛憎や葛藤、一度きりの人生の儚いハイライトが刻み込まれているかのように。ホックニーの絵画の美しさと切なさが生まれるその瞬間が、この映画には真空パックのように保存されている。DVD化もされず、今やほとんど「幻」となってしまった本作が再び公開される日を待ち望んでいる。
文・井出幸亮
関連記事

カルチャー
スーザン・ケアを知ってるかい?
初代Macのアイコンを生んだ伝説のデザイナーの仕事。
2021年6月16日

カルチャー
50 Questions with Tadanori Yokoo
2021年5月31日
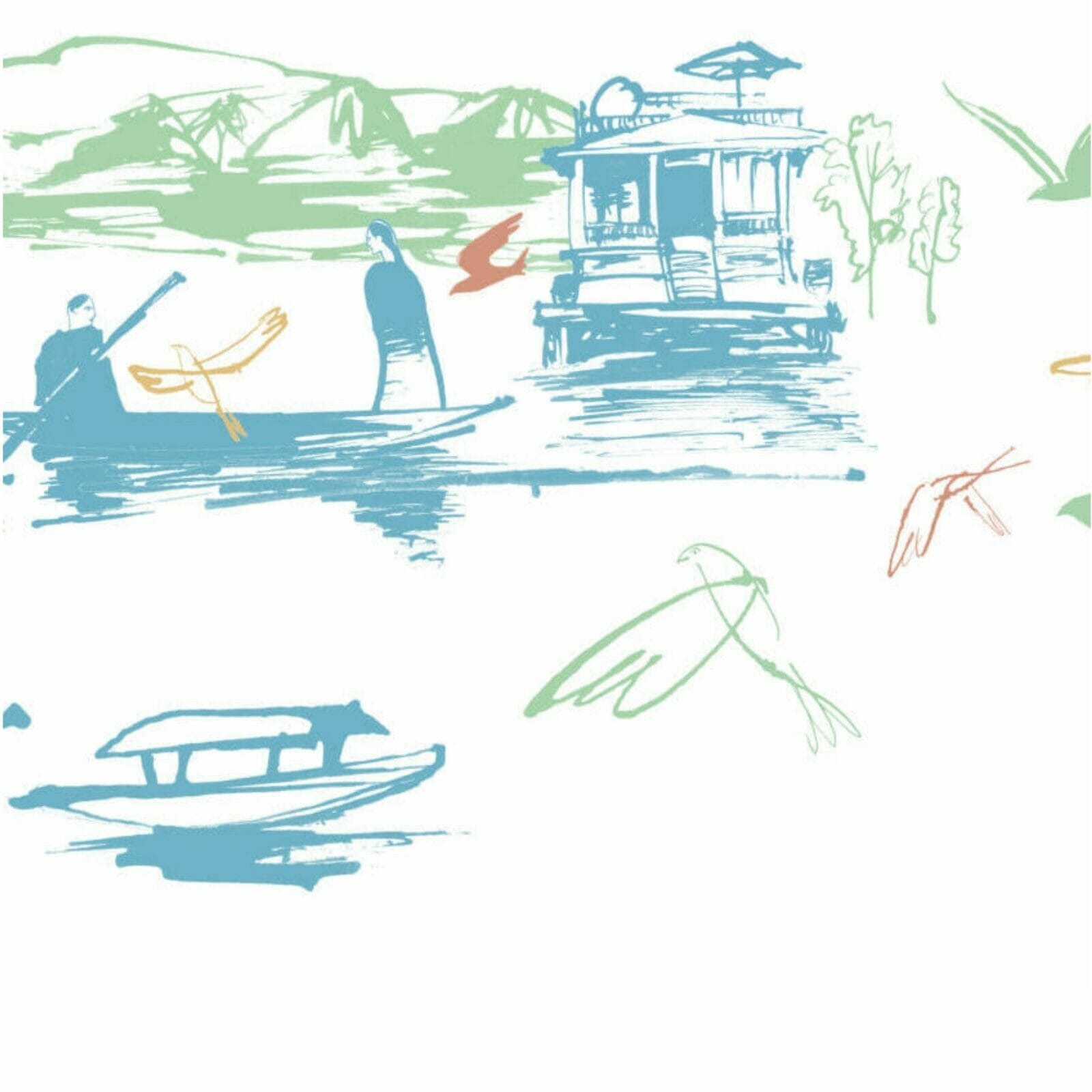
カルチャー
インドに行ける者といけない者/文・横尾忠則
2021年10月28日

カルチャー
子どものままで、いつまでも芸術を愛することができれば、それは幸せなことなのです。
国立新美術館「蔡國強 宇宙遊 ―〈原初火球〉から始まる」を開催中の蔡國強さんにメールインタビュー!
2023年8月17日

カルチャー
アートとスケートボード、ひいては宗教まで同じなのだとトム・サックスは言う。
TOM SACHS & SKATE
2023年8月24日