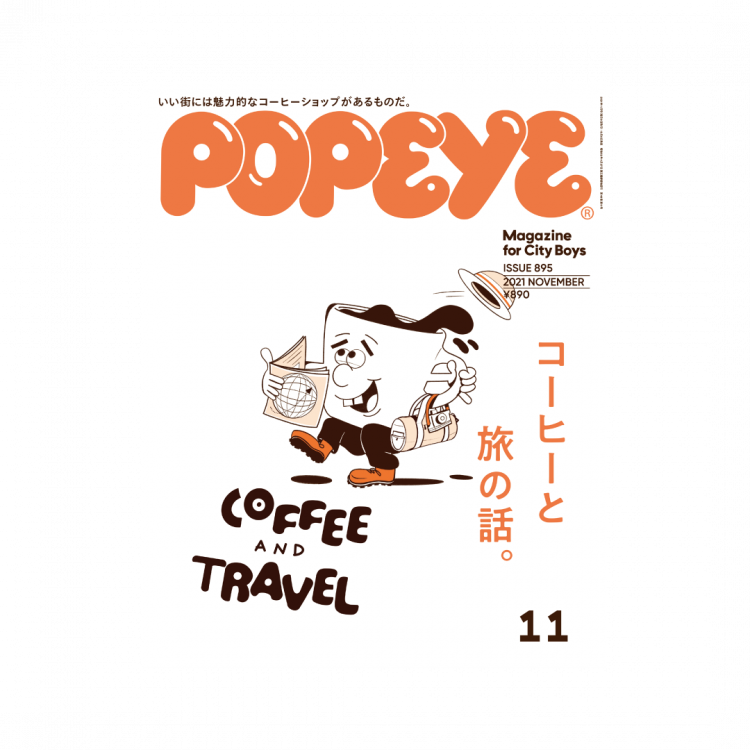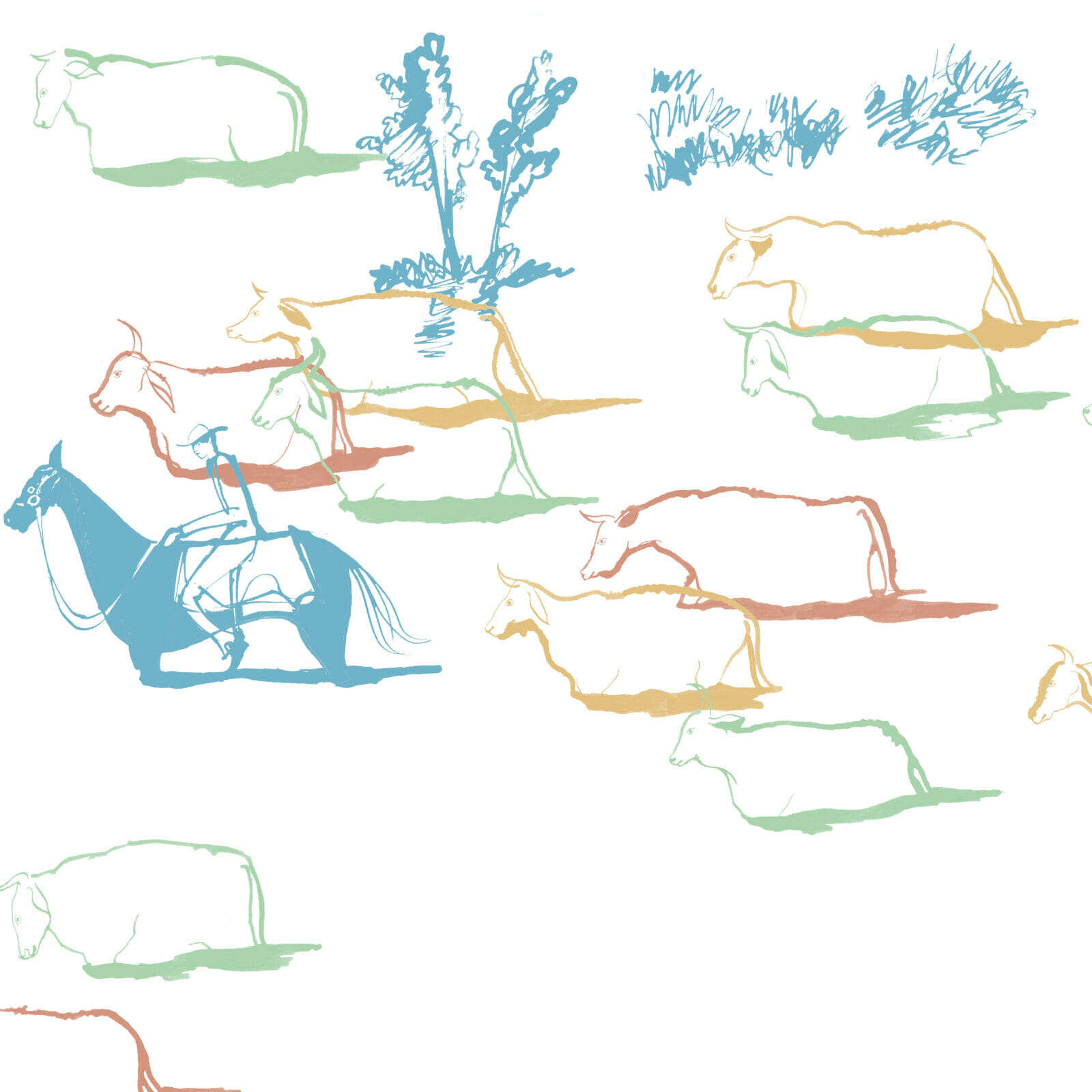カルチャー
インドに行ける者といけない者/文・横尾忠則
2021年10月28日
三島由紀夫さんの死の三日前の電話で三島さんはこんなことを言った。
「インドには行ける者と行けない者がいるけれど、君はそろそろインドに行けるんじゃないかな」
三島由紀夫が被写体になって、細江英公が撮った写真集『新輯版 薔薇刑』に、僕はオダリスク(*1)風の裸像の三島がヒンズーの神々によって豊饒の海を背景に天上に導かれる壮大な絵を描いた。その絵を見た三島さんがふと口にした言葉だった。この「インドに行ける者と行けない者」は人から人に伝わって、有名な言葉になってしまった。
生前、三島さんはよくインドの話をしてくれた。「君なんかインドに行くと卒倒してひっくり返るぞ」なんて脅かされていたが、とうとう三島さんのお許しが出て、「インドに行ける者」になったっていうわけだ。その理由は語ってくれなかった。どうもカルマ(業)と関係あるように思う。業といえば過去(前世)の悪業と関係があるようだ。インドへ行ってこの悪業を帳消しにして来い、そんな時期に来ているというのか。だけど言葉や行為によって、さらに業を積むことだってある。「どっちや?」と言いたいところだが、そんなことをいちいち考えると何もできない。三島さんの「行ける者」の資格を得たんだから、ゴジャゴジャ考えることはない。
そこで友人のカメラマンを誘って1ヶ月足らずのプライベート旅行を試みた。ニューデリーのアショカホテルでまず一泊、その翌日だったかに飛行機でスリナガルへ向かった。スリナガルは地上の天国と言われる風光明媚な実に美しい土地である。三島さんの「卒倒してひっくり返る」ようなインドは多分、ベナレスやオールドデリーの人類の巣窟のようなハリジャン(不可触賤民)のいる眼に飛び込んでくるパニック的な視点も定まらないような場所を言っていたと思う。そんな三島さんの見たインドではなく、至福の地上天国として名高いカシミールへ、僕は三島さんの言葉から逃れるような気持ちでスリナガルへ行った。スリナガルにはダル湖やナギン湖があって湖上に浮かぶハウスボートがホテルになっていた。早朝から湖上をすべるように何艘もやってくるのは観光客目当ての小舟である。一日はこの物売りの声で始まる。夕暮れは、どこから集まってくるのだろうと思う鳥の群がしじまの闇の中に消えていく。そんな幻想的な光景は本当に地上の楽園である。湖上に浮かぶハウスボートの生活は拙書『インドへ』を読んでもらえば詳しく書いてある。
スリナガルの旅の後、僕はインドへ計7回行ったことになる。インドに「行ける者」は不思議と何度でも行きたくなるようだ。
インドに行くことは、三島さんの言葉をもう少し類推すると、こちらが向かうのではなく、インドがこちらを迎えるような気がする。あなたは何回来なさい、あなたはもう来る必要がないですと言われているような気がする。インドはこちらを試しているように思う。
インドの旅は全て物珍しいものに出合って目や心の栄養になるのだが、それ以上に、自分の心の中を旅しているような気になる。外界を眺める目で心の中を眺める。ここにいながら、こことは別の心の場所を旅しているような不思議なバイロケーション(*2)感に襲われる。このような感覚はアメリカやヨーロッパの旅では味わえないインド特有の旅体験ではなかっただろうか。
旅は肉体を通して哲学することである。卓上でいくら思考しても得るものは観念である。旅に出ることは自らの肉体が乗り物に変化することで、肉体の行きたい所へついて行けばいいのではないだろうか。
*1 オスマン帝国においてイスラーム君主のハレムで奉仕する女奴隷。
*2 超常現象のひとつ。同一の人間が同時に複数の場所で目撃される現象。
プロフィール
横尾忠則
ピックアップ

PROMOTION
胸躍るレトロフューチャーなデートを、〈DAMD〉の車と、横浜で。
DAIHATSU TAFT ROCKY
2024年12月9日

PROMOTION
メキシコのアボカドは僕らのアミーゴ!
2024年12月2日

PROMOTION
〈ハミルトン〉と映画のもっと深い話。
HAMILTON
2024年11月15日

PROMOTION
〈バーバリー〉のアウターに息づく、クラシカルな気品と軽やかさ。
BURBERRY
2024年11月12日

PROMOTION
〈バレンシアガ〉と〈アンダーアーマー〉、増幅するイマジネーション。
BALENCIAGA
2024年11月12日

PROMOTION
タフさを兼ね備え、現代に蘇る〈ティソ〉の名品。
TISSOT
2024年12月6日

PROMOTION
人生を生き抜くヒントがある。北村一輝が選ぶ、”映画のおまかせ”。
TVer
2024年11月11日

PROMOTION
うん。確かにこれは着やすい〈TATRAS〉だ。
TATRAS
2024年11月12日

PROMOTION
〈adidas Originals〉とシティボーイの肖像。#9
高橋 元(26)_ビートメイカー&ラッパー
2024年11月30日

PROMOTION
〈ハミルトン〉はハリウッド映画を支える”縁の下の力持ち”!?
第13回「ハミルトン ビハインド・ザ・カメラ・アワード」が開催
2024年12月5日

PROMOTION
レザーグッズとふたりのメモリー。
GANZO
2024年12月9日

PROMOTION
〈ティンバーランド〉の新作ブーツで、エスプレッソな冬のはじまり。
Timberland
2024年11月8日

PROMOTION
この冬は〈BTMK〉で、殻を破るブラックコーデ。
BTMK
2024年11月26日

PROMOTION
ホリデーシーズンを「大人レゴ」で組み立てよう。
レゴジャパン
2024年11月22日

PROMOTION
「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3Sを体験してきた!
2024年11月22日