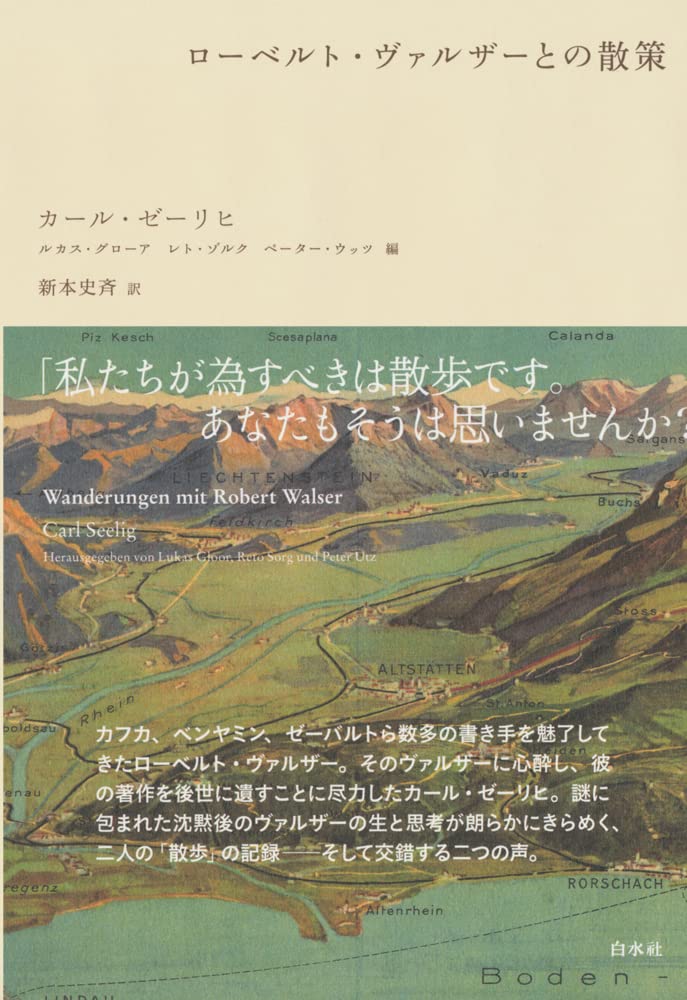カルチャー
12月はこんな本を読もうかな。
「クリスマスに読書も悪くない」と思える5冊。
2021年12月1日
text: Keisuke Kagiwada
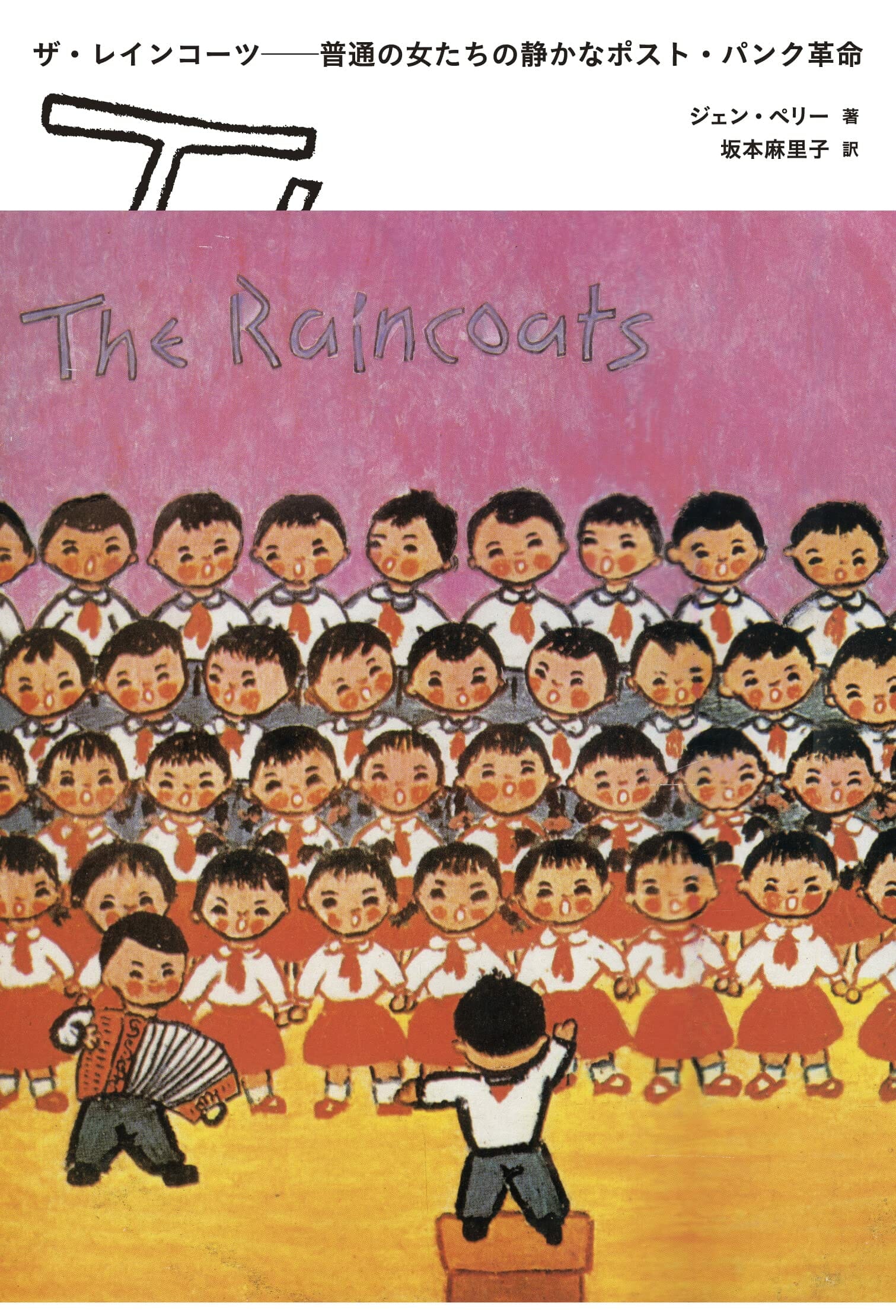
『ザ・レインコーツ──普通の女たちの静かなポスト・パンク革命』
ジェン・ペリー(著) 坂本麻里子 (訳)
1979年にロンドンで結成された4人組女性バンド、ザ・レインコーツって知ってる? 個人的には、90年代ラブコメの金字塔『恋のからさわぎ』で、ヒロインのカトリーナが好きだったフェミニスト思想に根ざした女性バンドくらいのイメージしかなかった。そんな彼女たちの詳細な来歴が綴られた本が出たので、これは読まなくては。¥2,530/Pヴァイン
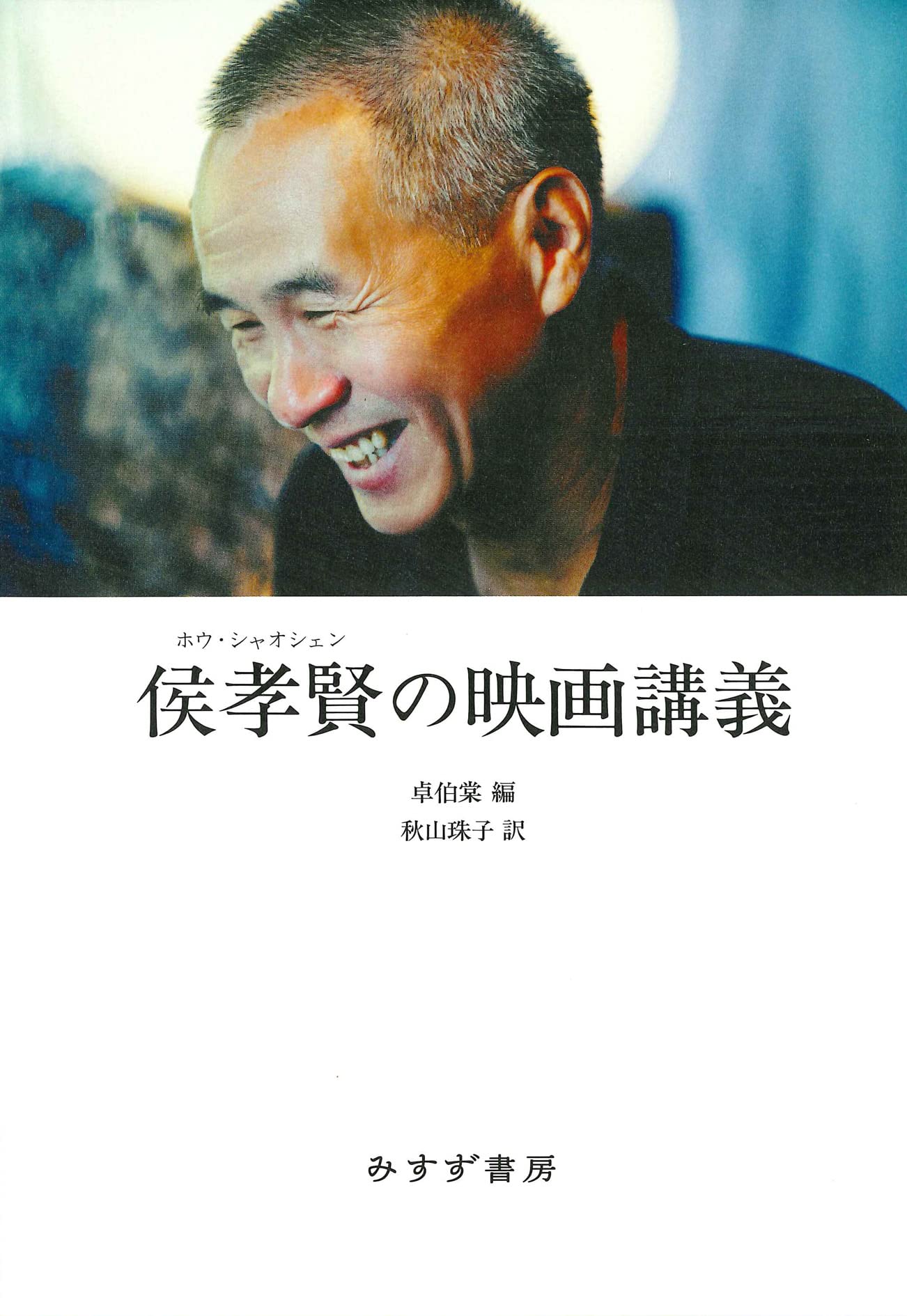
『侯孝賢の映画講義』
侯孝賢(著) 卓伯棠(編) 秋山珠子(訳)
台湾ニューシネマを率いた鬼才、侯孝賢監督が、2007年に香港バプテスト大学で行った講義の記録。のっけから引き込まれる言葉が満載だ。いわく「今日私は、自分へのこんな問いかけから始めようと思います。私はなぜ映画を撮れるようになったのか? さらには、いかなる能力と確信をもって、自分がこれでよい、あるいは好きだと思える映画を撮れるようになったのか?」。いや、必読でしょ。¥3,960/みすず書房

『図説 クリスマス全史 起源・慣習から世界の祝祭となるまで』
タラ・ムーア(著) 大島力(監) 黒木章人(訳)
そろそろクリスマスだけど、みなさんはどうお過ごしだろうか。恋人や家族としっぽり祝う、あるいは1人で通常営業などなど、いろんな過ごし方があるだろうが、そもそもこのクリスマスって何なの? ってことに豊富な図版を通して肉薄したのがこの1冊。これを読みながら過ごしてみるっていうのも、今年はアリかもね。¥3,850/原書房

『ニッポンの音楽批評150年100冊』
栗原裕一郎、大谷能生(著)
音楽について論じた批評は数限りない。音楽批評について論じた本っていうのも、まぁまぁあった気がする。だけど、明治初年前後まで遡り、現代に至るまで日本において音楽がどう語られてきたかについて、ここまで詳細な資料を通して検証した本は前代未聞じゃないか。日本における150年の音楽批評の歩みを知った後は、いつもと同じ音楽が何か違って聴こえてくるに違いない。¥2,750/立東舎
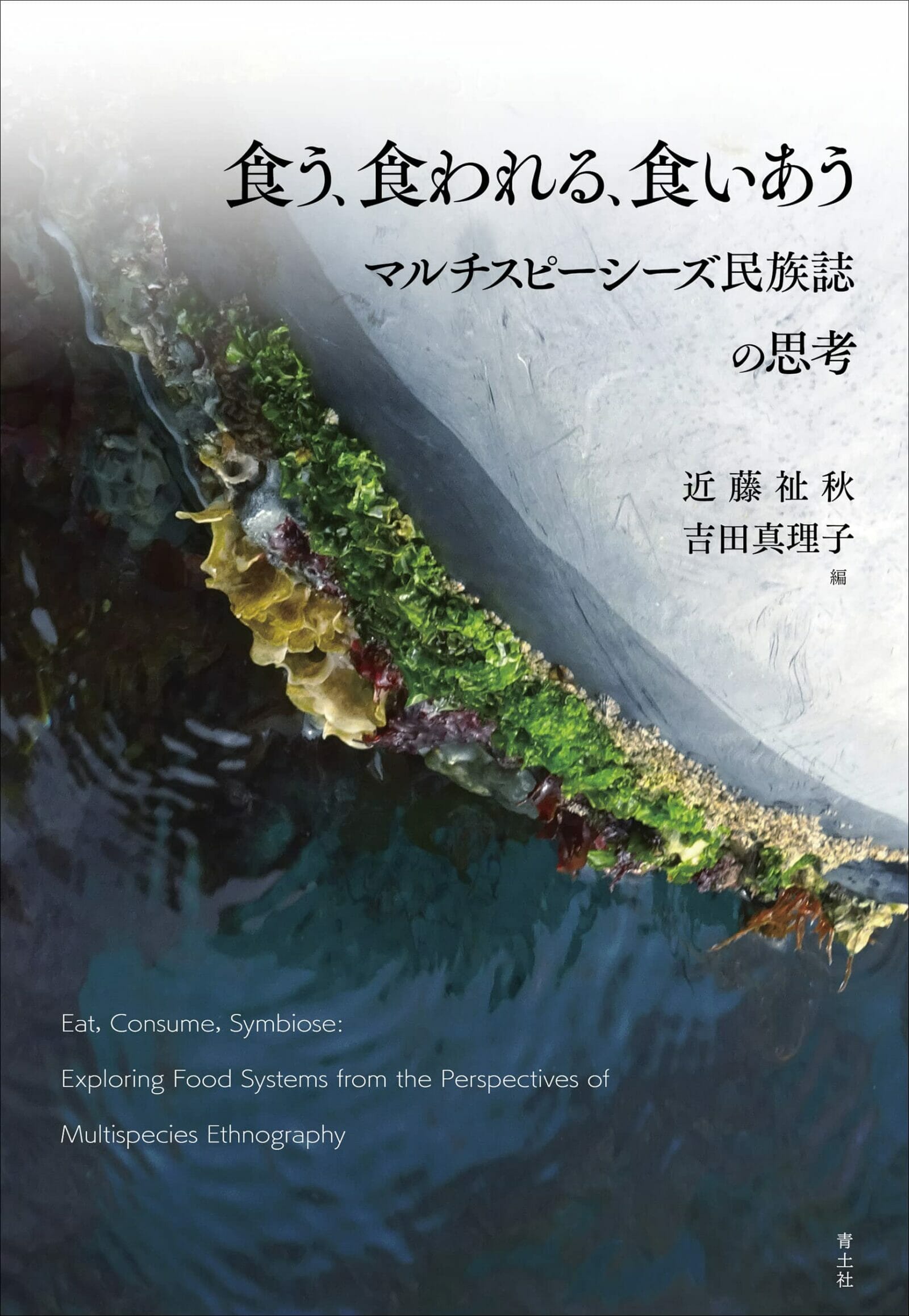
『食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考』
近藤祉秋、吉田真理子(編)
“マルチスピーシーズ民族誌”という、イカした言葉にまず惹かれる。なんでも、人間や他の生物種、ウイルス、モノなどの相互の関わりあいと、そこから浮かび上がるグローバルスケールの課題について記述する人類学の枠組みのこと……らしい。本書はそれを“食”というテーマでもって展開した論考集。正直なところかなり難しいけど、3度の飯より食べることが好きな僕らも、向き合う必要がある視点がたくさんありそう。¥2,860/青土社
ピックアップ

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日

PROMOTION
雨の日のデーゲーム
POLO RALPH LAUREN
2026年3月10日

PROMOTION
Gramicci Spring & Summer 26 Collection
Gramicci
2026年3月10日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日