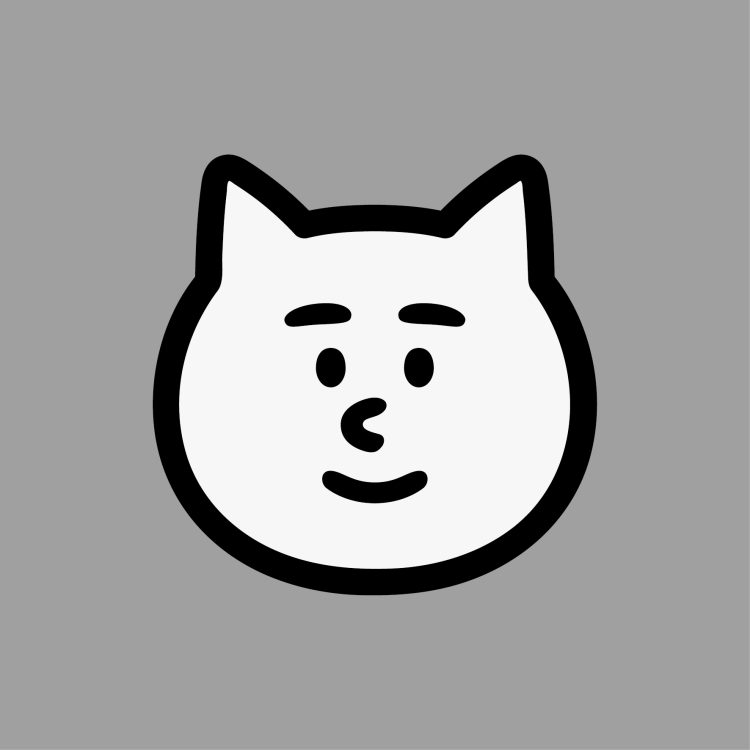TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム
【#4】新しい海辺
執筆:麻布競馬場
2026年1月1日
「昔、銀座は海だった」という話を聞いたことがある。街を歩けば、たしかに平坦な地形からは埋め立て地特有の気配が滲んでいるような気がするし、もう少し歩けば築地や勝どき、晴海といった海辺の街に辿り着く。
しかし、どうもそれは俗説にすぎないらしい。実際には、一部を除いて江戸開府以前から陸地だったようだ。残る一部も早いうちに埋め立てられ、今日に至るまでの著しい発展については言うまでもない。銀座は一貫して我が国を代表する、そして長くて正当な歴史を持つ文化的繁華街であったわけだ。
2025年の秋のとある平日の夜、僕は銀座を訪れていた。ちょっとしたエッセイ連載をとあるウェブ媒体でやる話が出てきたので、顔合わせと打ち合わせを兼ねた担当者との会食に出るためだった。指定された中華料理店に到着すると、今や老舗の域に差し掛かりつつもパリっとした清潔さが維持されており、それでいて僕のような新顔を明るく迎え入れてくれる気軽な雰囲気が満ちている。上質さを前提としつつ、肩の力を上手に抜きながら、それでいて砕けすぎていない―― いかにも「あいつ」が選びそうな店だ、と僕はあの頃を思い出して苦笑いする。
はじめまして、とあいつが名刺を差し出してきたので、僕も「はじめまして、よろしくお願いします」と返しながら名刺を受け取った。銀座はよく来るんですか、普段は港区のほうによく行かれるそうですね、と聞かれたので、僕は「ええ、僕みたいな田舎者には銀座はまだハードルが高くて」と返しながら適当に笑った。
作家としてデビューしてから3年、あいつと出会ってから15年が経っていた。目の前にいるあいつは大学卒業後、本人曰く「30歳までは遊んどかないと退屈な大人になるような気がして」という理由でフリーライター生活を続けた末、目に見えない線を辿るように、あるいは目に見えない手によって引き上げられるようにして、有名出版社に正社員として迎え入れられたのだという。数年前には例のウェブ媒体の立ち上げを主導し、現在はそこの編集長にまで昇りつめていた。
今日もお仕事だったんですか、と聞かれたので、僕は「はい、退屈な大人ですので」と相変わらずの作り笑顔で答えつつ、あいつの反応を窺った。すると、あいつは謝るでもなく、僕の意地悪な態度を指摘するでもなく、いやいや何言ってるんですか、『東京タワー』も『令和元年』も滅茶苦茶面白かったですよ、実は僕も慶應卒なので、全部僕の話かと思いましたよ、と綺麗に笑った。それを聞いて僕は、何か適当な反応を返した気がする。
全部僕の話かと思いましたよ。あいつがそう言ってからというもの、僕はそこでどんな話をして、どんな感情を抱いたのか、どういうわけかほとんど覚えていない。
22時過ぎに会はお開きとなり、僕はあいつと別れた。地下鉄はもちろん、タクシーに乗る気にもなれなくて、僕は1時間ほどかけて芝浦のタワーマンション群へと歩いて帰った。浜離宮と芝離宮の脇を抜け、日の出桟橋のあたりに出ると、銀座には永遠に存在することのない海のにおいがした。泣き出したくなるくらい懐かしい、あるいは魂の底から慣れ親しんだ、東京の海のにおい。
全部僕の話かと思いましたよ。あいつのその直感は、もしかすると正しいのかもしれない。だって、僕が書いてきたものはすべて、あいつになれなかった「僕」の話だった。裏側にはいつもあいつがいた。僕はあいつの裏側で、退屈な大人をやりながら、退屈な大人にしかなれなかった人たちのことを執拗に書き続けてきた。それをあいつが読んで、全部僕の話かと思いましたよ、だなんて笑顔で言った途端、片思いにすら似た歪んだ感情は行き場を失くしかけていた。
「あれ、お揃いですね。ほら、手首に巻いてるシェーヌダンクル」
帰り際、あいつがそう言ったのをかろうじて思い出した。相変わらずダサくて貧相な、何の文化資本も感じさせない、通販で適当に買った白い無地ロンTの袖口で不相応に光る、鮮烈な銀色。あいつが、自分の手首に巻かれたものと僕の手首に巻かれたものを見比べながら、いかにも安心したような表情を浮かべていることに僕は気付く。まるで、僕があいつと同じユニフォームをちゃんと身に着けた仲間だと認め、雑誌の内側に手招きしてやるように。
「……安心しないでくださいよ、親から引き継いだとかじゃないです。何の由来もない、ただの新品同然です。お世話になっているダサい先輩に無理言って譲ってもらった、ただの成金アイテムですから」
僕がそう返すと、あいつは何が起きているのか分からないまま、しかし相変わらず綺麗に笑っていた。それで十分だった。
夜の海辺を歩く。恋人や犬を連れた、完全に満ち足りた顔の人たちが僕を通り過ぎてゆく。もしかしたら、今の僕はようやく、彼らと同じ顔になれたかもしれない。
言うまでもなく、港区の名前は港を擁していることに由来する。僕が住む芝浦のあたりは、明治以降になって埋め立てが進められて造成された新しい街だ。その後、バブル景気の折には巨大ディスコが営業されたり、平成中期以降はタワマンが続々と建築されたりと、このあたりはいつだって「トーキョーに憧れちゃった田舎者」たちが集う街であり続けてきた。
新しいものたちは、いつだって海の向こうからやってくる。新しいものたちは、自分が辿り着いたこの新しい海辺を内心誇りつつも、遠くの高台で洗練された暮らしを送る人たちへ劣等感を募らせてゆく。そうするうち、いつしか洗練された暮らしを聞いたり読んだりして、自らもまた、少しずつ高台へと登ってゆくのだろう。
とあるタワマンの人気のないエントランスを抜けて、エレベーターに乗って、17階にある自宅に辿り着く。真っ暗なリビングの窓からは、真っ暗な東京湾の向こうに、また別の新しい街の明かりが小さく見える。高台に憧れることを、そこに登ることを拒否して、そのまま海辺で生きるという道だってあるのだ。僕はブレスレットを外しながら、窓の外をじっと見続けていた。新しい街の明かりは、あの鮮烈な銀色に似ていると思った。
プロフィール
麻布競馬場
あざぶけいばじょう|1991年生まれ。慶応義塾大学卒。2021年からTwitterに投稿していた小説が「タワマン文学」として話題になる。2022年、ショートストーリー集『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』でデビュー。2024年、『令和元年の人生ゲーム』が第171回直木賞の候補作に選出。