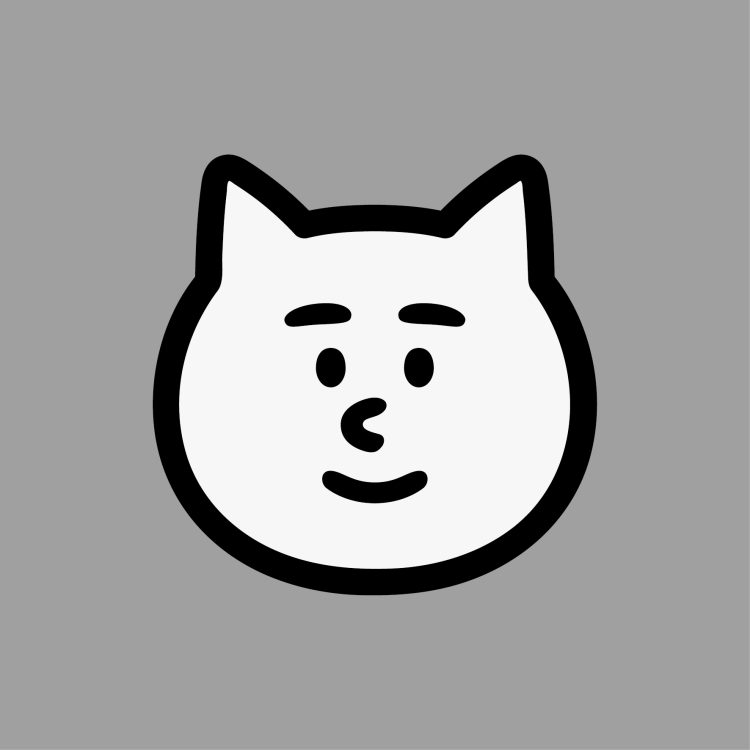TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム
【#1】最後の微熱
執筆:麻布競馬場
2025年12月11日
「あいつ」に初めて会ったのは、2010年4月の終わりのことだ。
慶應義塾大学の入学式が終わり、履修登録やサークル新歓なんかもひと段落して、僕たち新入生は「選ばれてあることの恍惚と不安」みたいなものにすっかり慣れてしまおうとしていた。それでも、風邪が治る寸前の微熱で頭がふわふわするような感覚が、それこそ悪い流行り病のように、僕たちの間で薄っすらと共有されていた。
かく言う僕がその一人だった。生まれ育った地元の街を出て、新丸子駅すぐのボロくて狭苦しい学生マンションで一人暮らしをしながら、これから始まる東京での生活(日吉キャンパスも新丸子も神奈川だったけど)に、大きすぎる期待を抱いていた。僕はこれから、何にだってなれる。だって、上京にあたって両親がプレゼントしてくれたPORTERのタンカーの中には、泣く子も黙る天下のケーオーの学生証が収まっているからだ。これさえあれば、人生のあらゆる可能性のドアは向こうから勝手に開くのだと、当時の僕は本気で信じていた。
そうして僕は、「あいつ」の存在を知ることになる。
当時流行っていたmixiには、2月の合格発表から数日もしないうちに「慶應2010入学☆」みたいなグループが立ち上がり、それぞれ色の違う自尊心を持つ新入生たちが全国各地から集まっていた。アカウントを作ったばかりで友達がおらず、そのうえ東京で友達ができるか不安だった僕は、インターネット上で社交デビューを果たし、一生懸命にグループメンバーに絡んでは友達を作っておこうと試みていた。
その一環で、僕はあいつと出会った。別に何かで深く意気投合したとかではなく、当時の僕は足跡をつけてくれた人を片っ端から訪ねては友達申請を出すような始末だった。あいつは「友だち」になってくれたものの、その後特にメッセージを交わすようなことはしなかった。
しかし、それでもあいつはどこか心に引っかかる存在だった。その原因は、おそらくあいつがプロフィール欄に書き込んでいた自身の簡単な経歴にあった。数行の文字列にすぎなかったけど、そこから僕はあいつの人生を存分に覗き見ることができた。東京の高級住宅街で生まれ育ったこと。名門私立校に幼稚園から通っていたこと。幼い頃からテニスにスキー、バンドにDJとあれこれ手を出し、そのいずれでもそれなりの成果を収めてきたこと……
つまりあいつは、少なくとも僕の地元には絶対にいないタイプだった。キャンパスの日当たりのいい場所で図々しく固まっている内部生とか、「東大に何点で落ちた」などとコスパの悪い人生を自慢している男子御三家出身者とか、東京に出てきて知った偉そうな連中とも違った。きっと頭も育ちもいいんだろうが、内部生や御三家出身者たちのように、わざわざそれを誇ることをしない。「文化」と呼ぶにはいい意味で肩の力が抜けすぎているし、「サブカル」にいくまで砕けすぎているわけでもない。かといって、家に引きこもっているだけではなく、ラケットや登山リュックを持って友達と笑顔で出かけるような、世界に対する社交性みたいなものも有している…… あいつはいったい何者なんだろう? 僕はその時点で、あいつをうまく評するための適切な言葉を持っていなかった。
キャンパスでたった数週間を過ごすうち、ここには僕より遥かに頭がいい人も、両親が有名な社長や芸能人だという人も、幼い頃から世界で活躍する文化やスポーツの才能を持つ人も、それはもう掃いて捨てるほど存在しているのだという事実を、僕は嫌でも思い知らされていた。
ケーオーの学生証ごときでは、僕はせいぜい量産型サラリーマンくらいにしかなれない。だとすれば、僕が何者かになる鍵は、もしかするとあいつにあるのかもしれない。現に、あいつは僕が知っている何者でもなく、それでいて明確に何者かであるような気がする。あいつと会い、あいつのようになれば、もしかすれば僕も――
風邪が治る寸前の微熱。平日の昼間に教育テレビをぼんやり眺めることが許された、特別な日々はまもなく終わる。明日にはすっかり熱が下がり、パジャマを脱いで退屈で平凡な学校生活に戻らねばならない。最後の夜に立ち尽くした僕の頭を、まるで幸せな夢のごとく鈍らせた、最後の微熱。僕にとってあいつは、まさしく最後の微熱だった。それが終わってしまえば、僕は現実の荒野に放り出される気がした。
《みんな、サークル決まりました? 実は、僕はどこもしっくりこなかったので(笑)、雑誌を作るサークルを立ち上げようと思ってます。興味ある人いたら連絡ください~》
だから、あいつがmixiにそんな投稿をしたのを見て、僕は衝動的に「興味あります!」と連絡してしまった。雑誌という、どこか大人っぽく浮世離れした言葉に多少心が躍ったということもあったのだろうが、それは本質ではない。あいつと一緒に何かやれる、あいつの近くにいられる。そのためであれば、サークルが取り扱うものが雑誌だろうが何だろうが構わなかったし、そもそもサークルである必要すらなかったかもしれない。
あいつの友達になりたい。いや、あいつになりたい。僕は指定されたとおりの時刻に、日吉キャンパスの学食ラウンジを訪れた。よく晴れた月曜の昼過ぎのことだった。そこには確かにあいつがいた。僕は期待に胸を高鳴らせながら、ゆっくりと、あいつのもとへと近づいていった。
シティボーイ。あいつのような人間のことをそう呼ぶのだと、僕はもう少ししてから知ることになる。
プロフィール
麻布競馬場
あざぶけいばじょう|1991年生まれ。慶応義塾大学卒。2021年からTwitterに投稿していた小説が「タワマン文学」として話題になる。2022年、ショートストーリー集『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』でデビュー。2024年、『令和元年の人生ゲーム』が第171回直木賞の候補作に選出。