カルチャー
8月はこんな本を読もうかな。
海辺のパラソルの下で読んでもいいかもしれない6冊。
2021年8月1日
text: Keisuke Kagiwada

『「探偵小説」の考古学: セレンディップの三人の王子たちからシャーロック・ホームズまで』
レジス・メサック(著) 石橋正孝(監訳) 池田潤他(訳)
江戸川乱歩やヴァルター・ベンヤミンも魅了したという探偵小説論の古典だ。探偵小説はどこに起源を持ち、どのような紆余曲折を経て、ジャンルとして成立するに至ったのか……。それが膨大な文献を参照しつつ、まさに探偵小説のごときスリリングさで綴られる。800ページ以上あるので、この本が凶器になる探偵小説があっても不思議じゃない。¥9,680/国書刊行会

『闘争と統治 小泉義之政治論集成 II』
小泉義之(著)
舌鋒鋭い筆致で現代をとりまくあらゆる問題の根源をえぐってきた著者の論考集。この本では資本主義、環境問題、人工知能、死刑制度、天皇制などが議論の俎上にあがり、目からウロコが1000枚くらいは落ちること必至の考え方が示される。特に、グレタ・トゥーンベリについて書かれた「天気の大人」は、タイトルや『アベンジャーズ』が取り上げられるあたりも含めて、とても刺激的。¥2,860/月曜社
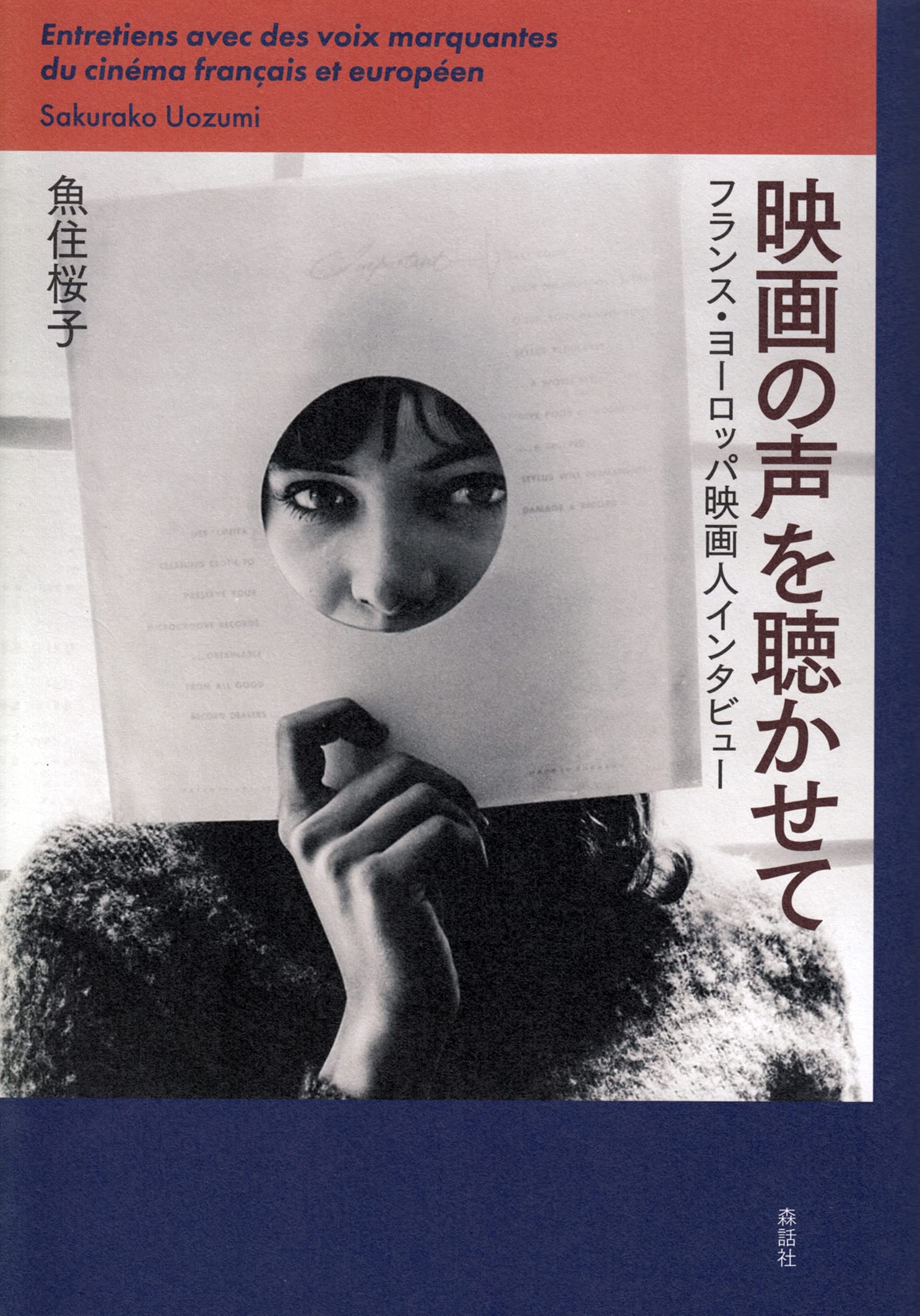
『映画の声を聴かせて フランス・ヨーロッパ映画人インタビュー』
魚住桜子
パリ在住の日本人ジャーナリストによる、フランス映画人へのインタビュー集だ。登場するのは、アンナ・カリーナ、エリック・ロメール、ラウル・クタール、ジュリエット・ビノシュ、アヌーク・エーメ、マノエル・ド・オリヴェイラなどなど! こりゃ映画好きなら「家庭の医学」レベルで一家に一冊は置いておきたい充実度だ。¥3,520/森話社
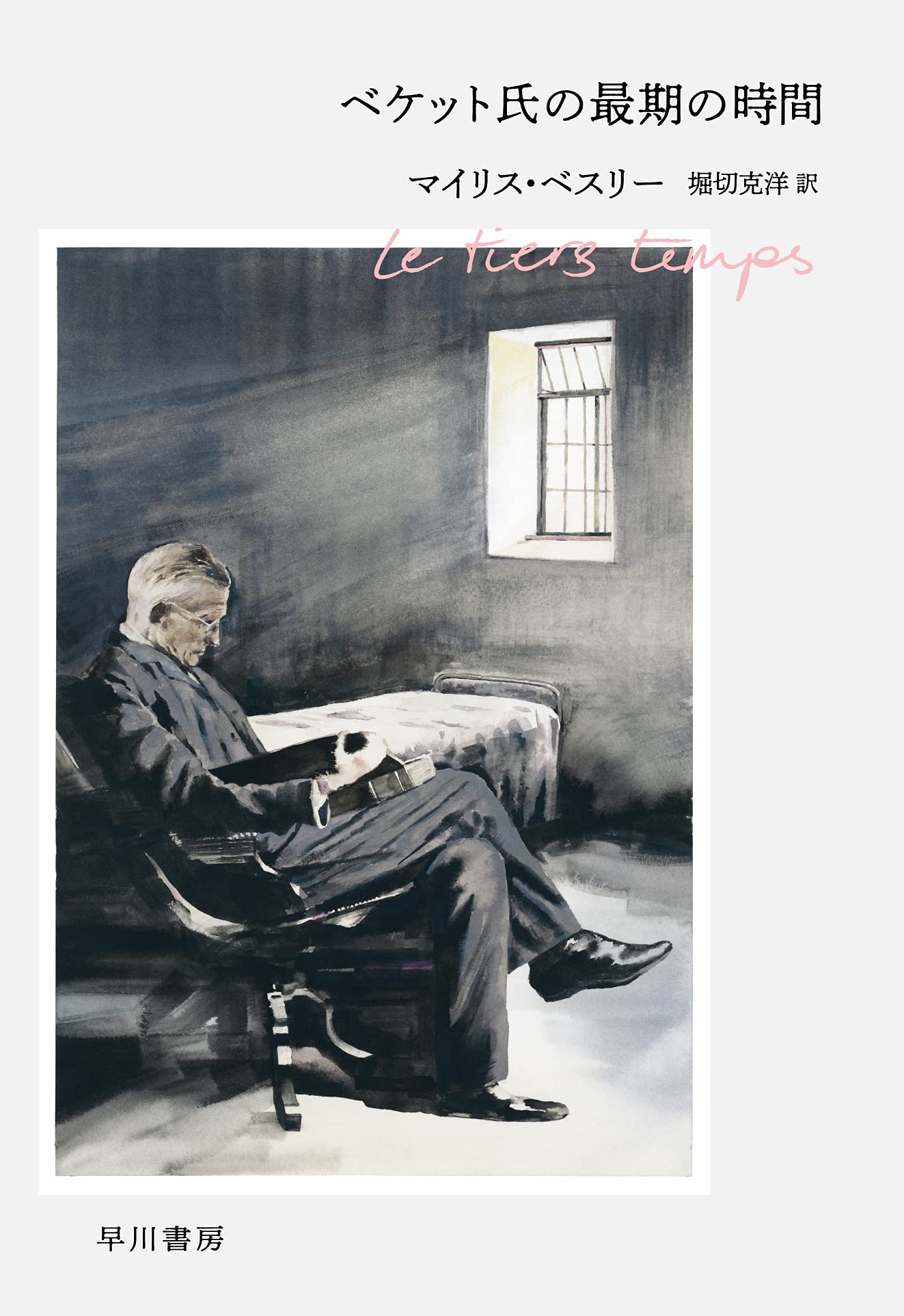
『ベケット氏の最期の時間』
マイリス・ベスリー(著) 堀切克洋(訳)
『ゴドーを待ちながら』をはじめ、そこに込められた深い意味はよくわからないけど、なぜか笑っちゃう小説や戯曲や詩を書きまくり(バスター・キートン主演の映画も作っている!)、1989年に亡くなったサミュエル・ベケット。彼はその最晩年の日々をどのように過ごしたのだろうか。それを史実と想像を織り交ぜながら描いたのが、こちらの小説。ああ、すごくいい。早川書房/¥2,860

『覆面アーティスト バンクシーの正体』
毛利嘉孝 (監)
“現代アート界のテロリスト”こと覆面アーティストのバンクシー。彼は何をやりたいのか、作品にはどんなメッセージが込められているのか。それをコンパクトかつ明快に解説しつつ、どこのどいつなのかという正体にまで迫る一冊。もしかするとバンクシーってすごくわかりやすいことをやっていて、それゆえに人気なのかも……と思ったり思わなかったり。宝島社/¥1,430
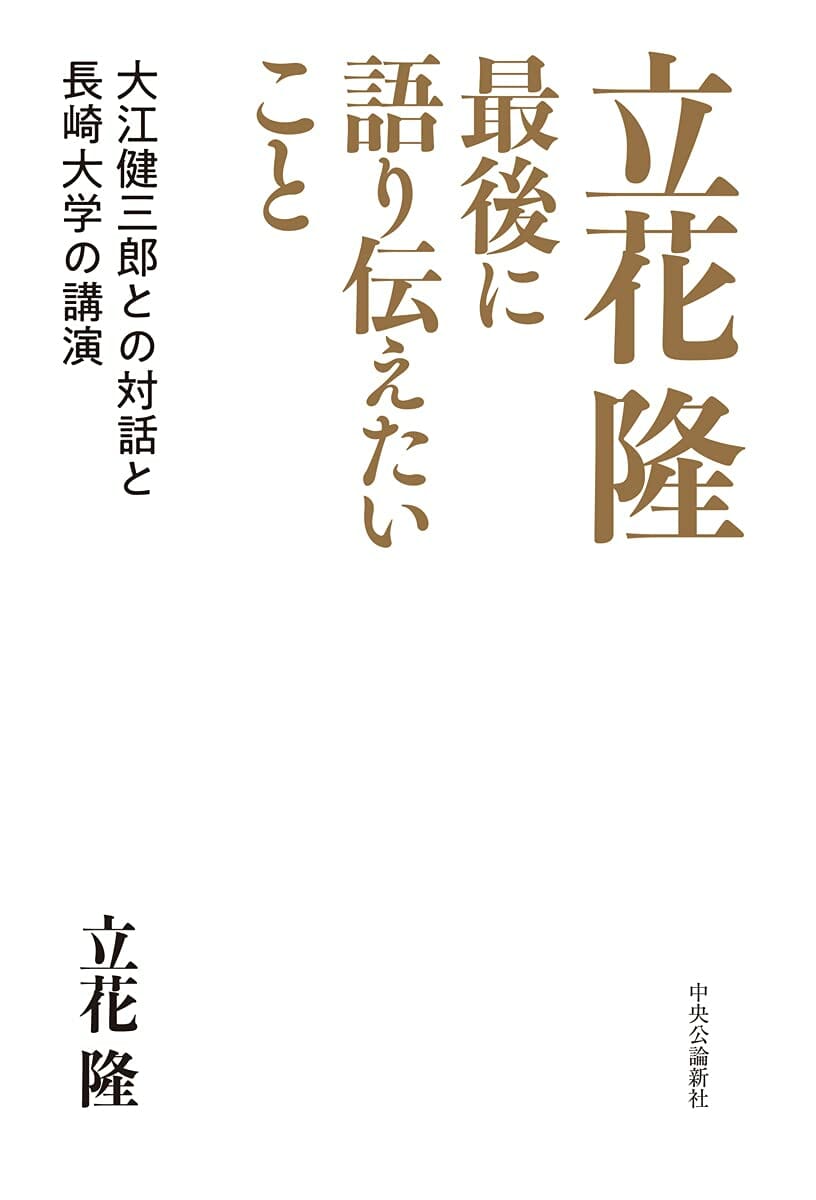
『立花隆 最後に語り伝えたいこと 大江健三郎との対話と長崎大学の講演』
立花隆(著)
2021年4月30日、立花隆さんが永眠した。ポパイ本誌の連載「二十歳のとき、何をしていたか?」は、立花さんのゼミに基づく『二十歳のころ』にインスパイアされた企画なので、本当に感謝しかない。ご冥福をお祈りします。この本はそんな立花さんが「どうしても最期に残しておきたい」と切望したという遺作だ。一部ではヒロシマ、ナガサキ、アウシュビッツの恐怖をなんとしても若い世代に伝えたいと、2015年に長崎大学で行った講演「被爆者なき時代に向けて」などが、二部ではソ連が崩壊した1991年に、21世紀を見通そうと大江健三郎さんと行った対談を収録。今こそ向き合うべきテーマが盛りだくさんだ。¥1,760/中央公論新社


![[#1] シャーロック・ホームズ・ラブストーリー](https://popeyemagazine.jp/wp-content/uploads/2021/07/SH01-1600x2332.jpg)



