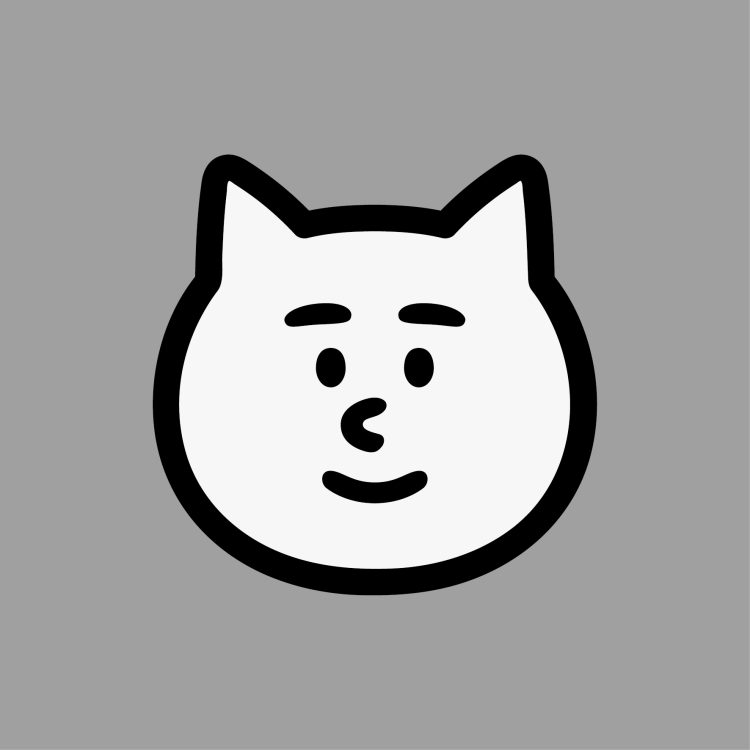TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム
【#2】銀色の傷
執筆:麻布競馬場
2025年12月18日
東京から遠く離れた町で生まれ育った僕の母親は、ファッションについて一家言を持つ人だった。東京に嫁いだ親族がいるから、という分かるようで分からない理由からファッショニスタのごとく振る舞う彼女は、日頃から夫や息子に対して服装にまつわる独自の理論を披露していた。その中核をなすのは「男はシンプルな服だけ着ていればいい」という思想で、その象徴となったのがアクセサリー禁止令だった。
男の魅力は中身にこそあるのだから、ピアスやネックレスなんかでガチャガチャと小細工する必要なんてない。国道沿いの大型量販店で売っている、無地の服をシンプルに着こなしていればよいのだ!……
そんな母の主張は、ノームコアの先駆だと好意的に解釈することもできるだろう。だが実際にはそんな素敵な話ではない。服屋らしい服屋のない地方都市。もちろんECなんてまだ影も形もない時代。小難しい言葉を持ち出せば、文化資本みたいなものを蓄積する余裕なんてない中流家庭。そういう事情が複雑に絡まり合う中、それでも朝の情報番組で細々としたファッションの素養を拾い集め、せめて息子にダサくない服を着せてあげたい母が導き出した最適解が、アクセサリー禁止令に代表される一連の主張だったのだろう。
そうして僕は、仰々しいフォントの英字がびっちりとプリントされていたり、折り返した裾にタータンチェックの生地が貼られていたりする服をうまく避けながら、無地の服ばかり着ていた。その習慣は、東京に出てきたあとも変わらなかった。むしろ、「努力によって地方から這い上がってきた」という自負から、いつしか自らの無地スタイルに圧倒的な自信を抱くに至っていた。そうだ、自分は着飾る必要なんてない。なぜなら、人間の魅力は中身にこそあるのだから。僕はアクセサリーなんかつける必要がなく、母の言うとおり無地の服だけ着ていればいいのだ。安っぽいアクセサリーをつけている同級生を大学で見かけるたび「自信のないやつだ」と内心笑うほどだった。
だから、その日も僕はいつもと変わらないスタイルだった。全身無地で、かつアクセサリーの類は何ひとつ身に着けていない。ただ、新丸子の狭苦しい学生マンションに置いている中でも、いわば一軍の無地服をわざわざ選んで着ていた。だって、僕はその日、初めて「あいつ」と会うからだ。
《学食の窓際の席のあたりに、14時くらいに》。曖昧な指示しか受けていなかったが、学食に入った僕は、すぐにあいつを見つけることができた。あいつは頬杖をついていた。ラルフローレンの白いシャツを着て、袖をラフに捲くっていた。大学デビュー組が安っぽい茶髪にしたり、ワックスで前髪をこねくり回したりしている中、黒いままの髪を無造作なセンター分けにしていた。
ファッションに無頓着な僕でも、あいつが僕とは「レベルが違う」ことがすぐに、そして痛いほどによく分かった。ラルフローレンのシャツなんて、卒園式くらいでしか着ないものかと思っていた。
あいつの周りには、すでに何人もの男女が集まっていた。学食の時計を見れば、時刻はまだ14時の10分前だ。それなのにみんな、まるで何年も前から親しいかのように打ち解け、時おり軽快な笑い声を上げていた。
「すみません、雑誌のサークルの……」と、ドキドキしながら声をかけた僕に、彼らの目線がさっと集まる。その目線の冷たさ。せっかくの楽しい時間を邪魔した、無礼で不審な人間を警戒するような目線。僕は面食らってしまい、立ち尽くしたまま黙り込んでしまった。
「誰かの友達?」あいつを取り囲む一人が、僕に声をかけてくる。顔を見れば満面の笑顔だし、口調もあくまで穏やかだが、その背後には、あの目線と同じ意図が潜んでいることが明らかだった。
「いや、mixiの投稿見て…… あの、●●●さんとは、mixiでは友達、なんですけど」
自分で言っていて、途中で情けなくなってきた。彼らの目線が、次第に警戒から困惑に色が変わってゆくのを、僕はすぐさま察した。
ああ、僕は間違った場所に来てしまったのだ。
ここでは全員が全員、あいつのような綺麗な格好をして、綺麗な標準語を喋っていた。おそらく、あいつ以外の彼らは全員、あいつと同じような生まれや育ち、あるいは精神性みたいなものを、見えないユニフォームのごとく共有しているのだ。
にもかかわらず、それらを一切持ち合わせていない田舎者が来てしまった。服装を一目見ただけで彼らにはそれが分かってしまったし、僕もまたそれが分かってしまった。残酷なくらい事態はシンプルだった。僕がすべきことは、明らかにたったひとつだった。
「あっ、ちょっと用事思い出したので。あはは、すいません……」
そう言い残すと、僕は携帯電話(当時はまだかろうじてガラケーだった記憶がある)で誰かと通話するフリまでしながら、そこから足早に去った。もしかすると、あいつが僕を止めてくれるのではないか。心のどこかで、ほんの少しだけ信じていたが、そんなことは起きなかった。結局、僕はあいつと言葉を交わすことも、目線を交わすことすらもできなかった。
「ってか、●●●のブレスレット、それシェーヌダンクルでしょ? クソ高いやつ。学生なのにエグない?」
さっきとは違う誰かが、背後でそんな声を上げた。自分たちは何も悪いことをしていない、とでもアピールするみたいに、罪悪感が一片も混ざっていない、すごく楽しそうな声。僕には何も言葉を寄越してくれなかったあいつが、その声にはちゃんと応じていた。
「いや、これ、自分で買ったんじゃなくて。親が昔からつけてたのを、お下がりで貰っただけなんだ」
へぇー、あのポパイ編集部にいたっていうお父さん? アンティークジュエリーってやつじゃん、新品買うよりかっこよくない? そんな声が続いたが、僕は相変わらず、振り返らなかった。そうか、アクセサリーをつけることはダサいことじゃないんだ、と僕はそのとき初めて知った。
学食を出るとき、ここなら大丈夫だろうと僕は立ち止まり、ようやく振り返る。遠くに、あいつが小さく見える。相変わらず、あいつにそっくりな連中があいつを取り囲んでいるのが小さく見える。
その光景は、まさしく雑誌みたいだった。選ばれた人間だけが世界に入り込むことができ、選ばれなかった人間はお金を払わされたうえ、遠巻きに眺めさせていただくことしか許されない―― そのときの光景を、僕は今でもたまに思い出す。
帰りに、日吉駅の東急デパートに入っている本屋に立ち寄った。雑誌コーナーに、さっき聞いた「ポパイ」という雑誌が置かれているのを僕は見つける。それをパラパラとめくって、結局買わずに出た。それきりだった。
プロフィール
麻布競馬場
あざぶけいばじょう|1991年生まれ。慶応義塾大学卒。2021年からTwitterに投稿していた小説が「タワマン文学」として話題になる。2022年、ショートストーリー集『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』でデビュー。2024年、『令和元年の人生ゲーム』が第171回直木賞の候補作に選出。
ピックアップ

PROMOTION
〈トミー ヒルフィガー〉The American Preppy Chronicle
2026年3月6日

PROMOTION
Gramicci Spring & Summer 26 Collection
Gramicci
2026年3月10日

PROMOTION
雨の日のデーゲーム
POLO RALPH LAUREN
2026年3月10日

PROMOTION
世界一過酷な砂漠のレース“ダカールラリー”を体感した、3日間。
TUDOR
2026年3月9日

PROMOTION
本もアートも。やっぱり渋谷で遭遇したい。
渋谷PARCO
2026年3月6日

PROMOTION
〈FOSSIL〉の名作が復活。アナデジという選択肢。
2026年3月2日

PROMOTION
もし友達が東京に来たら、教えてあげたいことがある。
EX旅先予約で巡る、1日東京アートデート。
2026年3月11日

PROMOTION
〈LACOSTE〉TWO-WAY SUNDAY
LACOSTE
2026年3月9日

PROMOTION
イル ビゾンテのヴィンテージレザーと過ごす、春のカフェ。
IL BISONTE
2026年2月17日

PROMOTION
〈ザ・ノース・フェイス〉の「GAR」を着て街をぶらぶら。気付けば天体観測!?
2026年2月27日

PROMOTION
坂本龍一の音楽とともに。渋谷PARCOは「人」から伝える。
渋谷PARCO
2026年3月12日