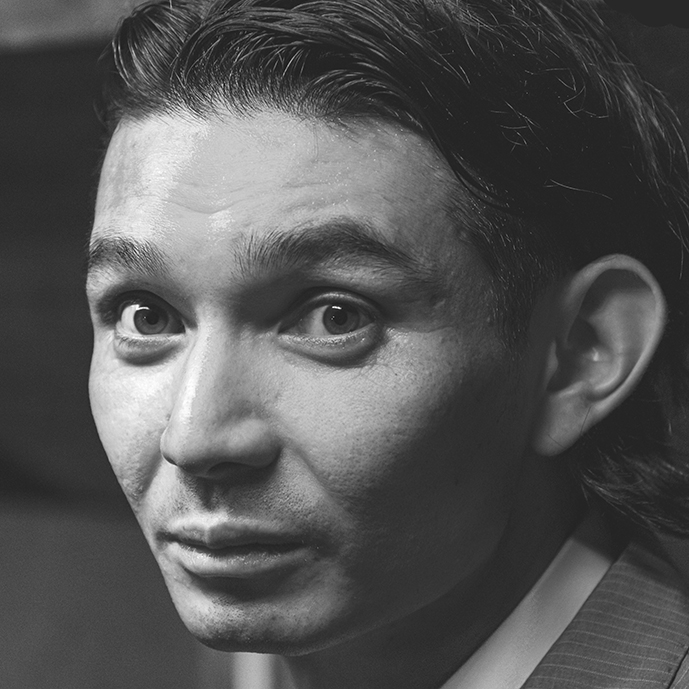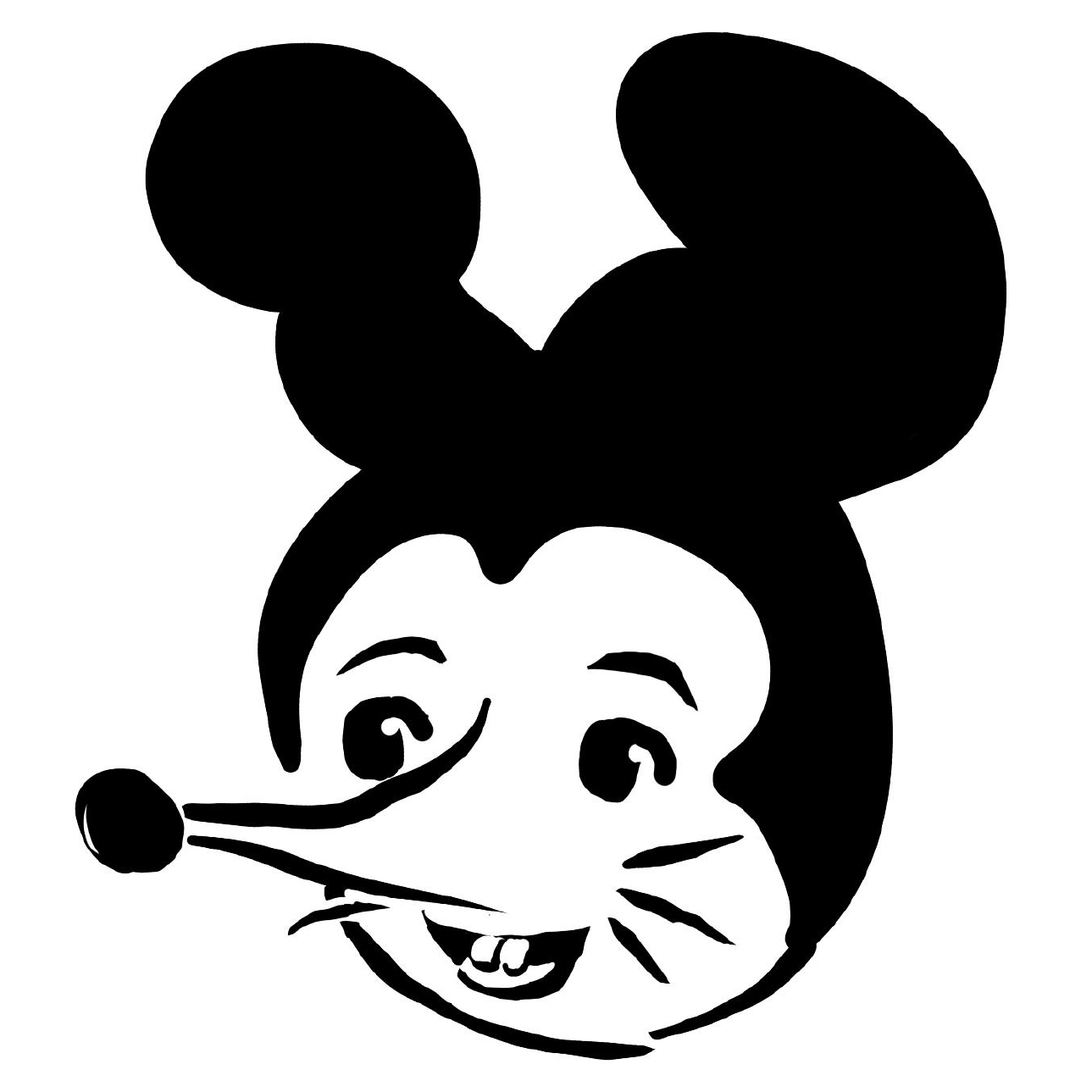TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム
【#2】美術について
執筆:佐塚真啓
2025年10月17日
「美術」という言葉について。
19歳で美術大学に入学し、美術・芸術・アート・ART、という言葉を日常的に使う人たちに出会った。しかし、それらが何を指す言葉なのか、みんな少しずつ違うニュアンスがあるような気がした。言葉は生きている。だから不動のものとして完全に定義することはできない。でも自分が使う言葉くらいは、自ら掴んで意図をもって使いたい。そんなふうにして僕の「美術ってなんだろう?」が始まり21年がたった。今、自分なりの「美術」という言葉がみえてきている。
まず、現在の「美術」の一般的な定義では、芸術という大きな言葉の中に、音楽・文芸・演劇、などと並び「美術」があるということになっている。芸術の中の視覚的な形を造るジャンルが「美術」であるということになっている。
しかし、「美術」という言葉がつくられたとされる明治期に、「美」と「術」を繋げた人が、何を考えていたのか。「美」という文字にどんな思いを込めていたのか。そんなことを考えていると、現在の「美術=視覚的な形を造るジャンル」という定義は、かなり限定的なもののように思えてくる。
美しさは、目からだけでなく、耳、鼻、口、手からも感じられるはずだ。友人との楽しい会話からも、野山に咲く花々からも、美味しい食事からも、布団の温かさからも、美しさは感じられる。日常のあらゆるところに「美しさ」は潜んでいて、それに気が付く「術」、そして、その気が付いたことを伝える「術」を「美術」と僕は考えたい。
さらに「美」という文字は、ただ「美しい」という状態だけを指すものではない。物事に向き合い、喜怒哀楽あらゆる方向に心が動いた状態を指す象徴として「美」という文字があるのではないか。心を動かす術、心にまつわる術が「美術」である。そう考えていくと、まったく美術に関係のない人はいない。
「美術史」は、人間が何に心を動かしてきたのかという歴史であると言えるし、「美術館」は、心を動かして生きている人間と、生きてきた先人たちが出会い交流する館である。「美術教育」は、人間の心が動くものに対する姿勢を教え育む学問になるのではないか。
ちなみに、芸術という言葉は「体」にまつわるものだと思っている。
体の動きが「技」になり、技が極まって「芸」になる。
人間は、体と心が交わったところに存在している。よって、心にまつわる術(美術)と、体にまつわる術(芸術)は、切り離すことのできない一対の関係にある。
芸術・アート・ARTの話はまたいつかどこかで。
プロフィール
佐塚真啓
さつか・まさひろ|美術家。1985年静岡県生まれ。丑年。おうし座。長男。A型。右利き。2009年武蔵野美術大学卒業。卒業後からは民具などの博物館資料を図化する事を始める。2011年青梅市に移住。2012年友人と共に「国立奥多摩美術館」を企画。「美術」という言葉が色々な物事を考えるときのキーワードになっている。2018年から「株式会社佐塚商事 奥多摩美術研究所」を主宰。2025年から「絵かきの里」を企画。座右の銘は、「来た時よりも美しく」。1日8時間の睡眠を心掛けている。冬はガタガタ震え、夏はダラダラ汗をかき過ごしている。
Instagram
https://www.instagram.com/satsuka_masahiro/
国立奥多摩美術館
https://www.instagram.com/moao.jp
Official Website
http://o9o2i3b874b.com/newpage4.html