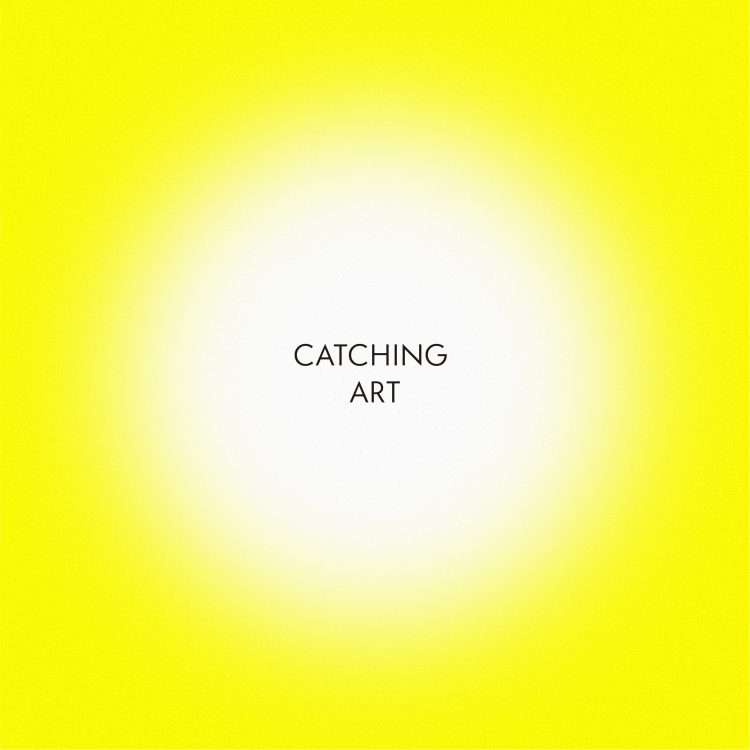カルチャー
三つの「キャッチ」について
Catching Art: 身体でアートを感じるために #1
2025年8月12日
おそらく、皆さんは京都の龍安寺に行ったことがありますよね。今回は、この世界的に有名な場所を「アート」として体験する方法について考えてみたいと思います。
その前に! 自己紹介を。私はカリフォルニア州出身のアメリカ人で、京都市の東方部に住む美術史家です。「美術史って何?」「なぜ京都に?」と質問に思う方もいるでしょう。2つ目の質問の答えは、今後の連載で少しずつ書いてみたいと思います。今回は「美術史」について。私の説明は大体2通りあります。まず、美術史は「歴史」の一つ。つまり、特定の時代や場所を、アートを通じて理解しようとしている分野。同時に、アートそのものの「見え方」作品が何をどうやって表現しているかにも注目します。この「どうやって」(つまり「形式」)こそ、歴史と深く結びついているのです。
そもそも、アートはどう見ればいいのでしょう? 私たちはつい、冷静な声で「芸術作品」と言ってしまったら、妙に博物館のガラスケース越しに鑑賞するものというイメージが思い浮かぶではないでしょうか。私は美術史家なので、ある意味では「アートを見るプロ」です。確かしそうかもしれません。だけどそれにもかかわらず、この連載では、アートは「目」だけじゃなく、身体全体で感じるものだと提案します。
「アートと身体」? どういう関係か? 龍安寺の体験を例に説明します。実を言いますと、美術史の中でも、私の専門は日本の写真史です。なのでお寺の専門家ではありません。でも、あえてこの場所で私が「感じたこと」を通じて、「Catching Art」の「キャッチ」は三つの意味を探ります。
アートを「捕まえる」
私の「Catching Art」の「キャッチ」の1つ目の意味は、野生動物を「捕まえる」ように、アートをルールに従って捉えること。龍安寺の枯山水といえば、15個の石が配置されていながら、どこから見ても1つは隠れているというのが有名です。だから現地に行って、庭の前に座ると、ガイドの方が大抵こう説明します:「石を数えてみてください。いくつ見えますか? 実はこの位置に立つと、15個全部が見えるんですよ……」
この関わり方は、あらかじめ「見たいもの」を決め、ある種のルールを知る。その頭の中のルールとアートが合う瞬間を待つ。捕まえるまで。合ったら、キャッチ!もしかしてインスタ用写真を撮って、終わり。その態度です。ここで私が「知る」「頭の中」という言葉を使ったのは、この方法が脳や理性だけに頼ったアートの体験だからです。
アートを「受け取る」
2つ目の「キャッチ」の意味は、野球の「キャッチャー」のように、アートから投げかけられるものを身体全体で受け取ること。無理やりこの野球の例えをしますと、キャッチャーはピッチャーの球を予測しつつ、どんな変化球にも体を張って反応します。文字通りに、体を柔軟しなければならない。龍安寺の庭でも、ガイドのおしゃべりを無視して、ただ庭そのものに向き合ってみましょう。10分、30分、あるいは1時間長い時間をかければ、庭が伝えようとすることに気づき始めます。
最初は見る行為だったのが、次第に感じる体験に変わっていくこともある。15個目の石を探すのをやめ、庭が投げかけるものに自分を開くと、石の配置を別の次元から受け止めることができる。「こうすると絶対こう感じる」というコツなどはないです。まるでマジカルアイのようで、自分の経験によってしか得られないものなので。もちろん目を閉じろと言うわけではありません!視覚以外の感覚によっても、アートと接することができると言いたいのです。これを試みるにあたって、少なくとも自分からの投影のない見方が必要と思います。あらかじめ用意した投影ではなく、アートがもたらす要素に反応すること。キャッチャーのように、かな。
アートと「キャッチボール」する
このようにアートを「キャッチ」したら、次はどうする?もちろん受け取ったものを「投げ返す」こと。同じ位置に座り続けていると、石の見え方が変わってきます。石の表面じゃなくて、石と他の石の「関係」が現れているかもしれません。そしてやがて雲の動きで変わる光の質も気付ける。鳥やトンボが飛び込むと、急に庭の空間を引き立てる。つまり、庭と自分の身体との間に生まれる反応に気づくでしょう。それは予測不能で、予め誰にも言葉にできません。
抽象的かつ詩的に聞こえるかもしれません。龍安寺に行くと必ずこうなる、と言うわけじゃない。ただ、私自身がそう感じたことがありますし、きっと私だけではありません。今回、わざと世界的に有名な場所を取り上げたのです。有名なアートでも、重要なのは自分なりに、自分の身体を開いて、「キャッチ」することだと思います。そうすれば、新しい体験が待っているはずなのです。
プロフィール
ダニエル・アビー
1984年生まれ。アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。美術史博士(UCLA)。2009年から日本の美術や写真にまつわる執筆・編集・翻訳に携わる。現在、大阪芸術大学 芸術学部 文芸学科の非常勤講師として美術史・写真史を教えている。
https://mcvmcv.net/