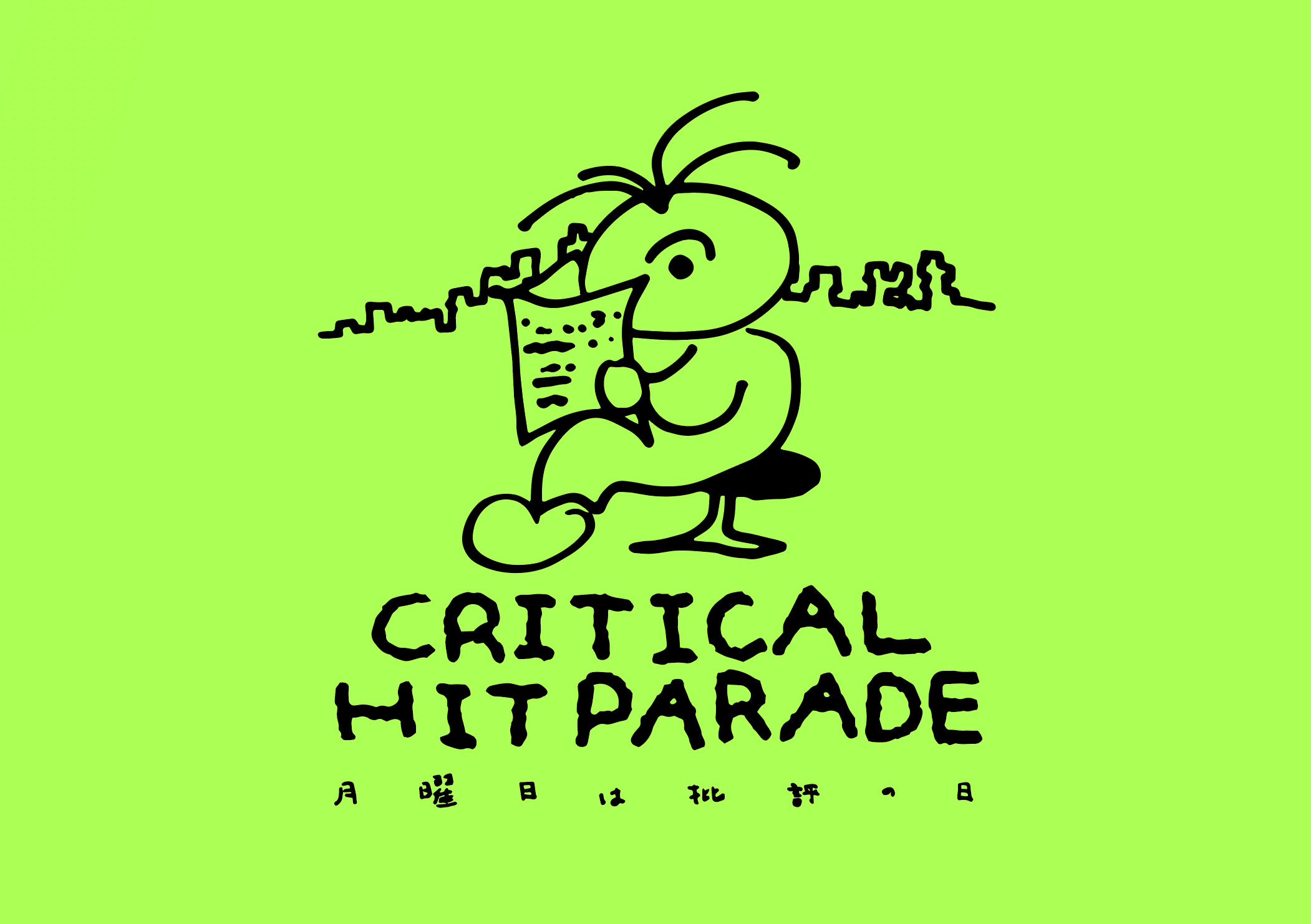カルチャー
アメリカ文学を研究する青木耕平さんによる『盲目の梟』のレビュー。
クリティカルヒット・パレード
2025年9月6日
illustration: Nanook
text: Kohei Aoki
edit: Keisuke Kagiwada
アメリカ文学を研究する青木耕平さんが新しい小説をレビューする「クリティカルヒット・パレード」。今回取り上げられるのは、『盲目の梟』だ。
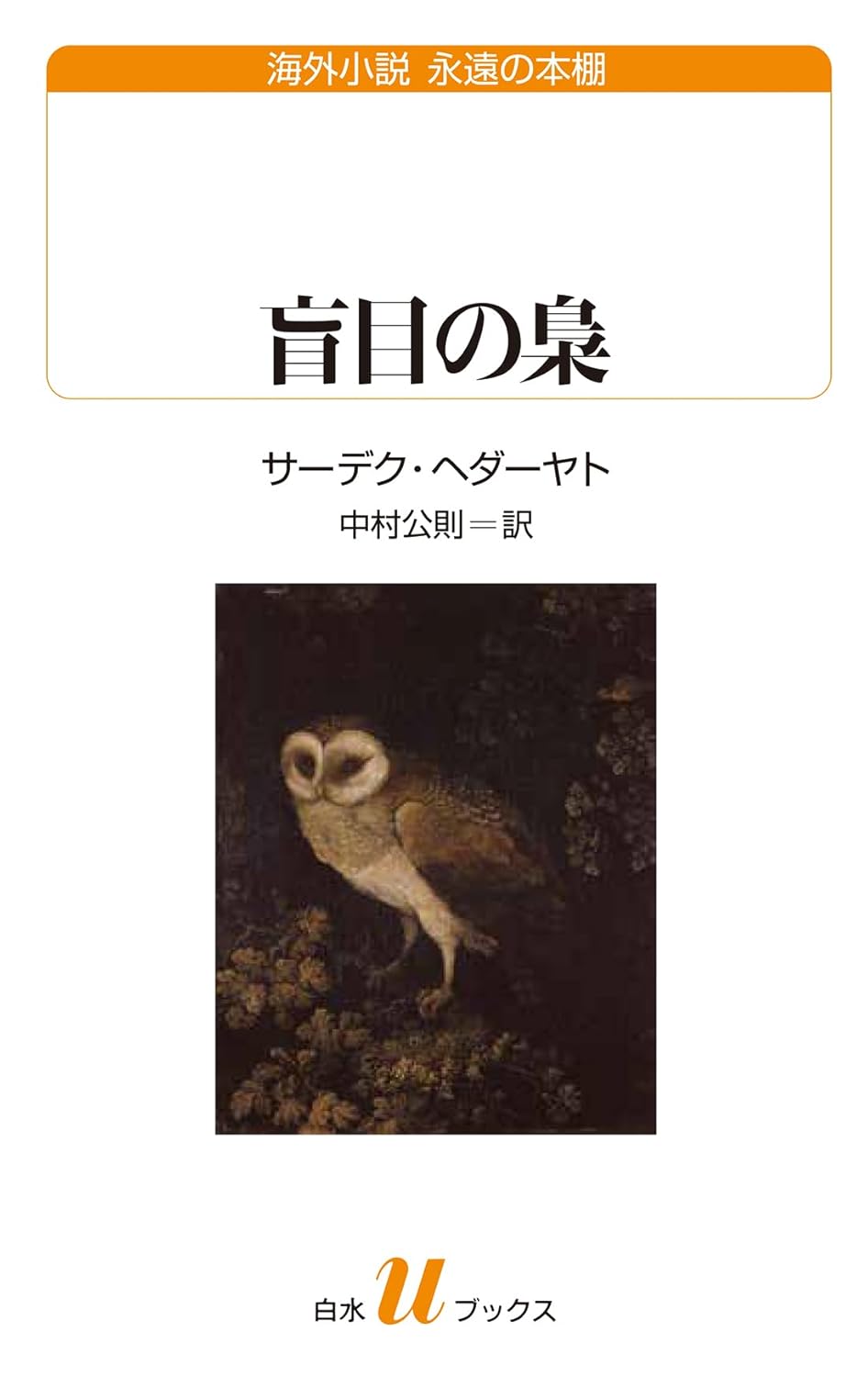
『盲目の梟』
サーデク・ヘダーヤト(著)
中村公則(訳)
¥2,090/白水社
最初に大切なことを言わせてほしい。『盲目の梟』は、歴史的な傑作である。ここ日本で約40年ぶりに新版が発売されたが、英語圏においては実に4つ目の新訳がペンギン・クラシックより2022年に刊行された。本作はすでに数十を超える言語に訳され、2023年には世界中の研究者が寄稿した論集が出版され、国際会議が開かれた。
世界中の読者が、今世紀に入って新たに『盲目の梟』に出会っている。私もこの夏に初めて出会った。あなたも出会うべきだ。ただ一つだけご用心、──「
中編小説『盲目の梟』は、1937年にイラン国籍を持つ33歳の青年サーデク・ヘダヤートによってペルシア語で書かれた。本作がいかにイラン文学・文化において重要だったかは、中村公則氏による素晴らしい訳者あとがきと、中村菜穂氏の優れた解説があるのでここでは触れない。そのような自国文化に偉大な足跡を残しつつも、『盲目の梟』はいまや言語や国家を超えて、偉大なる20世紀文学として読まれている。
研究者たちは語る。いわく、『盲目の梟』は、エドガー・アラン・ポーの美学に貫かれ、フランツ・カフカの不条理が現前し、ドストエフスキーのオブセッションが憑依し、同時代のシュールレアリストたちの論理によって物語が支配されている。そればかりではない。本作を支配する厭世と存在への恐れは戦後のフランス実存主義を先取りさえしている──。
このような評価が定着する中、興味深い新たな説が、アカデミアではなく一般読者の口から上がり始めた。評者はその説にとても魅惑され説得させられた。それは、一言で要約すると次のようになる──
以下、本レビューでは、『ロスト・ハイウェイ』と『盲目の梟』の内容に踏み込む。未読・未視聴の方は注意されたし──。Hoo! Hoo! Hoo!
🦉. 🦉. 🦉. 🦉. 🦉. 🦉.
『ロスト・ハイウェイ』を初めて観た時、私はあまりに混乱し、スクリーンの前に置き去りにされたまま、物語が進展するのを呆然と見守った。私だけではなく、多くの人がそうだったろう。そしてそのような人はまた、『盲目の梟』の構造を初読で理解できないだろう。両者の最大の共通点、
『ロスト・ハイウェイ』の主人公はジャズ奏者のフレッド。ある日、家の前にビデオテープが置かれているのを妻が発見する。それは、夫婦が住む家の中が撮影されたテープだった。不法侵入であると警察に通報し、警備を依頼する。その日パーティーで、フレッドは初老の男に「私たちは会ったことがある」と話しかけられる。そのような記憶はないと返すと、男は「たった今、私はここと同時にあなたの家にいる」と告げ、フレッドが自宅に電話すると、自宅の受話器からその男の声が聞こえ、フレッドと妻はすぐに帰宅する。翌日、また新たなテープが届く。再生すると、その中にはバラバラになった妻の遺体と、その横で叫ぶフレッドが映し出されていた。そのテープを見て混乱し妻の名を叫ぶフレッドだが、気が付くと彼は妻殺しで逮捕されていた。死刑が求刑され、独房に監禁されるも、頭痛は激しさを増し、医者が睡眠薬を与える。独房に戻っても頭痛が消えないフレッドは、初老の男の幻覚を見る。翌朝、看守が独房を覗くと、
中編小説『盲目の梟』は、一人称で書かれている。〈私〉には「孤独な魂を蝕んでいく潰瘍のような古傷」があり、「己自身を自らの影に示さんがため」に、その古傷となった過去の体験を綴ると冒頭で宣言される。
〈私〉は筆箱に絵を描く職業だが、なぜか「樹の下に座る老人と、花を差し出す女性」の絵ばかり繰り返し描いてしまう。しかしそのモティーフがどこから来たかわからない。ある日、「それまで一度も会ったことのない」老人が叔父であると自称して尋ねてくる。酒を出そうと棚に手を伸ばした時、通気孔を通して「樹の下に座る老人と、花を差し出す女性」の姿が目に入る。女と目があった瞬間に、〈私〉は忘我の境地となる。翌日、どうしてもまた女を見たいと通気孔を覗こうとするが、通気孔などそこにはなかった。失望に暮れていたが、ある日、その女が玄関の前に座っていた。女は家に上がり込み、横になる。そこで〈私〉は突如として気づく、その女が死んでいることを。〈私〉は彼女の身体をバラバラに切り刻んでトランクに詰めると、「あなたのことも、あなたの家がどこにあるかも知っている」という老人が現れて墓堀を手伝い、女の遺体を埋める。〈私〉は阿片を飲み、意識が混濁し、気づくと「小さな部屋」にいて、眠りに落ちる。目が覚めた〈私〉は新たに語り始めるが、
前半部だけで『ロスト・ハイウェイ』と『盲目の梟』の類似点を挙げればキリがない。両作ともさらに後半部で入れ替わった主人公[語り手]の人生が展開するのだが、全くの別の話のようでありながら、前半部と同じモティーフ、細部、そして「死んだ女を想起させる女」が登場する。
すでに両者を比較した学術論文は書かれているが、リンチが『盲目の梟』を実際に読んだかどうかは定かではない。そして、その事実はさほど重要ではない(リンチは『ロスト・ハイウェイ』の着想元を当時のO・J・シンプソン事件である、と公言している)。リンチ映画のファンならば、この構造の類似を『マルホランド・ドライブ』に見出すことだろうし、『盲目の梟』は、「世界で最も詩的なトピックは、美しい女性の死である」というエドガー・アラン・ポーのテーゼの実践版とも言えるが、リンチもまた『ツイン・ピークス』でローラ・パーマーという「世界一美しい死体」を中心に据えたのだった。上記のポーのテーゼは現在ならば「男性中心の視線」そのものであるが、『盲目の梟』そして『ロスト・ハイウェイ』では、「女性の視線」に怯える男性たちが描かれもする。
分身、分裂、ドッペルゲンガー、影、はリンチ作品からの影響を公言している村上春樹にも繰り返し現れるテーマであるし、ポーやカフカの名を出すまでもなく、古来より芸術が追い続けたテーマでもある。リンチ作品の背後には数えきれないほどの先行する映画たちがあり、『盲目の梟』は西洋と東洋の文学の上に成り立っている。
ただ、その上でなお、この両作品の類似は「よくできた偶然」の域を超えているように思える。このような特異な構造でしか語れない世界がある。無意識や夢や精神分析ではなく、「盲目の梟」にしか見えない世界が、きっとあるのだ。梟は見かけによらない。
レビュアー
青木耕平
あおき・こうへい|1984年生まれ。愛知県立大学准教授。アメリカ文学研究。著書に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』(共著、書肆侃侃房)。