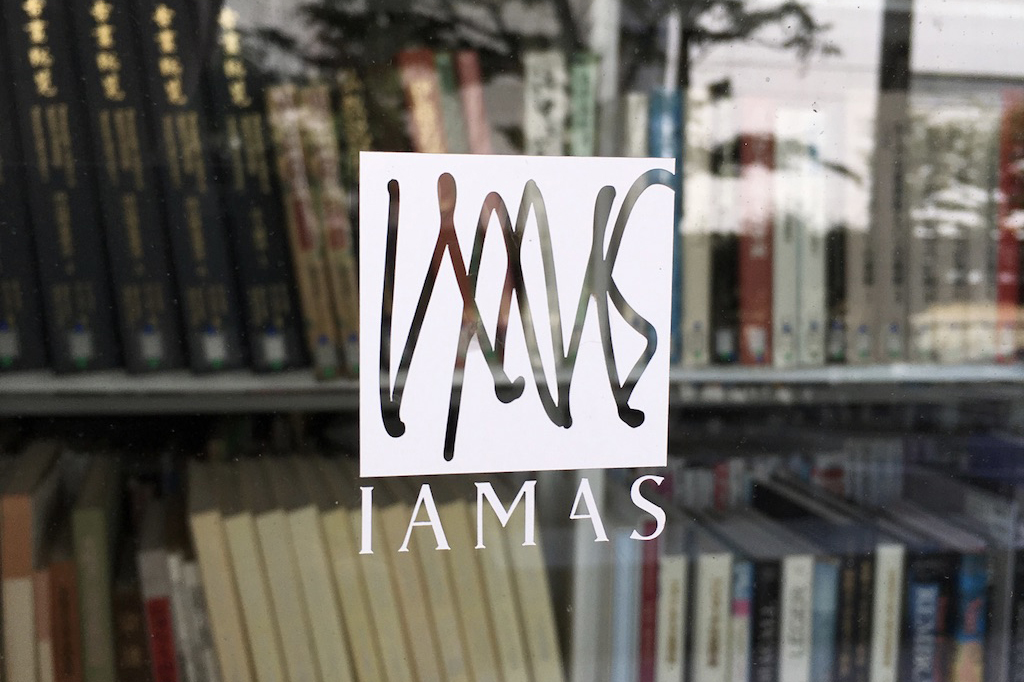TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム
【#2】BMCへ行って、共同体について考えた
執筆:永原康史
2025年7月22日
ぼくがノースカロライナ州に通って調べていたブラックマウンテンカレッジ(BMC, 1933–1957)は、いうなれば「大学コミュニティ」である。BMCに「学校」と「コミュニティ」両方の側面があったのは、教員家族と学生が寝食を共にし、共同の農地を耕し、家畜を飼い、生活の雑事を分担するなど、そういったことをすべて含めて教育としていたからだ。あげくの果てには自分たちで校舎まで建てている。もうコミューンと呼んでもいいぐらいだ。
地縁・血縁といわれるように、家族、親戚、地元の人たち、つまり自分で選んでいないが強い関係を持つ集団がある。学校も似たようなもので、偶然同じクラスになった人たちと関係を築く。でも学校は自分で選ぶのだから、まったくの偶然というわけでもない。入学審査を経て同質の人が集まる場所でもある。もともと学校は、コミュニティ的要素をもっている場所なのだ。

BMCの学生たちが自分たちの校舎を建てている写真。NC州西部アーカイヴにて筆者撮影。Courtesy of BMC Records, WRA.

校舎全景、おおよそ築80年のDIY建築。手前の小屋とベランダの屋根、奥の煙突はあとから増築したもの。

まさに地縁を象徴するようなブラックマウンテン・ダウンタウンの親父。南部は家族や地元との結びつきが強い。
ぼくが最初に教鞭をとったのは、略称でIAMAS(イアマス)と呼ばれる科学と芸術の境界領域を学ぶ県立の小さな学校だった。設立は1996年。日本でインターネットの商用利用が認められて2年と少し、Googleができる2年前の、メディアアートという言葉がまだ目新しかったころだ。
開校当初、IAMASは廃校になった女子校跡地を利用しており、周囲には自動車教習所と小さな食堂がひとつあるだけだった。学校は24時間開いていて、仮眠室とシャワー室があった。洗濯機もあったと思う。その気になれば住める。充実したコンピュータ設備には、まだ珍しかった高速インターネット回線が繋がっており、コミューン化する条件は揃っていた。そして、実際にコミューンとなるのにさほど時間はかからなかった。
ウェブデザインという言葉ができたばかりのころだったと思う。連載を持っていたデザイン誌の担当編集者に、若い優秀なウェブデザイナーがみんな同じドメインのメールを使ってるんですが、なんだかわかりますか? と聞かれたことがある。IAMASのドメインだった。Gメールのような気軽にメールアドレスをつくれるサービスがまだなかったので、学校でメールサーバーを立てて学生全員のアカウントを用意し、卒業してもそのアドレスを使えるようにしていたのだ。
ぼくが行ってる学校の卒業生ですよ。そう伝えると、その雑誌は数ヶ月後にIAMASの特集を組んだ。嘘のような本当の話だ。卒業してもコミュニティは存続し、知らないもの同士でも卒業生というだけで仲間意識が生まれた。そして、メールのドメイン名がIAMASコミュニティに属している証となっていた。
ぼくがその学校を離れたのは、もう20年も前のことだ。そのころには誰もがメールアドレスを取得できる世の中になっていて、卒業後にIAMASドメインのアドレスを使うこともなくなっていた。もし、今も変わらずコミュニティが存在しているとすれば、それをつなぐものは何なのだろう。IAMASの経験がなければ、ぼくはBMCにこれほど興味を持っていなかったのかもしれない。
プロフィール
永原康史
ながはら・やすひと|グラフィックデザイナー。印刷物から電子メディアや展覧会のプロジェクトまで手がけ、メディア横断的に活動する。2005年愛知万博「サイバー日本館」、2008年スペイン・サラゴサ万博日本館サイトのアートディレクターを歴任。1997年~2006年、IAMAS(国際情報科学芸術アカデミー)教授。2006年~2023年、多摩美術大学情報デザイン学科教授。『日本語のデザイン 文字による視覚文化史』(Book&Design)、『よむかたち デジタルとフィジカルをつなぐメディアデザインの実践』(誠文堂新光社)など著書多数。2024年には現地に通って書きためたリサーチと旅のエッセイ『ブラックマウンテンカレッジへ行って、考えた』(BNN)を上梓した。第24回佐藤敬之輔賞など受賞。