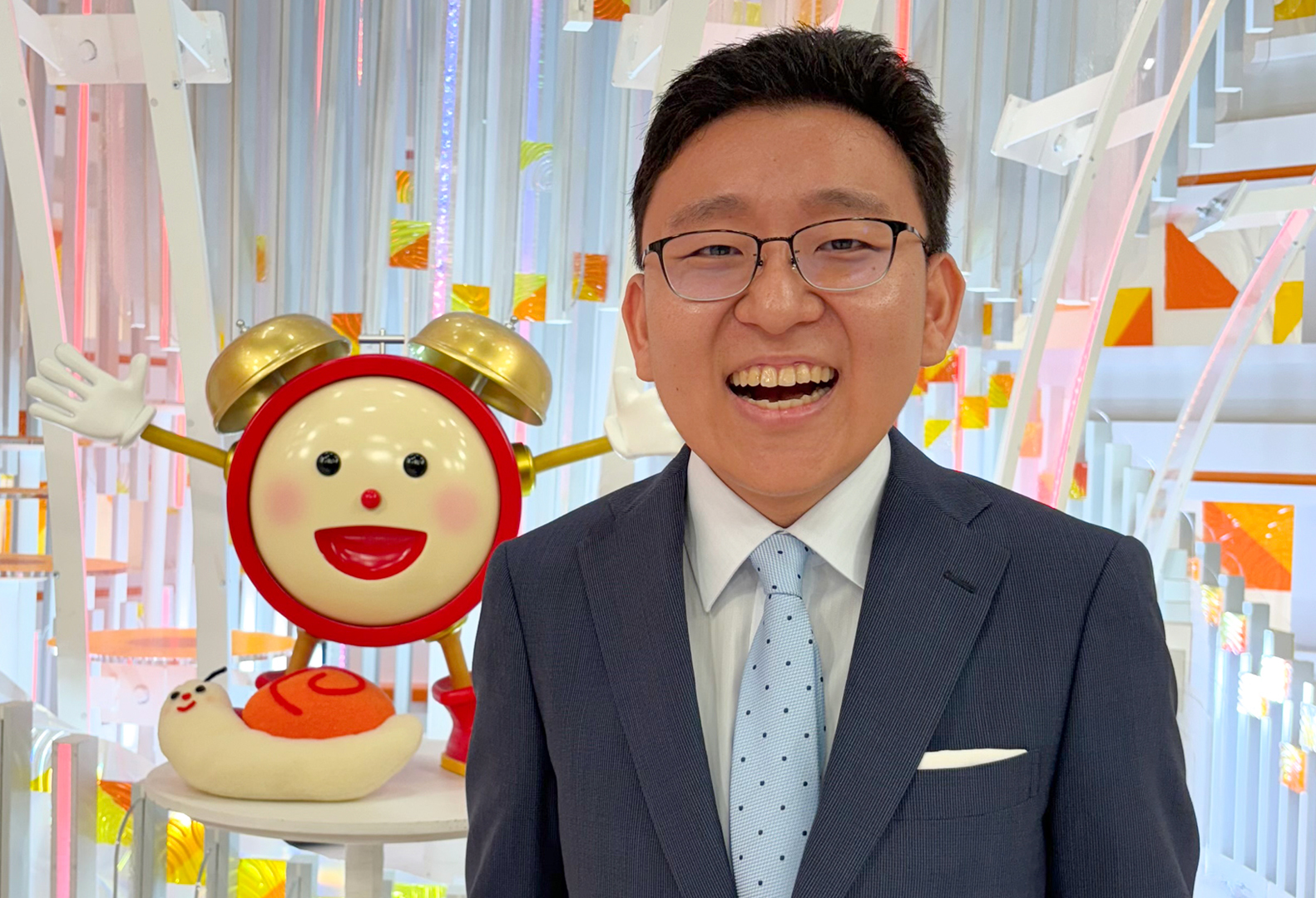TOWN TALK / 1か月限定の週1寄稿コラム
【#2】教員にはならなかったけれど
執筆:上垣皓太朗(フジテレビアナウンサー)
2025年9月22日
フジテレビアナウンサーになって、1年半が過ぎた。
大学で国語と地理歴史の教員免許を取得したものの、教職には就かなかった私は、ペーパードライバーよろしく、ペーパーティーチャーのひとり。
とはいえ、教職課程のころの気持ちを忘れてはいけないと、ときどき思う。
まずは、地形図が好きな私から、みなさんに質問。
「次の地図(茨城県下妻市の一部)を見て、印象に残る地形は何ですか?」
いかがだろうか。
もちろん地図は自由に読んでいただければ幸いである。
しかし、私が同じ質問に答えるなら、「カーブを描くようにひと続きになっている部分」と答えるにちがいない。
こうして赤色で加筆するとわかりやすいだろうか。
ひらがなの「つ」のような模様が大地に刻まれている。
これは旧河道(きゅうかどう)といい、昔の川の流れた跡。地図の左側に流れている大きな川が現在の鬼怒川だが、鬼怒川はかつて、「つ」の部分を蛇行していたのだ。
旧河道は、洪水のときに川のカーブの一部が切り離されたり、治水工事で川の流路を変えたりして生まれる。道路の舗装や宅地開発でわかりにくくなっていることもあるが、この地域の場合はとてもわかりやすい。
一般に、旧河道はかつて川が流れていただけあって、周囲より低くて水が集まりやすい。また、堤防と旧河道が接しているところでは、堤防が切れるリスクも高まることがある。
地図は、こうした大地に残った痕跡を教えてくれるのである。
さて、ここからが地理教員候補生としての腕の見せどころ。教職学生が集まれば、この地図を使って授業をつくれないか、地理の時間に防災教育ができるんじゃないかと、みんなで知恵の出し合いが始まる。
加筆前のなんのヒントもない地図で、3か所ぐらいに印をつけよう。「洪水が起きたら、どこが一番浸水しやすいと思う?」と3択で生徒に尋ねたらどうだろう?
きっと生徒は、現在の川から近ければ近いほど浸水しやすくて、遠ければ遠いほど浸水しにくい、と考えるんじゃないか。
そして、「実はそんなに単純な話でもないよ」と言って、旧河道の説明をしたら、興味をもってくれるかもしれない。
・・・学生どうしでそんなことを、わいわいと話し合うことになる。
「教員はクリエイティブな仕事だから、互いのアイデアに感化されながらいい授業をつくってほしい」教職課程では、そう言われてきた。
教員にはならなかったけれど、アナウンサーもクリエイティブな仕事である。中継ひとつ、VTRひとつに、無数のアイデアを持ち寄って議論する。それは、教職課程の「話し合い」の熱気に通じる。
防災報道にも従事することがある。旧河道しかり、地域の特徴に注目すると、伝え方のヒントが見えてくるときがある。
災害が起きてからの報道だけでは十分ではない。むしろ発災前、日々の啓発こそが重要なのだと、アナウンス部の防災班に所属するアナウンサー同士でよく話している。そういう意味では、広い意味での「防災教育」の視点には、参考にできることがあるのだと思う。
いま、フジテレビの公式WEBニュースサイト「めざましmedia」で、自然災害の伝承碑を訪ね、災害の歴史を学ぶ連載「上垣アナの災害遺構探訪記」を続けている。自分が学び続けていないと、お伝えすることはできないと痛感している。
プロフィール
上垣皓太朗
うえがき・こうたろう|フジテレビアナウンサー。2001年兵庫県出身。2024年にフジテレビに入社し、現在は「めざましテレビ」「めざましどようび」「かまいまち」などを担当するほか、競馬などの実況でも活躍。趣味は銭湯での長風呂、AMラジオ視聴。特技は地形図を見ながら街を歩くこと。
Official Website
https://www.fujitv.co.jp/ana/profile/k-uegaki.html