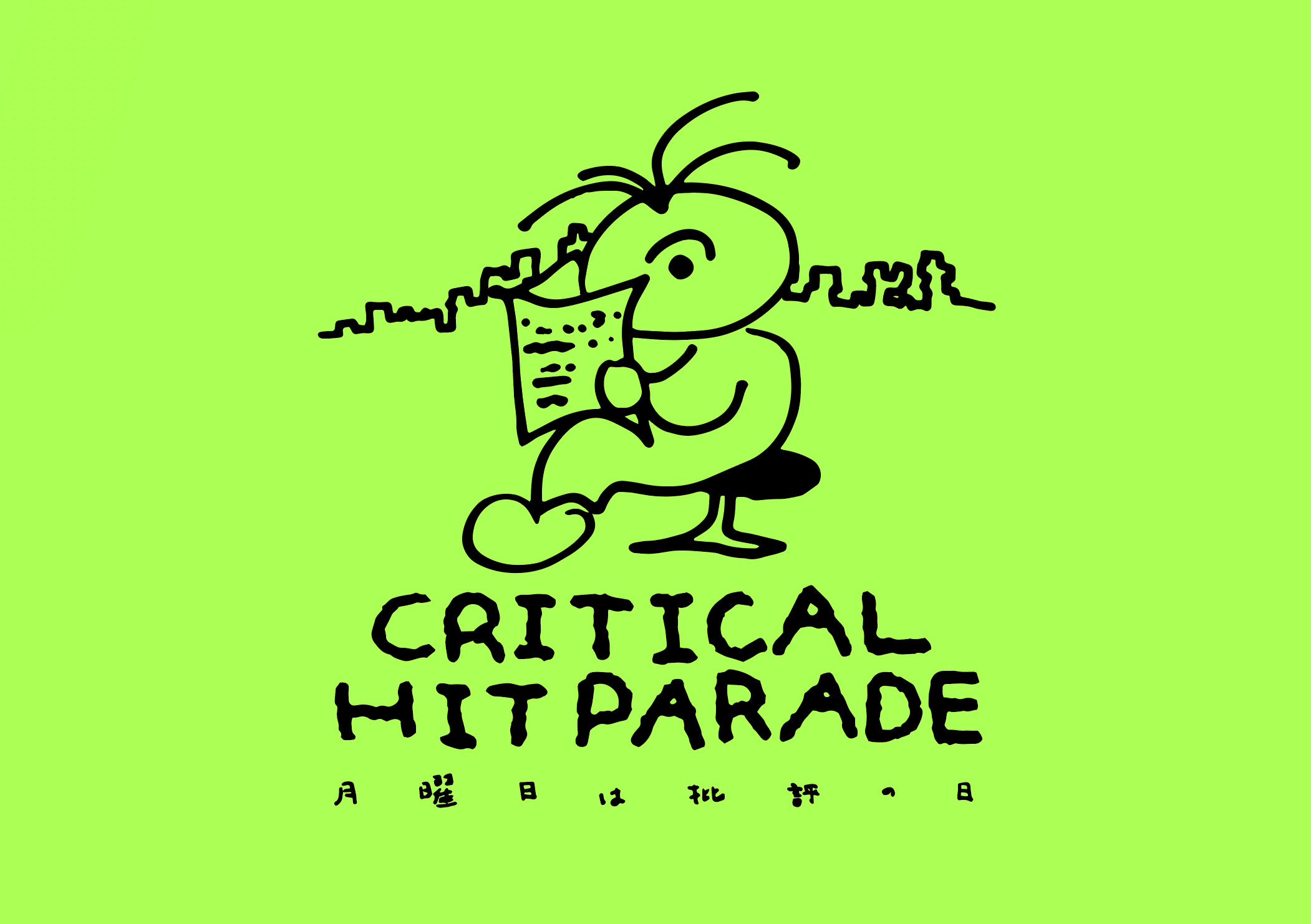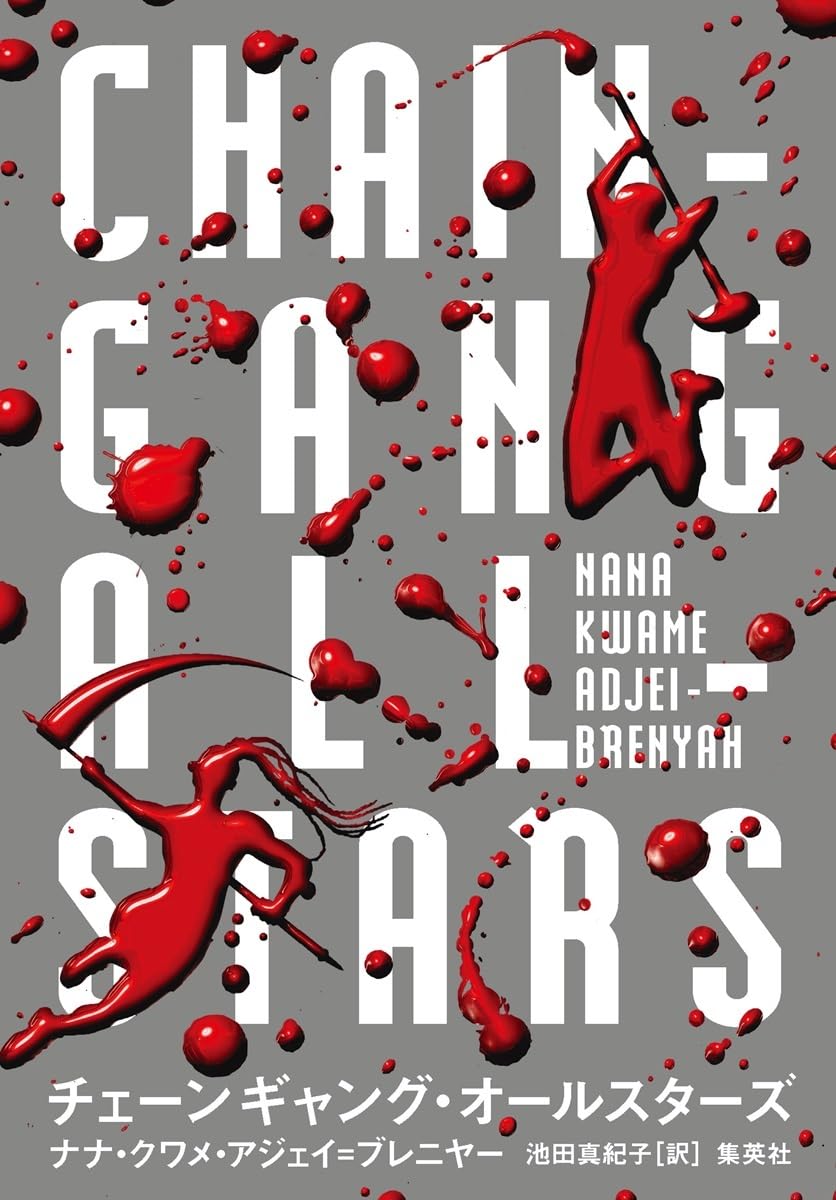カルチャー
アメリカ文学を研究する青木耕平さんによる『チェーンギャング・オールスターズ』のレビュー。
クリティカルヒット・パレード
2025年4月14日
illustration: Nanook
text: Kohei Aoki
edit: Keisuke Kagiwada
アメリカ文学を研究する青木耕平さんが新しい小説をレビューする「クリティカルヒット・パレード」。今回取り上げるのは、ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤーの『チェーンギャング・オールスターズ』だ。
チェーンギャング・オールスターズ。チェーンに縛られたギャングたち。世界を熱狂させるオールスターにして、非道なギャングスターズ。近未来のアメリカにおいて、重犯罪を犯した囚人たちは、観衆のもとで殺し合いをし、その勝利者は自由を得る。その様はストリーミング配信され、全米で巨大ビジネスと化している。人々はその殺し合いに熱狂する。自らの生のために他人に死を与える、それこそが生のあるべき姿だ。またある人々は、その殺し合いに嫌悪を催す。生死を見世物にするなど、人間がやるべきことではない──。
と、ここまで書けば日本の読者は皆『バトル・ロワイアル』を思い出すだろう。アメリカにおいては『ハンガー・ゲーム』、世界的には『イカゲーム』、映画でならば『グラディエイター』があるが、ここ日本ではそれらを出すまでもなく『バトル・ロワイアル』そして多くの格闘・デスゲーム作品のライトノベルや漫画・アニメがある。わざわざ翻訳小説として、そのようなテーマの作品を読む必要など、どこにあるのか?
その通りだ。私もそう思う。だがしかし、待ってほしい。この作品が、現代アメリカ文学最高のルーキーの手によるものだったら? そのゴールデン・ルーキーが、現代アメリカが抱える人種、ジェンダー、産軍複合体、刑務所ビジネスと資本主義、デモとネットフリックスの問題をえぐろうと全精力を捧げた第一長編だとしたら?
ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー。なぜ彼が現代アメリカ文学最高のルーキーと呼ばれるのか、その理由から始めよう。
2015年のグラミー賞授賞式、アルバム・オブ・ザ・イヤーのプレゼンターを務めたプリンスは、「アルバム、ってみんな覚えてる? アルバムは今も重要だよ。」と語った。
2015年、それは、すでに世界中の音楽愛好家の間では当たり前のサービスとなっていたSpotifyに対抗する形でAppleも同様の定額ストリーミング・サービスApple Musicの提供を開始した年だった。
定額制ストリーミング・サービスは、私たちの音楽の聴き方を劇的に変えた。誰もがDJのように、アーティストやジャンルを横断し、好みの曲を取り出して自らのサウンドトラックを作る自由を手にすることが出来たのは素晴らしい革命だ。しかし、ここでプリンスが批判したのは、「差し出されたプレイリストを受動的に流す」リスニングの形である。それは緩慢な消費者行動に過ぎず、アーティストが一つの総合的なコンセプトのもとで作ったアルバムの総合性は軽視される。
そのようなトレンドに逆らうように、アルバムというフォーマットにこだわり続けたプリンスはこの発言をした。そして、この発言は、以下のように続く──「アルバムは今も重要だよ。本や黒人の生命と同じでね」
2015年、すでに全米各地で起こっていたブラック・ライヴズ・マター運動を見据えて、黒人の血を持つプリンスは発言し、大きな喝采を浴びた。このような発言をあえてせねばならぬほどに、黒人の生命は、アルバムは、そして書籍は軽んじられていた。
さて、音楽における「アルバム」を、書籍それもフィクションに置き換えて喩えるならば、やはりそれは「短編小説集」となるだろう。複数のトラックがあり、そのアルバムを代表するリード曲があり、複数のキラーチューンを持つアルバムを我らは「名盤」と呼ぶように、一つの駄作もなく、傑作と呼ばれる短編を持ち、心掴む短編が複数あって、かつ、一つのコンセプトによって貫かれた(プレイリストではなくアルバムの美学を持った)短編小説集を私たちは「傑作」と呼ぶ。
そのような意味で、ここ10年のアメリカで最も優れた短編小説集、それもブラック・ライヴズ・マター運動に深く関わった作品こそが、ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤーによる書籍デビュー作、『フライデー・ブラック』であった。
冒頭に置かれた歴史的傑作「フィンケルスティーン5」で読者の心を鷲掴みにして脳みそを揺らし、ジョージ・ロメロよろしくゾンビとアメリカの資本主義を結びつけた「フライデー・ブラック」、エンターテイメントしての人種差別を描いた「ジマーランド」とキラーチューンが立て続けに連発される。どれも抜群に冴えたエスプリが効いており構成も見事でハッとする気づきが与えられる、見事な短編ばかりが揃った傑出した短編集だ。
ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤーは1991年生まれであり、『フライデー・ブラック』刊行時はまだ30歳手前で、これからの将来を嘱望される書き手だった。書籍と黒人の生命が軽視される時代に、文学界の未来という重責を担わされた若き黒人男性作家。そんな彼が満を持して2023年に初めて書いた「長編小説」こそが本作『チェーンギャング・オールスターズ』である。
さて、その上で『チェーンギャング・オールスターズ』に戻ろう。駄作ではない。が、正直に言って、私はこれが傑作だとは思えない。優に十を超える文学賞の候補となっていながら、どれ一つとして受賞をしていない理由もよくわかる。一言で述べるならば、本作にはノヴェル[長編小説]の快楽が弱い。
ヒラメキがあり、優れたパンチラインがあり、魅力的な登場人物がいて、その政治性・メッセージ性も必然性があり緊迫性がある。が、それだけでは長編小説が傑作になるための魔法はかからない。
ノヴェルと短編小説集とは異なったフォーマットであり、異なった美の感覚がある。たとえどれだけ断片化されていようが、読み終えた時、そこには「長い旅を終えた」満足感が必要だ。ミハイル・バフチンが『ドストエフスキーの詩学』で四大長編について分析したように、様々なヴォイスは聞こえるべきであり、それが統合される必要もないが、長いレンジで眺めた時、そこにはシンフォニーが鳴っていて欲しい。
ウィリアム・フォークナーは「(短編小説と異なり)長編小説はゴミや異物を受け入れる猶予を持つ」といい、村上春樹は「(短編小説と違って)長編小説は文体のネジを緩めなければならない」と言ったが、本作はそのテーマ・政治性において、ブレニヤーの安全なコントロール下のもとにある印象が否めない。私たちは作中で凄惨な切り傷を目にするが、作者の喉元に向けられた危険なナイフとしてのポリフォニーはない。厳しいことを言えば、これはリベラルな作家が書いたリベラルなメッセージを持った作品だろう。(ニューヨークタイムズはジェスミン・ウォード『降りていこう』における同性愛の導入を「インターセクショナリティを書けばいい、という見せかけだけの平等主義」と厳しく批判したが、本作のサーウォーとスタックスにもその批判は向けられるべきだろう)
もちろんこれは述べたように物語の設定があまりに日本の読者には既知なこと、そもそも私がブレニヤーに大きな期待を寄せていたことが原因であり、極私的な感想にすぎない。(とはいえ、英国ザ・ガーディアンはその書評で私と全く同じ観点から本作を「退屈」だと断じている)
それに開き直った上で、長編小説を傑作に変える魔法はどうやってかかるのか、魔法はどうやって作品に宿るのかと、考えずにはいられなかった。
2025年、誰もがスマートフォンを手にしてSNSとショート動画を観る時代だからこそ、長編小説はまだ重要だ、と叫びたい。そのような現代小説を、いや、そのような長編小説だけを、私たちは待っている。
レビュアー
青木耕平
あおき・こうへい|1984年生まれ。愛知県立大学准教授。アメリカ文学研究。著書に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』(共著、書肆侃侃房)。