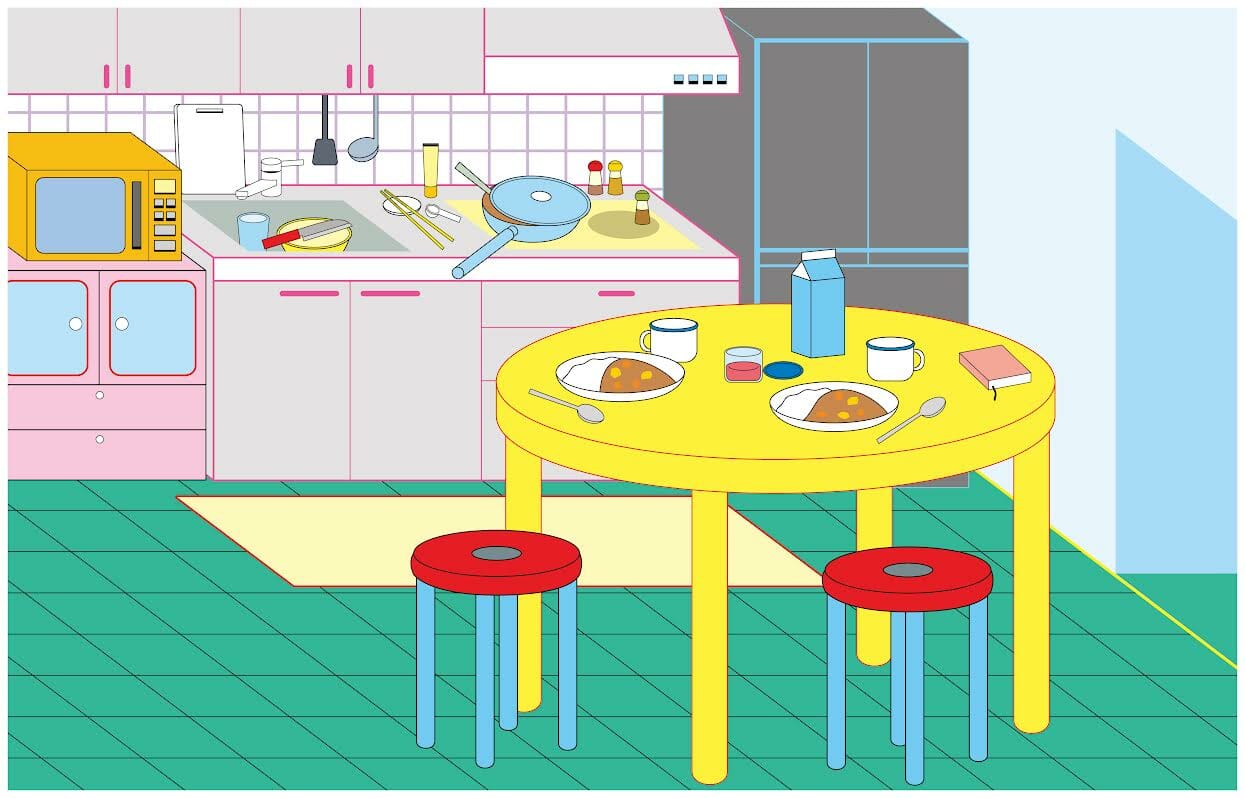カルチャー
ルイ=フェルディナン・セリーヌ著『戦争』をレビュー。
クリティカルヒット・パレード
2024年2月5日
illustration: Nanook
text: Kohei Aoki
edit: Keisuke Kagiwada

アメリカ文学を研究する青木耕平さんが新しい小説をレビューする「クリティカルヒット・パレード」。今回取り上げられるのは、ルイ=フェルディナン・セリーヌ著『戦争』だ。

ルイ゠フェルディナン・セリーヌ (著)
森澤友一朗 (訳)
¥2,750/幻戯書房
ルイ=フェルディナン・セリーヌが戻ってきた。この戦争の時代に、『戦争』と題された作品とともに帰ってきた。舞台は第一次世界大戦、語り手の名はフェルディナン。物語の幕開けはこうだ──「翌る日の夜中もまだしばらくそこから動けなかった。左耳がまるごと、それから口も地面に血糊でへばりついている。耳と口の間では轟音が唸りを立ててる」。戦地に横たわるフェルディナンの上には激しい雨が降り注ぎ、隣には仲間の死体が転がっている。フェルディナンの片腕は酷く負傷し、動かすことができない。銃弾の嵐と爆撃の轟音に包まれるようにしてフェルディナンは眠る。このように戦時下の極限的状況が語られる物語の第一パラグラフは、次のように締められる──「おれはこの頭の中に戦争を捕まえたんだ。そいつはいまだってこの頭の中に閉じ込めてある」。
フェルディナンはなんとか起き上がり、負傷した腕を押さえつつ助けを求め歩いていく。その間ずっと、彼の頭の中に閉じ込められた「戦争」が喚き続ける。
野っ原で我が脳髄の拷問は大音声で響き渡ってた。自分でも聞いてて怖くなるくらい。この音量じゃ戦闘再開をけしかけちまうんじゃ、そう危惧せんばかりの轟音を抱え込んでた。おれはおれの中に戦争も叶わぬほどの轟音を高鳴らしてた。
このセンテンスに出会ったとき、私は不覚にも大きな感動を覚えた。「戦争も叶わぬほどの轟音」が、セリーヌの脳内で高鳴っていたのだ。そして私はいま、セリーヌが閉じ込めて歴史がそれを奪ったはずの『戦争』を読む、という思いがけない幸運にあずかっている──。
2021年、「セリーヌの失われた作品が発見された」というニュースが飛び込んできた。世界中でこれほど文学ファンの興味を攫ったニュースは近年なかった。いったいどんな内容なんだろうと、好奇心が大いに膨らんだ。しかし正直なことを言えば、当時の私はそれが読める日が来るとは、ましてや日本語で読める日が来るとは期待も想像もしていなかった。「2020年代のセリーヌ」だって? 字面だけであまりに危険すぎて、もはやジョークのように感じたのだ。
もし「歴史的傑作とはなにか定義せよ」と問われたら、「その作品が存在しなかったとしたら、現在の文化の光景が変わっていただろう作品」と私は答える。セリーヌの1932年のデビュー作『夜の果てへの旅』は、そのような意味で歴史的傑作である。そもそもセリーヌが何者でどのような作品を書いたのかを知らぬ読者のために、これまた歴史的傑作であるカート・ヴォネガット『スローターハウス5』から引用しよう:
セリーヌは第一次大戦の勇敢なフランス兵であった──頭部に大きな傷をうけるまでは。それ以後、彼は不眠症にかかり、幻聴に悩まされるようになった。セリーヌは医者になり、昼は貧しい人びとの診療にあたり、夜はグロテスクな小説を書くことに没頭した。死との踊りなくして芸術は存在しえない、と彼は書いている。「真実は死だ」と、彼はいう。「おれはいままでそいつとうまく闘ってきた……そいつと舞い、そいつを飾りたて、ワルツを踊りまくった……リボンや羽毛で飾り、くすぐりたてた……」
むろん『スローターハウス5』の副題「死との義務的ダンス」はセリーヌからの借用である。ここ日本でも中上健次が『夜の果てへの旅』を高校時代に読み文学感が一変したことを告白し、日本フリージャズの伝説的サックス奏者である阿部薫は生前唯一リリースしたソロ作品にセリーヌが1936年に発表した第二長編である『なしくずしの死』の名をつけた。セリーヌがいなければ、私たちが目にする文化の光景は今とは少し違っていただろう。
しかし、セリーヌは文学史とりわけフランス文学史から追放されようとしていた。なぜか。1937年、彼は激烈な反ユダヤ主義パンフレットを立て続けに発表したのだ。その時すでにドイツではナチスが政権を奪取していた。二次大戦の勃発、パリ占領の時期も彼は意見を変えず、国内追放にあってもなお自らの主張を撤回しないどころか、戦後サルトルが「セリーヌはナチスに買収された」と書いた時、猛然とくってかかった。未来永劫忘れられない文章を書いたのち、許されない差別的言辞を吐き許されることを死ぬ時まで拒否したセリーヌ。彼が「呪われた作家」と称される理由である。
そんな呪われた作家セリーヌの失われたテクストが90年の時を経て見出され、私たちの前に届けられた。それが本書『戦争』である。詳しい経緯は本書訳者である森澤友一朗氏による素晴らしい訳者改題を確認していただきたいが、なぜ上記のように反ユダヤ主義者の消せない烙印を背負うセリーヌの作品がフランスで刊行されたかといえば、おそらく本書『戦争』の執筆時期が1933-34年と目されているからだろう。つまり本書は32年の『夜の果てへの旅』と36年の『なしくずしの死』の合間、37年の反ユダヤ主義発言以前に書かれた作品なのである。はたしてこれが免罪符となるのだろうか、政治と芸術の関係、倫理と道徳、作家の戦争責任……前世紀と同じ議論が世界中ですでに繰り返されている。
『戦争』に戻ろう。プロットは至極簡単で、物語の大半は野戦病院に運び込まれたフェルディナンの入院記・観察記だ。他の作品同様、「戦争、死、セックス」が中心であるが、言葉こそが真の主役だ。容赦のない悪罵と終わらない呪詛、陰鬱であるが陽気な知性、句点と読点と三点リーダで痙攣する文章が、全てのページで踊っている。
『戦争』の最終シークエンス、野戦病院を退院しイギリスへと向かう船上でフェルディナンはゲロを吐きつつ「海が全てを呑み込んだんだ、海が全てを覆い尽くしたんだ。海に万歳!」と海に感謝し、船酔いの中でこう語る:
戦争ってやつは俺にも別の海を授けてくれたんだ、おれただひとりの海を、吠えたて、この頭のなか大音響で唸りをあげるおれだけの海を。戦争万歳!
セリーヌは「獄中ノート」のなかで「過去」というものに対し「想起せよとばかりに押し付けがましい、不愉快の種」だと述べた。この戦争の時代、憎悪と分断の時代、キャンセル・カルチャーが問題とされる時代に、セリーヌという厄介な過去が戻ってきた。現在の価値観から『戦争』を断罪するのはあまりにも容易だ。女性蔑視であり外国人差別であり倫理的・道徳的退廃だ。ともすれば本当に戦争賛美ともとらえられかねないほどフェルディナンの言葉は暴力的だ。だが、この「過去」を求めたのは「現在」の我々だ。終盤フェルディナンはこう呟く「それにしたって人生ってやつは途方もない。いたるところで道に迷うばかりだ」。私たちは、途方もない人生で道に迷った作家の言葉こそを求めている。死との義務的ダンスは続く。
レビュアー
青木耕平
あおき・こうへい|1984年生まれ。愛知県立大学講師。アメリカ文学研究。著書に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』(共著、書肆侃侃房)。