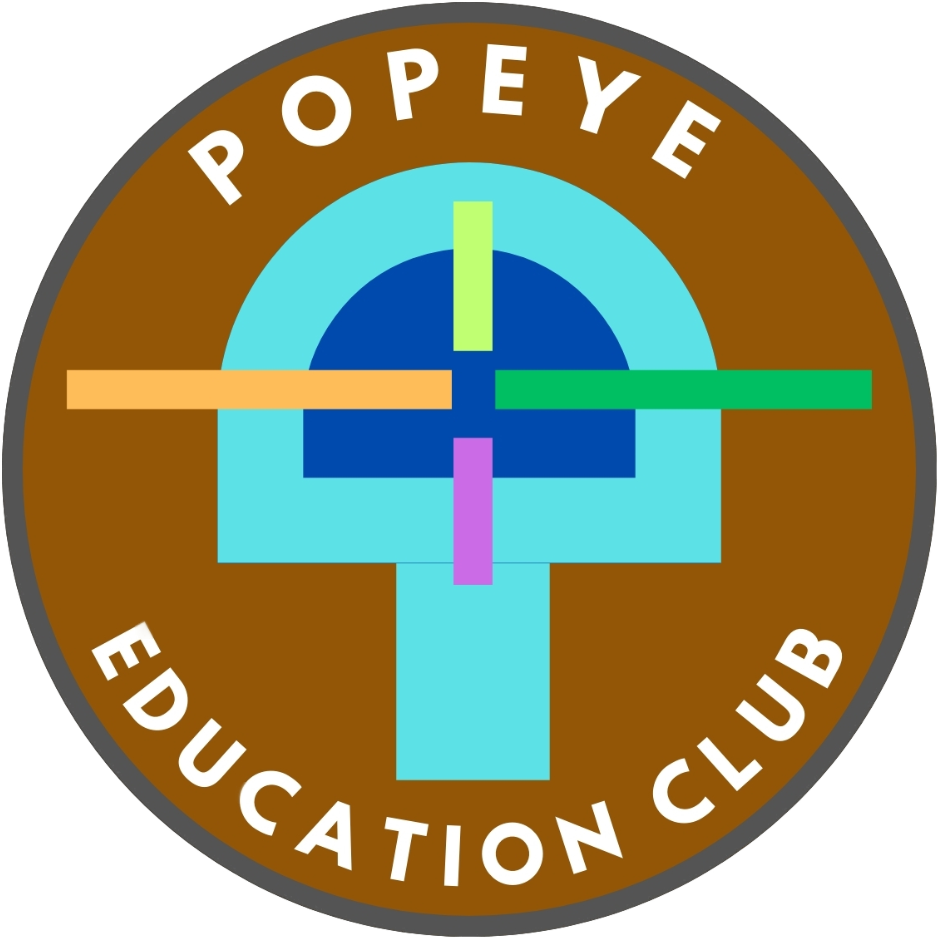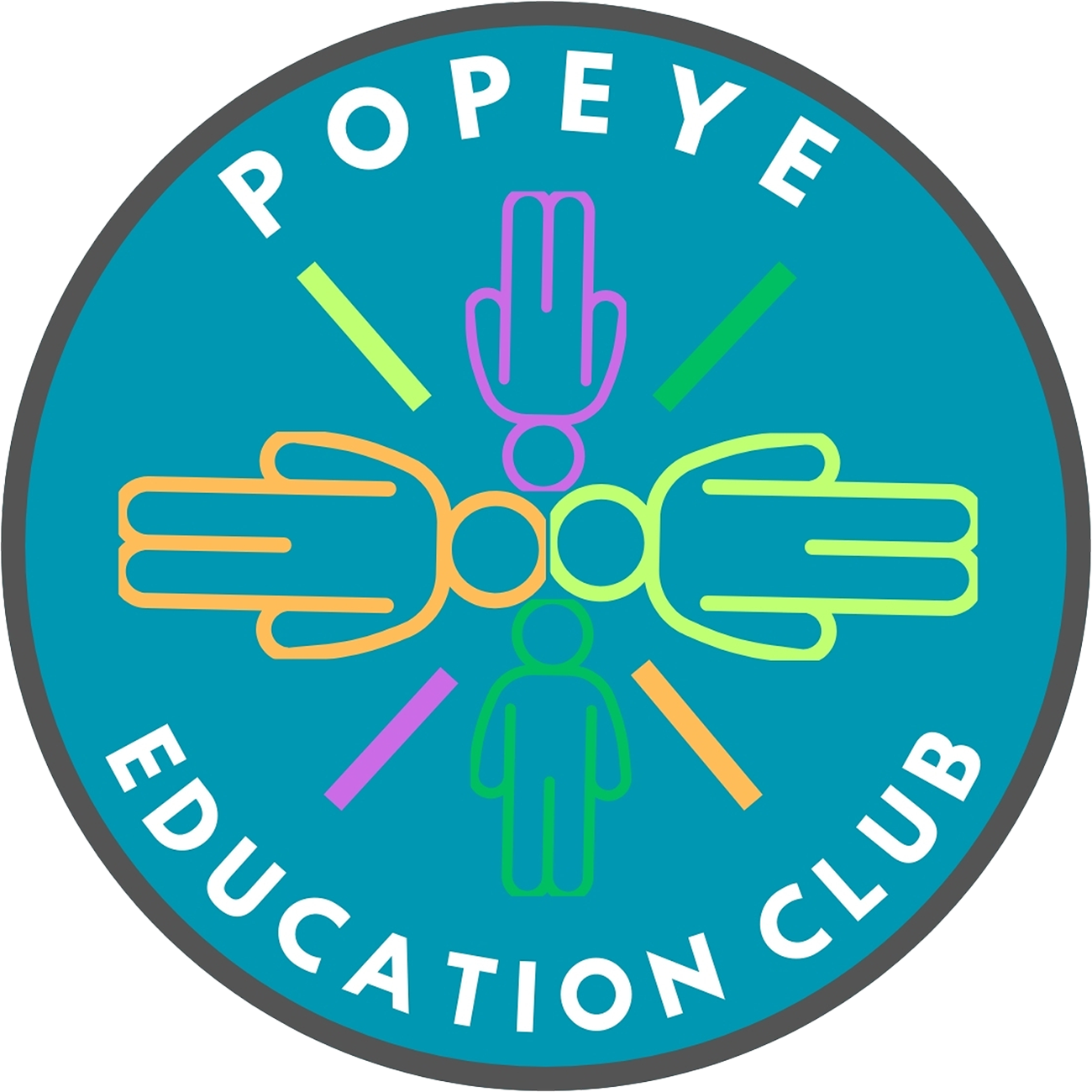トリップ
山の味覚の王様・サマーポルチーニを探せ!/前編
「正直スーパーに売っている舞茸はキノコと思えないというか、それくらい自生している彼らはズバ抜けて香りが……」。そう言葉を選びながら語るのは、岩手県でキノコ狩りを22年間続ける名人・菅原徹さん。これまでヒメタケやワラビなど山菜採りを伝授してくれた山のプロであり、POPEYE Webが10月に開催する「エデュケーション・クラブ/秋のキノコ狩り」の先生である。
・ここからは、イベントを運営する「くらしごとユニオン」の「キザシONLINE SHOP」に移行します。
・イベントの運営に関するお問い合わせは「祭り法人射的」宛にお願いいたします。
山の恵みを自力で採って、下処理をして、食べてみる。その一連の体験があまりに素晴らしかったから、続いて山の幸のエース、「キノコ」狩りを教えてもらうことに。今回狙うはトリュフやマツタケと並ぶ世界三大キノコのひとつであるサマーポルチーニ! さっそく会場となる八幡平市の「県民の森」へ向かう。
八幡平は、岩手県と秋田県にまたがる十和田八幡平国立公園内に位置し、スキー場やホテルが点在するリゾート地。元々は酪農が営まれていたこともあり、高原台地のなだらかな地形が広がる。トレッキングとともにキノコ狩りを楽しめる初心者にもってこいのスポットだ。とはいえ、東京と比べると緯度が高いので、やはり植生は変わる。見渡すと、道路の脇道などの平地でも白樺が群生し、それらが生み出すひんやりとした空気が頬を撫でる。北に来たぞ、という実感がキノコ狩りのボルテージをぐんと高める。逸る気持ちを抑えて、まずは道具の説明をしてもらった。
身を守りつつ、キノコを傷つけないための道具。

服装は長ズボン、長袖のアウター、長靴(または歩きやすい丈夫な靴)でOK。ただし、黒色は⾍が寄って来やすいのでなるべく避けること。菅原さんが手にしている鎌は、地上ではなく、小高い木といった手の届かない場所に生えたキノコを取る上級者向けの専門道具。山菜バッグと同様にホームセンター『DCM』などに売っている。



熊に人間がいることを知らせるために、熊鈴は欠かせない。「山に入っている間は肌身離さず腰にぶら下げて歩くので、こだわる人は音色もなるべく心地いいものを選びますね。中でも真鍮製が最高ですよ」と菅原さん。続いて入れ物は、布地ではなく通気性のいい竹製のカゴがベスト。種類もさまざまあるけど、腰カゴを持っていれば間違いないとのこと。手袋は「背抜き⼿袋」(⼿のひら側だけがゴムになっていて、 指が動かしやすい構造のもの)があれば、採る際にキノコを傷つけない。
知られざるキノコから山を知る、菅原流フィールドワーク。
虫除けスプレーよし、水分補給よし。準備を終えて、一同いざ入山! 菅原さんに続き、ゆるやかな自然歩道を歩く。紅葉前の若々しい山もまた、森林浴をしているようで気持ちがいい……などと浸っていると、突如目の前に白樺の倒木が。表皮にポツポツと寄生するソレを皮切りに授業が始まった。
「おお、ツリガネタケという固いキノコです。漢方薬や健康食品として煎じて飲むのが一般的ですが、それだけじゃなく、昔から着火剤に使われている自然の道具ですね。特徴としては、見てわかるように、倒木など枯死した木に発生することが多い種類です」
当日はイベントの下見も兼ねて菅原さんが講師となり、料理人の平塚章延さん、〈くらしごとユニオン〉の佐藤啓さんとともにフィールドワークを行った。
これもキノコだとはつゆ知らず。すかさずペリッと引き剥がし、ポケットに入れる。サイズ感といい、触った感触はほぼ胡桃のよう。菅原さんはこう続ける。
「木に生えるキノコは一本の木のなかで、栄養分を奪い合う習性を持ちます。で、こいつは強いんですよ。例えば、ツリガネタケと椎茸の2つの菌が入ると、後者は負けてしまうんです。といっても、稀に共生していたりもしますが、固い種類のものがあるときは、柔らかいキノコはないと思っていて大丈夫ですよ」
なるほど、陣地合戦に近いのかもしれない。ファンシーな印象だったキノコにも弱肉強食の世界があったとは。ともあれ、キノコを探すときは倒木を見るのがポイントってことだ。では、地面から生えているタイプはどうやって探せばいいのだろう?
「第一に沢や池など水場が近くにあることが大切です。空気中に水分があると、活発に生えていますね。そして、種類によって変わるので一概には言えないのですが、サマーポルチーニなどメジャーなキノコは次が最大のポイント。風通しが良くて、開けたところに奴らはいます。葉っぱの背丈が高くて地面を覆っているところ、つまり鬱蒼としているとほぼないと思っていいですよ」
レクチャーを受けながら進むこと約20分。たしかに、さっぱりとした場所に生えていることがわかる。それも群生しているのではなく、ポツンと佇みこちらを待ち受けているじゃないか。なんともかわいい。「お宝は奥地や植物の影にひっそりと隠れているに違いない」と思っていた思い込みが覆える。さらに続けて、「本当は暗い方がいいんだけどな……」と呟くもんだからまたしても驚いた。
「実は薄暗い方がキノコは浮き上がって見えるんですよ! なので、僕が一人でキノコを採るときは、陽が上がる前に山に入り、明るくなり出したら降ります。おじいちゃんから教わったことで、サングラスがあっても、自分の場合はイマイチ見えづらいんです。虫も明らかに暗いときはこないですし(笑)。それにカラーバス効果ではないですが、何かひとつの種類を狙うときは、あえて別のキノコを見ないようにも気をつけていますね。その形が意識に刷り込まれてしまうので、お目当てのキノコにピントが合わないんです」
日の出前から人知れず山に入り、静寂とともにキノコを探す。その動物的な視線、その嗅覚を持ち得た山のプロフェッショナルの言葉は、予想を裏切ることばかり。
キノコは地球一大きい生物だった。
「そもそも、キノコは地球一大きい生物なのを知っていましたか? というのも、普段食べるのは子実体(しじつたい)と呼ばれる『胞子をつくるための生殖器官』で、地中や木には母体となる菌糸体(上の写真)が根っこのように張り巡らされているんですよ。で、それぞれのキノコにとって大好きな気温になると地上へ出て、僕らがイメージする形になるわけで」と菅原さん。つまり、普段食べるアレは胞子を飛ばすための姿であり(植物だと花)、土壌に形成された超巨大なコロニーこそ本来のキノコということか。調べてみると、アメリカ・ミシガン州で観測されたキノコは、15万m2(東京ドーム約3個分!)もの範囲に菌糸を広げ、重量は100tと推定されているそう。ならば、実はこの八幡平の山がキノコといっても過言ではないのかもしれない……! アカデミックなことを自然の中で実感を持って知る、これもまたフィールドワークの醍醐味だ。