PROMOTION
こんな仕事があったのか!/Sony編 Vol.1
No.01: シニアアートディレクター 矢代昇吾さん
2022年10月31日
cover design: Masaki Takahashi
photo: Naoto Date
text: Neo Iida
edit: Kyosuke Nitta
小さい頃からずっと、ソニーの製品に魅了されてきた。プレイステーション®も、ブラビア®も、α™(アルファ)も、なんとなく“家電製品”とは呼べないカッコよさがある。1979年リリースの初代からずっと進化し続けている歴代ウォークマンもまたしかり。常に独創的でワクワクするプロダクトを発表し続けているって、本当にすごいと思う。

そんなソニーのデザインを一手に担っているのが、クリエイティブセンターだ。デザイン室として1961年に設立され、「『原型』を創る」というフィロソフィーのもと、エレクトロニクスからエンタテインメント、金融の分野まで、幅広くデザインの可能性を開拓し続けている。現在は日本の他に、イギリス、スウェーデン、中国、シンガポールに拠点を持ち、多国籍なデザイナーが活躍しているという。
POPEYE Webでは、謎につつまれたクリエイティブセンターに潜入! 第一線の現場で働く方々がどんなことを考え、どんなふうにデザインをしているのか、貴重なお話を聞いてみた。まずは1人目、カメラ部門でインダストリアルデザインを担当する、シニアアートディレクターの矢代昇吾さんからスタート。Cinema Lineカメラ『FR7』やヘッドホン『MDR-Z1R』など、数々のプロジェクトに携わる矢代さんのデザインとの向き合い方とは。さらには金継ぎにいそしむ私生活まで、貴重なお話を聞いた。
機能を追求し、必然的に辿り着いたCinema Lineカメラ『FR7』とヘッドホン『MDR-Z1R』

「クリエイティブセンターにはカテゴリーごとに分けたスタジオがあり、僕は“カメラ”のデザインを担当するスタジオに所属していまして、シニアアートディレクターとして主にインダストリアルデザインとコミュニケーションデザイン領域のディレクションを行っています」
横浜にあるソニーシティみなとみらいに到着すると、矢代さんは黒いシャツに黒いパンツ、グレーのニューバランス990といういでたちで出迎えてくれた。ファッションに一切の無駄がない! ソニーのデザインに相通ずるものを感じて、思わず唸ってしまった。
「デザインにはいろいろなアプローチがありますが、僕が行っているのは“ソニーの持つテクノロジーを、使いやすく美しい道具に仕立てて、クリエイターに届ける”ということ。プロダクトデザイン的には、王道でひねりがないように見えるかもしれませんが、これがすごく大事なことなんです」

そう言って見せてくれたのは、発表されたばかりのリモートカメラ『FR7』。映像製作用Cinema Lineシリーズの新製品で、フルサイズセンサーを搭載したレンズ交換式旋回カメラ。パン、チルト、ズームの機構を搭載し、遠隔操作でユニークな視点からの撮影を行うことができるという。
「今までリモートカメラというと、監視カメラのような“記録”のニュアンスを持った製品が主でした。でも今は記録から表現の時代に変わってきていますよね。TikTokに代表されるように、現代は誰でもクリエイターになれて、表現ができる時代です。それなら、リモートカメラも表現のためにアップデートされていい。FR7は映画制作で培われたCinema Line製品群のルックを搭載しています。つまり、映画撮影時にソニーのメインカメラと同じ画が撮れる。これまではリモートカメラの映像を繋げようとすると画質が合わなかったんですが、すべてが一致するようになりました」
つまり、撮影時に人が踏み込めないような場所でも、遠隔操作でバッキバキの画が撮れてしまうわけだ。真っ黒なフォルムもカッコいいけれど、デザイン的なこだわりはどんなところにあるんだろう。


「“機能的な必然性”というのがプロダクトデザインにおいてはすごく大事なんですね。例えばFR7は左右非対称の形をしているんですが、これは右側に駆動のためのギアが入っていて、左側にはレンズ交換のための要素をまとめているから。『こういうデザインがしたいんだ』ではなく、現場のクリエイターの話を聞き、観察し、レンズ交換における一連の所作を最も効率よく落とし込んだ形なんです。コンシューマのカメラをデザインするときも、常にプロのカメラマンから意見をもらいます。一緒にずぶ濡れになってサッカーの試合を撮影したこともありますよ」
「どう使うか」という視点で無駄を省いていくと、自然と見えてくるデザインがあるという。一方、彼の代表作であるハイレゾ対応ヘッドホンのMDR-Z1Rは、「どう最高の音を作るか」というアプローチ。最高音質を実現するため、自然の摂理に従った。

「音のメカニズムは、物体が振動し、それが空気を伝わり、鼓膜を震わせることで脳が“音”として感知する現象です。つまり物理現象によって生まれるものです。それを踏まえると、デザインにも物理現象を取り入れることで、音質を高める究極の形状があるのではないかという考えに至りました」

「わかりやすい例を一つお話しします。音を発生させる振動板というパーツがあり、それを保護するためのグリルがあります。通常のグリルは強度を確保するためにがっちりとした桟で設計されていますが、理想の音質を再現するための遮蔽要素になることがあります。極端に言えば、振動板の前に隔てるものが何もないほうがいい音が出ます。そこで利用したのがフィボナッチ数列です。自然界に存在する法則で、例えばヒマワリの種の配列に見られるもので、限られた面積の中に最も効率よく種が配置されるようできています。このヘッドホンにおいては『いかに効率よく最大の開口を作り、遮蔽要素になる桟を細くしながら強度を保つことができるか』という発想でデザインを作り上げました。様々な形状パターンを音響チームと検証したのですが、自然の摂理に沿ったこのデザインが最も良い結果となったフィボナッチパターングリルを採用しました。測定では、グリルのない状態とグリルをつけた状態で、ほぼ同等の音質を実現できたんです」
飛行機のプロペラに、必然の美しさを見る

自然の法則に学び、無駄を削ぎ落とした結果、美しいデザインが生まれるのも興味深い。矢代さんのデザインセンスは、ソニーに入る前から培われたものなのだろうか。
「以前は大阪のメーカーで商品企画とデザインの両方を担当するという独自スタイルで仕事をしていました。その経験からか、表層的なスタイリングではなく、コンセプト(そのモノの中心をなす価値)に比重を置いてデザインを考えるようになっていきました」
その会社には20代前半から6年ほど在籍。30歳を迎えるときにはひととおり頑張った思いもあり、転職を決意したという。どんな仕事をしようかと考えながらいろんな人に会いに行くうち、過去に手掛けたヘッドホンがグッドデザイン賞をもらったときの選考委員に会う機会があった。ソニーのヨーロッパデザインセンターを立ち上げた第一人者だ。
「いろんな話をしてくださって、そのなかで『ソニーに来たら?』と仰っていただいたんです。ちょうどその頃は、モノリシックデザインという足のないテレビや、ソニー初のミラーレスカメラが出たとき。とても楽しそうで興味を持っていました。ソニーにはすごいデザイナーがいるから、僕もそこでやってみたい。そう思うようになりました」
2011年、クリエイティブセンターの門を叩き、面談を受けた。面接官は全員デザイナーで、みんな個性に溢れていて魅力的だった。当時のトップのデザインディレクターに言われた、「誰かに『あなたの最高傑作は?』と聞かれたら、『次に作るもの』と言えばいいよ」という言葉もカッコよく響いた。晴れて入社し、デザイナーとして数々のプロダクトデザインをするなか、“必然”を強く意識するきっかけがあったという。
「それまでも潜在的には持っていた感覚だったと思うんですが、2015年に森美術館で行われていた『シンプルなかたち展』を観に行ったんです。パリのポンピドゥー・センターのコレクションを持ってきたもので、楽茶碗とかヘンリー・ムーアの彫刻とか、様々な切り口でシンプルな作品を展示していたんですが、そのなかで圧倒的だったのが、飛行機のプロペラでした。人間が考えたアート作品よりも、飛ぶために必然的な形をとったプロペラのほうが、僕にとってはものすごく綺麗に見えて。そこで明確に意識し始めましたね」
デザインを育むクリエイティブセンター
こうした思いを大切に、MDR-Z1RやFR7といったプロダクトを世に送り出してきた矢代さん。その裏側には、デザイナーを力強く支えるソニーならではの風土があるという。
「ソニーの魅力は人だと思いますね。社風も、『人にやさしく、デザインに厳しく』という感じで、作るものに関してはシビアだけど、人を責めるようなことはしません。一人ひとりの個性を尊重し、際立たせているんだろうなと思います。さらに、長年培われたシステムが、そのクオリティを強固なものにしているんです」
デザイン案は、あらゆる方向から鋭い目でチェックされる。この仕組みが群を抜いていると矢代さんは言う。
「案件に対して“審議”というプロセスがあるんです。まずデザイナーは作ったデザインを10人規模の小チームで審議にかけ、プレゼンテーションをします。そこで大枠のコンセプト部分から、小さなデザインの0.1mm単位の形状まで、あらゆる意見をぶつけられる。それを踏まえてブラッシュアップされたものを、別チームも同席する30人規模のスタジオ審議にかける。最後には、新人なら絶対震えてしまうクリエイティブセンター全体の審議が待っています。緊張しますけど、ある意味アピールの場でもあるし、そうやって精査を重ねることでデザインが何段階も抜けていく。デザイナー個々の力に加えて、集合知が合わさるので、よりクオリティが上がっていくんです」
さらに、クリエイティブセンターはデザインの可能性を広げる挑戦を続けている。毎年4月にイタリアで行われるミラノデザインウィーク(家具見本市ミラノサローネと同時期に開催)にも、過去数回にわたりテクノロジーとデザインを軸に作品を出品。2019年には「Affinity in Autonomy〈共生するロボティクス〉」というインスタレーション作品を出品した。人間とロボットの間にどうやって共感や親和性が生まれてくるのかをテーマに、チームでインスタレーションをデザイン。5つの段階でロボットと人間の親和性を表現。近年プロダクトデザインからアート領域にも興味を広げる矢代さんも、ひとつのロボットを手掛けた。中央の棒がゆらりゆらりと行き来し、人が近づくと棒の先端が近寄り、その人の動きに付いていくというもの。映像を見せてもらったら、まるで生きているようだった。矢代さんが表現したのは、人間が自然界の中にある現象に抱く心地よさや共感性だという。

「人間は、自然の摂理に沿って発生する現象に理屈抜きに共感したり、気持ちよさを感じたりするのではないかという仮説を持ちました。そこで重力という自然現象に着目し、振り子運動としてロボットの動きに取り入れています。実際の振り子運動をそのまま再現すると、スピードが速すぎて怖さがあるので、少し遅くしてあります。リアルな運動を再現しつつ、現実では起こりえないゆっくりとしたスピードを持っています。あくまでアートで、プロダクトデザインのように正解があるものではないので、曖昧さを残しながらデザインをしました。とてもオーガニックな動きをするのですが、感覚的には水族館でクラゲを眺めているときのような気持ちよさがあるんです。飲み屋に置いてあったらずっと見ちゃうと思います(笑)」
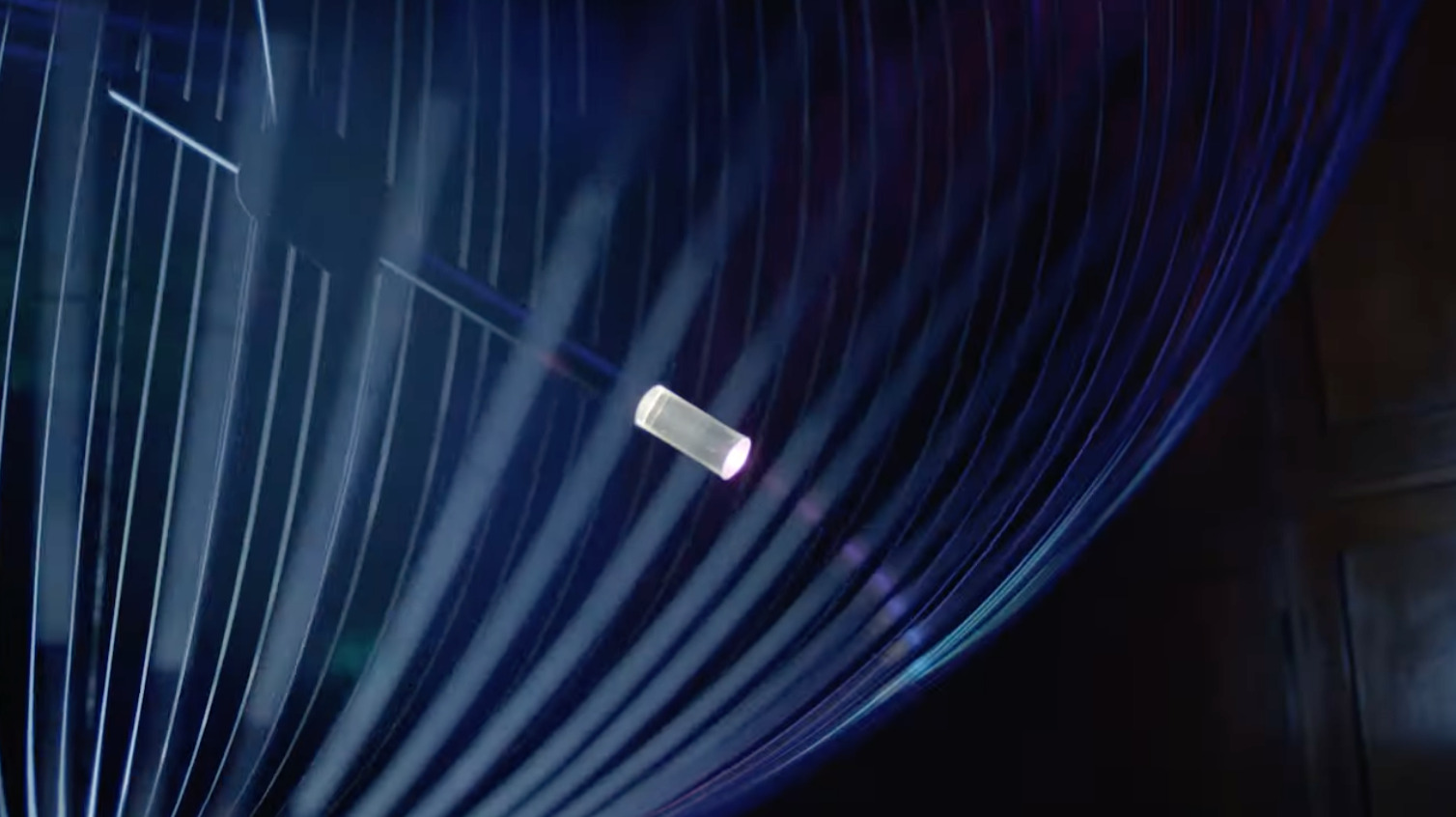


「会期中は常に10人ほどの人がこのロボットを囲んでいたのですが、ロボットがインタラクションをしてくれるのはたった一人だけ。みんな棒に向かって『来て来て』と呼び掛けていて、別の人のところに行ってしまうと、『なんで!』とちょっと嫉妬する方もいたりして(笑)。単なる棒に対して感情移入している姿がとても印象的でした。『気分屋で猫みたい』といった感想もあったり、見た目に生物感やキャラクター性がなくても、モーション一つでここまで心が動くんだということに驚きました。僕が意図したのは、重力の動きによる本能的共感と棒が寄ってきてくれるというインタラクションの面白さだったのですが、来場者の方々の関心はさらに先にありました。来てくれたりくれなかったりする気分屋な感じとか、その不完全さにも共感していて。ロボットには正確さや完璧性を求めがちですが、その真逆の価値に気づけ勉強になりました。この作品を『Imperfection(不完全)』と表した来場者の方もいて、非常に腑に落ちましたね」
金継ぎもまた、物理法則の賜物


「無駄を徹底的に削ぎ落とす」という矢代さんのデザイン哲学は、プライベートでも一貫している。自宅の写真を見せてもらうと、ギャラリーみたいな洗練された空間に、器や木製の机などのアンティークが整然と並んでいた。
「20代の頃の趣味はモダンデザイン一辺倒で、それからあらゆるデザインを見てきましたが、本当の意味での新しさってなかなか生まれないということもわかってきて。家具でも家電でも、はじめに生まれたものは原初的な良さがあるのですが、それ以降はただのバリエーションだなと感じることも多く、ものへの興味も薄らいできた時期でした。ただ、30歳を過ぎた頃、ある骨董の名店で一枚の美しい皿に出合いました。17世紀のオランダで盛んになったデルフト焼というものなのですが、割れて直されているのに結構なお値段だったんですよ。当時、皿への興味も骨董的な価値も知らぬまま、ただその美しさに惹かれて買ってしまったんです」

それが初めて買った骨董だった。
「モダンデザインの領域ではヴィンテージという概念がありますが、せいぜいここ数十年の話。一方、アンティークという領域は紀元前まで選択の幅があり、それだけの年代から自分の視点でものをキュレーションしていくのが楽しかった。一気に視界が開けていくような感覚があって、ものへの興味が再燃していったんです」
ものをたくさん持たず、何かを手に入れたら何かを手放す、というのが矢代さんのスタイル。そうするうちに、自然と特別なものだけが手元に残るようになり、やがて、自分の傾向が見えてきたという。
「選ぶのは、酒器もお皿も割れてるものが多いんですよ。ずっとなんでだろうと思ってたんですけど、コロナ禍で時間ができて、独学で金継ぎを始めたときに気がついて。割れたものの線や欠けも物理法則により引き起こされる造形なんです。何かしらの衝突により生まれる自然の線。器の大きさ、受ける衝撃によって割れる形は様々ですが、根底には物理法則という確固たる働きがあり、それにより生まれる線は必然です。時々、仕上がった金継ぎの線が雷に見えたり、木の根っこに見えたりするのもそうしたことと繋がりがあるように思います。自然によって生まれた線に、自分の引いた線が勝るわけもなく、何か意図を加えるほどに仕上がりがだめになる気がして。だから、ただ割れたままの線、欠けたままの形をなぞるのが、一番綺麗だと思っています」
器に限らず、古い家具にも興味があるという矢代さん。金継ぎをするときに使っているという杉板で作られた江戸時代の文机にも、プロダクトデザイン的な発見があったという。


「安い素材で、めちゃくちゃ軽いんですが、いまだに歪まずに使えています。見ると、桟が正面と背後に1本ずつ、側部には2本。この構造は、ジオ・ポンティが設計したスーパーレジェーラチェアとまったく一緒なんですよ。スーパーレジェーラチェアは、そのルーツをイタリアのキアヴァリに持ち、ポンティが装飾性を排除してモダナイズしたもの。選ばれた職人しか作れない超高度な椅子です。一方、文机は誰でも作れて安価。対極にあるものなのに、『軽さ』という価値を追求した結果、辿り着いた答えが同じというのが非常に面白いなと思いました」
ある意味、これも必然から生まれた形。無理のないデザインは時代を超える。矢代さんが生み出すプロダクトもまた、次の時代の必然になっていくのだろう。
「自由に表現したり、新しく何かを作り出すというより、その必然性を探り当てていくことが、自分にとってのデザインの作業ですね。その考え方が根底にある気がします」
プロフィール

矢代 昇吾
やしろ・しょうご|1980年生まれ。2011年にソニー入社。クリエイティブセンターでMDR-Z1Rやカメラなどのプロダクトデザインを担当。現在はシニアアートディレクターとしてFR7などのデザインを監修する。プライベートでは金継ぎ師としても活動。2023年の12月に展示会も企画中。








