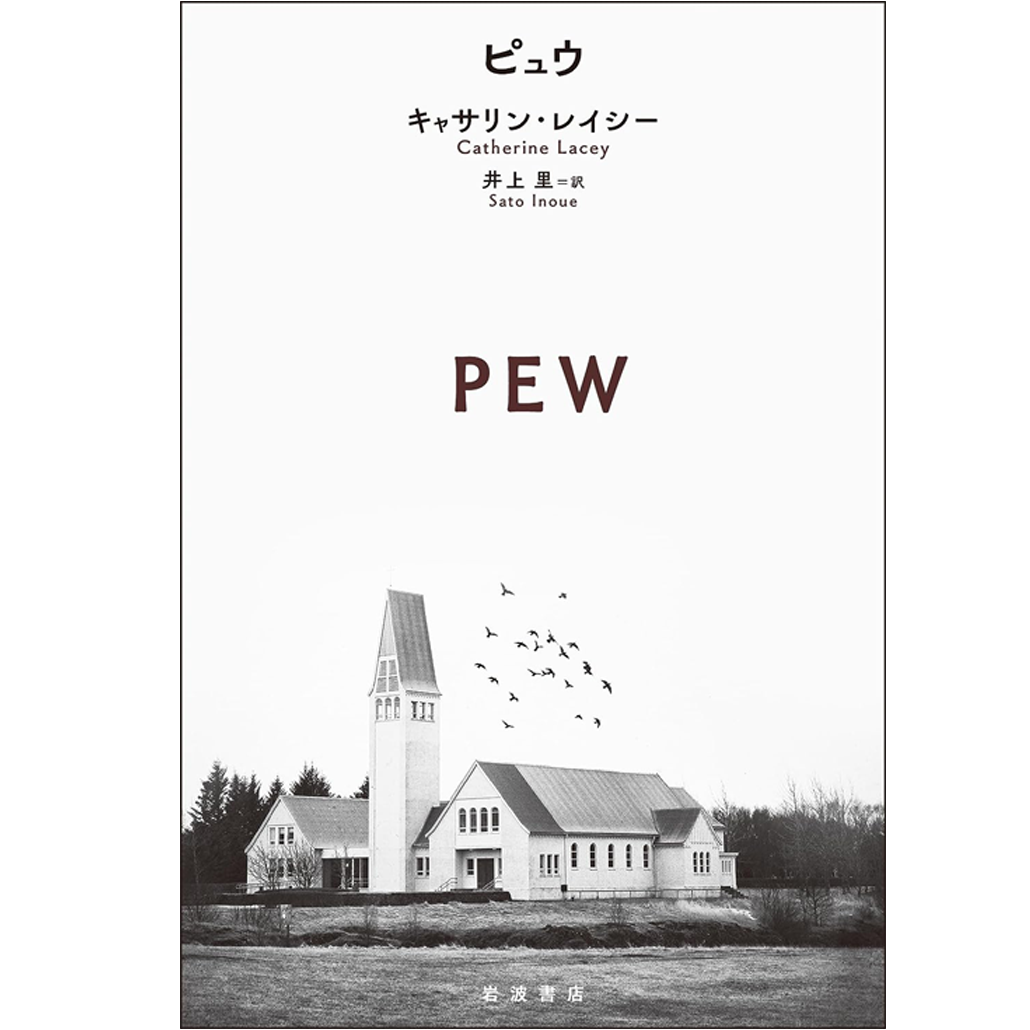カルチャー
キャサリン・レイシー著『ピュウ』をレビュー。
クリティカルヒット・パレード
2023年10月23日
illustration: Nanook
text: Kohei Aoki
edit: Keisuke Kagiwada

アメリカ文学を研究する青木耕平さんが新しい小説をレビューする「クリティカルヒット・パレード」。今回取り上げられるのは、キャサリン・レイシー著『ピュウ』だ。
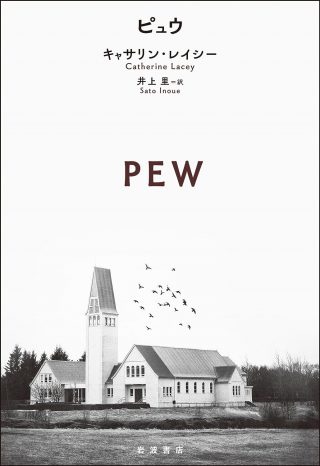
キャサリン・レイシー(著)
井上里(訳)
¥3,080/岩波書店
徹頭徹尾、不穏な書である。本書にたいし、英国ガーディアンは「映画『ミッドサマー』のような絡みつく不安」が漂っていると指摘しているが、『ミッドサマー』でフローレンス・ピューが最後にたどり着く恍惚の瞬間は、『ピュウ』の主人公ピュウには最後まで訪れない。この不安さ、落ち着きのなさのその多くは、主人公ピュウに起因する。
ひび割れた鏡に、二本の脚と腕が映っているのが見える。目を閉じ、いま見たばかりの体を思いだそうとするが、閉じたまぶたの裏にはどんなイメージが浮かぶこともなく、自分がどんな容れ物のなかでいきているか思い出すことはできない。
上記引用は「睡眠」と題された冒頭章からのものだ。ピュウには記憶がない、自分が何者であるかわからない。鏡を見なければ、自分の肉体を認識できない。そして、不明なものは記憶だけではない。
いつだったか、きみは華奢な首をしている、女性らしい首だ、と言われた。女性らしい首なのに、男性らしいがっしりした肩をしている、と。もしかすると逆だったかもしれない──……誰かがこの体について言うことは、いつも、かつて別の誰かに言われたことと食い違っている。自分の肌を見ても、それが何色なのかわからない。
物語全編を通して、ピュウの性別/ジェンダーは不明なままであり、ピュウに出会う人々はピュウが白人か否かで議論する。未成年であるようだが、人によってピュウは12歳にも18歳にも見える。ピュウはジェンダーレスで人種不明、さらには年齢不詳の存在だ。そして、そもそも実は、名前すらない。
短い冒頭章「睡眠」が終わると、「日曜日」と題された本編が始まる。その書き出しはこうだ──「わたしは信者席の上で目を覚ました」
さて、きみのことはなんと呼べばいい? 牧師がたずねた。わたしは暗いテレビ画面に目をやり、そこに映った幽霊のような影を眺めた。きみの名前は? 牧師がまたたずねた。というより、きみの好きな呼び名を教えてくれればいい。
わたしはどんな名前でも呼ばれたくなかった。(太字は原文まま)
記憶もない、名前もない、ジェンダーも人種も年齢もすべて不明であり、かつ、目覚めた町で保護してくれた住人との会話にさえ応じない主人公は便宜的に目覚めた/発見された場所である「ピュウ」と呼ばれることとなった。
驚くべきことに、本作の語り手をつとめるのが「ピュウ」なのだ。一人称を採用する小説は、「語り手」の視点によってのみしか物語世界を見ることができない。記憶の混乱や意図的な虚偽をつくなど、「信頼できない一人称の語り手」をもった作品は数多くある。また、メルヴィル「バートルビー」のように、対話コミュニケーションを拒否するアイデンティティ不詳のキャラクターも文学史上に前例がいる。しかし、スペクテイター誌が指摘するようにまるで「バートルビー本人に語らせるというリスクある戦略」を本書は採用しているのである。これがミステリー小説ならば、語り手の正体が徐々に判明していくというプロットが用意されるのだろうが、『ピュウ』はまったくそうならない。
アイデンティティ不詳なのは主人公・語り手だけではない。本作全体がカテゴリー化不能である。美的な純文学? 明確なメッセージを有した社会派小説? じわじわと追い詰める心理ホラー? 政治的寓話? そのどれのようでもありながら、どれひとつとして確証をもって名指せない。ただ、読み進めていくと、ピュウが目覚めた教会があるのがアメリカ南部であるということは判明する。町の住民は白人ばかりで、どうやら時代は20世紀末のようだ。町にはキリスト教が根付いているが、教義にはない町独自の「祭り」の風習を有しており、その最重要儀式が行われる直前の一週間が物語の舞台となる。
このような要素から、海外書評の多くは本書を南部ゴシックでキリスト教色が強いフラナリー・オコナーと比較し、祭りの様相からシャーリー・ジャクソン『くじ』との類似を指摘している。さきほどミステリー小説ではないと書いたが、井上里氏の見事な訳者解説を読めば、『ピュウ』が先行する文学史にしっかりと依拠し現在のアメリカを見据えた作品であることがわかる。ただし、本書が最も範としている先行作品は、アーシュラ・K.ル=グウィンの「オメラスから歩み去る者たち」であることを、著者自身が明らかにしている。なぜといって、「オメラス」の結末部がエピグラフとして長く引用されるところから、『ピュウ』は始まるのだ。
完璧な調和が保たれた理想郷オメラス。しかし、オメラスの平和は一人の子供の犠牲の上になりたっていた。オメラスの地下の一室には、知的障害をもった子供が幽閉されており、その子は自らの排泄物の上に座り皮膚は爛れ、ろくに食事も与えられず、懸命に助けを求めるも誰も応えない。いや、応えてはいけない。その子に憐れみをみせ優しくした瞬間に、オメラスの平和が崩れる。オメラスに暮らす子供たちは皆、ある年齢を過ぎるとイニシエーションとしてその部屋をその目で見る。皆が強烈なショックを覚えるが、ほとんどの子供は成人になるにつれその不条理を受け入れる。ただ、それを受け入れられない者たちが、のちにオメラスから歩み去る──。
ル=グウィン自身も認めていることだが、このテーマにも先行作品がある。ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』のハイライトをなす、神への反抗者イワンが聖職者である弟アリョーシャに仕掛けた論争だ。そこでイワンは、もし仮に神の平和がこの世に実現し、親に糞便を塗りたくられ苦しむ子供たちの涙も最後には調和のもとに統合されるのだとしたら、そんな調和こそが糞食らえであり、天国への入場券を「謹んでお返し」すると宣言する。神が人の罪を赦すことを人は許すことができるのか? 文学が投げかけた最大の問いがここにある。
『ピュウ』は「現代アメリカ文学」というカテゴリーのなかで考えれば、間違いなく佳作であり一読に値する作品だ。ジェンダーや人種や宗教右派や保守的な南部をめぐる寓話として、見事に現在のアメリカが抱える問題を抉っている。正しくル=グウィンやドストエフスキーのテーマも引き継がれている。が、引き継がれているだけだ。オメラスの子[たち]は、現代アメリカの問題を照射するためにオメラスから歩み去った/鎖から解き放たれたのか? ──私の『ピュウ』への不満はこの一点に尽きる。
これが不当な言いがかりであることは承知している。著者キャサリン・レイシーは、ル=グウィンの想像力を借りて物語を創造したわけで、この問いに答えてアップデートせよ、というのはクレームでしかない。が、ル=グウィン「オメラス」を引用するということは、私のようなクレーマー読者を引き寄せるということであり、それは著者もわかっていたはずだ。私は著者とほぼ同年代であり、インタビュー等を漁ると宗教的なバックグラウンドが似ている。そのうえでいえば、本作におけるキリスト教の描写は甘すぎる。オコナーと肩を並べるにはまだまだ遠い。信仰に悩んだ経験を持つ人間の文章だなんて一ミリも思えな……すみません、取り乱しました。あらためて本作は、非常に優れたアメリカ現代文学です。ただし、文学にある種の超越を求めるのならば……いや、どのみち読んで、ぜひ私に忌憚なき感想を教えてください。
レビュアー
青木耕平
あおき・こうへい|1984年生まれ。愛知県立大学講師。アメリカ文学研究。著書に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』(共著、書肆侃侃房)。
ピックアップ

PROMOTION
うん。確かにこれは着やすい〈TATRAS〉だ。
TATRAS
2024年11月12日

PROMOTION
〈バーバリー〉のアウターに息づく、クラシカルな気品と軽やかさ。
BURBERRY
2024年11月12日

PROMOTION
タフさを兼ね備え、現代に蘇る〈ティソ〉の名品。
TISSOT
2024年12月6日

PROMOTION
ホリデーシーズンを「大人レゴ」で組み立てよう。
レゴジャパン
2024年11月22日

PROMOTION
「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3Sを体験してきた!
2024年11月22日

PROMOTION
人生を生き抜くヒントがある。北村一輝が選ぶ、”映画のおまかせ”。
TVer
2024年11月11日
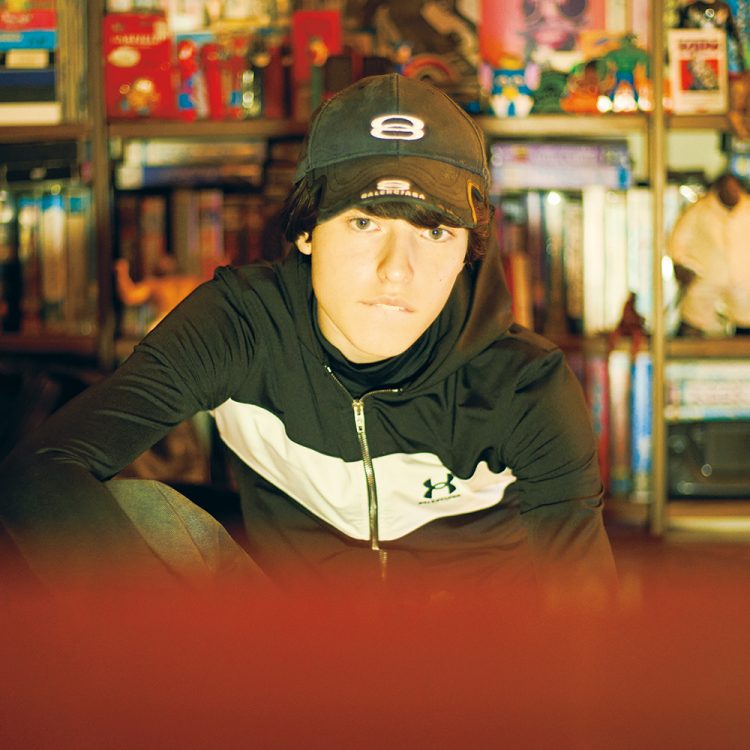
PROMOTION
〈バレンシアガ〉と〈アンダーアーマー〉、増幅するイマジネーション。
BALENCIAGA
2024年11月12日

PROMOTION
〈adidas Originals〉とシティボーイの肖像。#9
高橋 元(26)_ビートメイカー&ラッパー
2024年11月30日

PROMOTION
レザーグッズとふたりのメモリー。
GANZO
2024年12月9日

PROMOTION
メキシコのアボカドは僕らのアミーゴ!
2024年12月2日

PROMOTION
〈ハミルトン〉と映画のもっと深い話。
HAMILTON
2024年11月15日

PROMOTION
胸躍るレトロフューチャーなデートを、〈DAMD〉の車と、横浜で。
DAIHATSU TAFT ROCKY
2024年12月9日

PROMOTION
〈ハミルトン〉はハリウッド映画を支える”縁の下の力持ち”!?
第13回「ハミルトン ビハインド・ザ・カメラ・アワード」が開催
2024年12月5日

PROMOTION
この冬は〈BTMK〉で、殻を破るブラックコーデ。
BTMK
2024年11月26日

PROMOTION
〈ティンバーランド〉の新作ブーツで、エスプレッソな冬のはじまり。
Timberland
2024年11月8日