#50 夏のTシャツ事情と音声スナップ。
2023年7月22日
第50話(!)となる今週は、今夏のTシャツの選び方について会議中です。会議でもないか。個性を出したり消したりできる万能な無地Tか、思想を軽めにプレゼンテーションできるプリントTか、もしくは最近見かけないピチピチタイトなVネックの黒T(いるところにはいる……)か、まあ、世の中にはいろんなTシャツがあるけれど、僕らは今何を着ればいいのだろうか? Tシャツの脱ぎ方についても討論中。出演者/宮本賢(POPEYE Webエディトリアルディレクター)、国分優(POPEYE Webクリエイティブディレクター)、トロピカル松村(編集者/POPEYE Webライター)
ピックアップ

PROMOTION
新しい〈グラミチ〉を着て、街へ海へ。
GRAMICCI
2024年3月29日

PROMOTION
〈adidas Originals〉とシティガールの肖像。
#2 Erika Murphy(24)_Musician
2024年4月11日

PROMOTION
特別な〈ル ラボ〉が京都にオープン。
2024年4月5日

PROMOTION
柚木沙弥郎の作品と老舗の技術が詰まった〈セル〉のランドセル。
2024年3月29日

PROMOTION
街も山も〈THE NORTH FACE〉のレインブーツ『TNF Rain Boots GORE-TEX』があれば。
2024年3月30日

PROMOTION
〈アウトドアプロダクツ〉はこうでなきゃ! ゆるくてタフで機能的なアメリカ製バッグ。
OUTDOOR PRODUCTS
2024年3月29日

PROMOTION
〈ナナミカ〉とオルカ
nanamica
2024年3月29日

PROMOTION
〈ティンバーランド〉スリーアイの魅力を長谷川昭雄さんに尋ねた。
Timberland
2024年4月24日
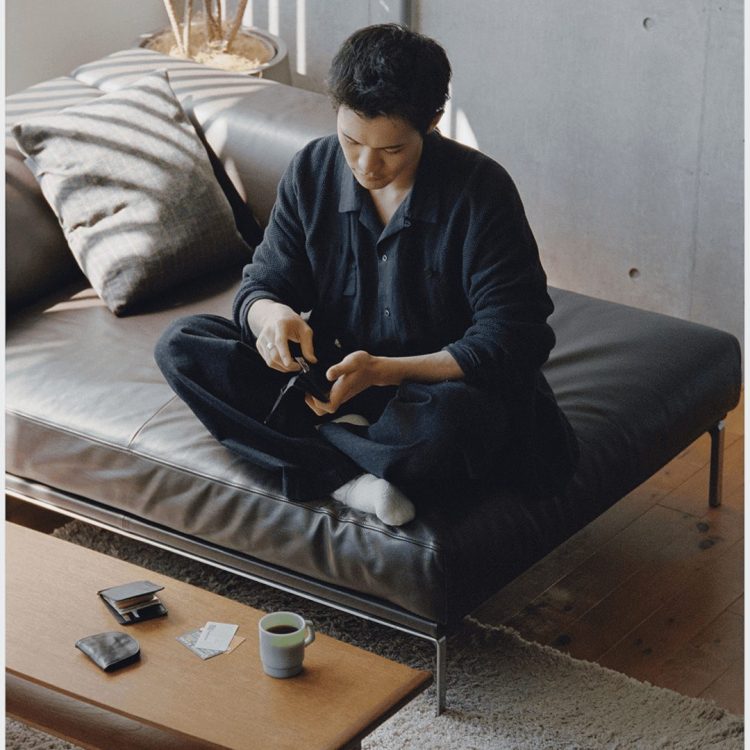
PROMOTION
春の早朝は〈イル ビゾンテ〉のキャニオンレザーとともに。
IL BISONTE
2024年4月11日

PROMOTION
懐かしいけど、新しい。〈VANS〉の「NEW JAZZ」にターコイズブルーが登場。
ABC-MART
2024年3月29日

PROMOTION
〈KEEN〉の代名詞「UNEEK」が10周年。進化を続けるニュースタンダードを履きこなす。
Created by GINZA
2024年4月12日

PROMOTION
〈マーガレット・ハウエル〉と東京の雨。
2024年4月9日

PROMOTION
100周年を迎えた〈カルティエ〉の「トリニティ」リング。
Cartier
2024年4月9日